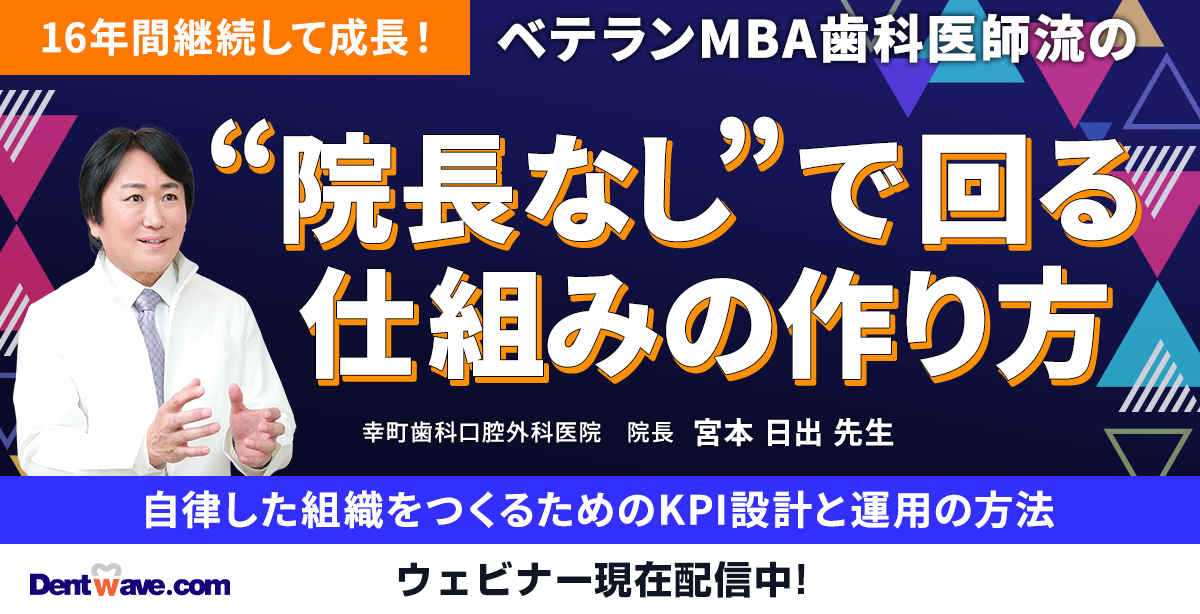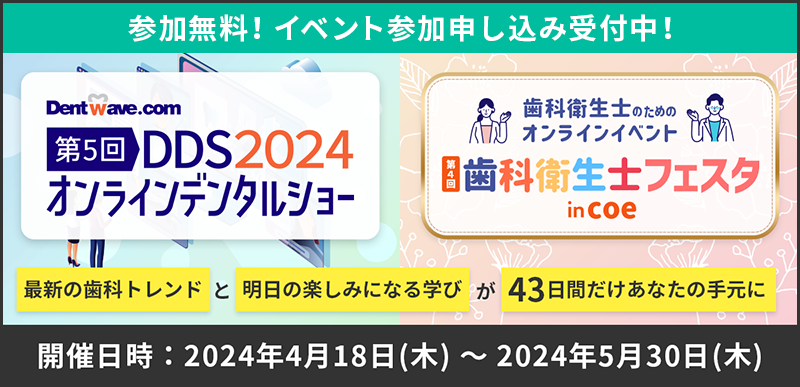この記事は
無料会員限定です。
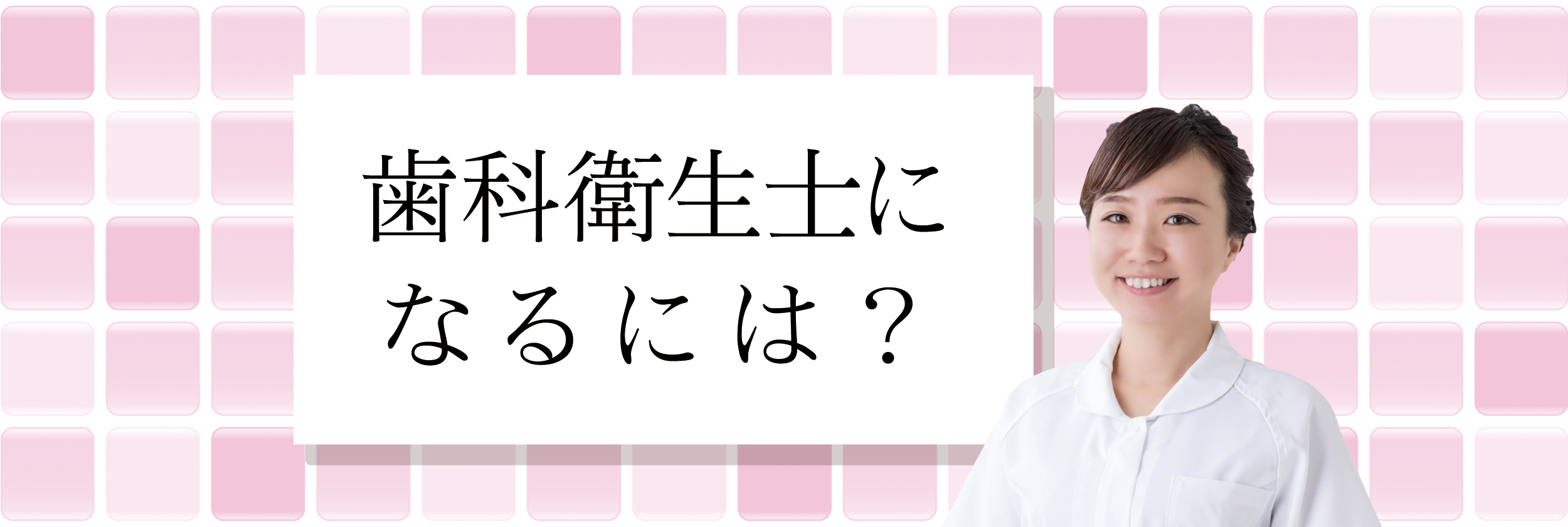
歯科衛生士になるには高校を卒業後、歯科衛生士の専門学校や短期大学、大学に通う必要があります。専門学校・短期大学は3年制、大学は4年制です。学校で歯科に関する知識や技術を習得し国家試験に合格すると、晴れて歯科衛生士になることができます。
なお歯科衛生士の国家試験を受けるための受験資格は、指定された学校を卒業した(あるいは現在通っており卒業する予定がある)ことで得られます。つまり歯科衛生士になるにはまず学校へ通うことが必須で、独学で歯科を学んだとしても国家試験を受けることはできません。また学校が定める卒業試験などに合格できず、卒業資格を得られなかった・留年が決定した場合も国家試験を受けることはできません。
歯科衛生士が活躍する場は全国の歯科医院に限らず、大学病院や総合病院、保健センター、介護施設、企業などさまざま。大学院に進学して研究者になる道もあります。また歯科衛生士は、国家試験に一度合格すればその資格を一生涯使用することができます。例えば結婚・出産によりブランクが空いてしまっても、資格や免許の更新は必要ないため復帰しやすいです。加えて活躍の場も多いため、歯科衛生士という職業は女性に優しい職業と言えます。
歯科衛生士の国家試験について
歯科衛生士の国家試験は現在マークシート形式で、記述式問題や技術試験はありません。そのため学校側が卒業前に技術試験を設けていることも多いです。なお受験にはあらかじめ願書の提出が必要で、受験料は14000円ほど。願書は学校に通っていれば手配してもらえることも多く、指示された書類を用意し提出すればまとめて提出してもらえます。
その他国家試験の難易度や日程、試験内容などについてご紹介します。
①難易度・合格率
歯科衛生士国家試験の難易度は、やや易しめと言えます。合格点・合格ラインはおよそ6割に設定されており、合格率は90%台後半を維持しています。過去10年間を見ても、合格率が90%を下回ったことはありません。
歯科衛生士国家試験は、学校で習った知識が定着していれば合格できるでしょう。全国で毎年7000人ほどが受験しています。また学校全体で模試を受けるなど、歯科衛生士国家試験に向けたサポートがあることがほとんどです。
②試験日時・日程
歯科衛生士国家試験は現在、3月の第一日曜日に行われています。当日のタイムスケジュールは例年以下のようになっています。
| 8:45~ | 試験についての説明 |
| 9:30~12:00 | 試験(午前の部) |
| 13:30~16:00 | 試験(午後の部) |
| 16:00 | 試験終了・解散 |
午前の部・午後の部に分けられ、両方への参加が必須です。なおタイムスケジュールは変更になる可能性もあります。
地域によっては天候などにより交通機関の乱れが起こることも。試験会場が遠い場合は前泊するなど、余裕を持って行動しましょう。
③試験会場
歯科衛生士国家試験の会場は、全国に10か所ほど用意されています。例年の試験会場は以下の地域に用意されています。
- 北海道
- 宮城県
- 千葉県
- 新潟県
- 愛知県
- 大阪府
- 広島県
- 香川県
- 福岡県
- 沖縄県
いずれも大学や専門学校のキャンパスが利用されることが多いです。なお毎年同じではないので注意が必要です。
④試験内容・科目
歯科衛生士国家試験の例年の試験内容・科目は以下の通りです。
- 人体(歯・口腔を除く)の構造と機能
- 歯・口腔の構造と機能
- 疾病の成り立ちおよび回復過程の促進
- 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み
- 歯科衛生士概論
- 臨床歯科医学
- 歯科予防処置論
- 歯科保健指導論および歯科診療補助論
こちらも毎年同じではないので注意が必要です。
学校に通っていた3〜4年間で学んだ分野から、毎年満遍なく出題されています。そのため特定の分野に絞るよりは、過去問題・問題集を見ながら全体を網羅するように勉強すると良いでしょう。勉強した分野が国家試験で出題されなくても、歯科衛生士として働き始めると必要になる知識ばかりです。
⑤合格発表
歯科衛生士国家試験の合格発表は、毎年3月末に行われます。指定された時間になると合格者の受験番号が公開され、インターネット上で見られます。
合格発表の時期が3月末ということもあり、国家試験の合否が分からないまま就職先の決まる人がほとんどです。というのも歯科衛生士国家試験の合格率は毎年かなり高いため、合格を前提として採用されます。
歯科衛生士の国家試験に落ちてしまったら
歯科衛生士の国家試験が不合格だった場合でも、翌年以降に再受験が可能です。学校を卒業したばかりでなくても、過去に指定された学校を卒業していれば受験資格が得られるからです。就職先が決まっていたのに不合格だった場合は、採用取り消しとなることがほとんどでしょう。歯科衛生士の資格を持っていなければ患者さんを診ることができないからです。歯科助手であれば資格が必要ないため、アルバイトをしながら試験勉強して再受験すると良いでしょう。
また企業など歯科衛生士枠としての採用でなければ、採用取り消しにならないこともあるようです。
他の歯科衛生士コラムを読む
セラミック・【これだけは押さえておきたい】セラミックのきほんのき
・【これだけは押さえておきたい】保険適用になるセラミック
インプラント
・【これだけは押さえておきたい】インプラントのきほんのき
・【これだけは押さえておきたい】インプラント周囲炎とは
ライフスタイル
・歯科衛生士が仕事中にメイク崩れを起こさないための方法
・日本歯科衛生士会の「認定資格」とは?分野A・B・Cの審査資格を解説
転職
・まずは何をすべき?転職を考えたらやるべきことと転職先の決め方
・【歯科衛生士の転職事情】転職理由や転職先の探し方を解説!
ホワイトニング
・これだけは押さえておきたいホワイトニングのきほんの「き」
マウスピース
・マウスピース矯正の種類・メーカーと違い一覧。矯正患者へのTBI方法
・【これだけは押さえておきたい】マウスピース矯正のきほんのき
歯科衛生士ができること(仕事内容)
・歯科衛生士 できること できないこと
・歯科衛生士になるには?

浜崎 実穂
東京医科歯科大学卒業後、大学病院に歯科衛生士として勤務。大学の卒業研究では、日本歯科衛生学会の学生研究賞(ライオン歯科研究所賞)を受賞。2019年4月からフリーライターに転向し、自身で立ち上げた歯科メディアは売約を達成。現在は「歯科衛生士ライター」として活動し、歯科企業や歯科医院でライティング業務を行う。
東京医科歯科大学卒業後、大学病院に歯科衛生士として勤務。大学の卒業研究では、日本歯科衛生学会の学生研究賞(ライオン歯科研究所賞)を受賞。2019年4月からフリーライターに転向し、自身で立ち上げた歯科メディアは売約を達成。現在は「歯科衛生士ライター」として活動し、歯科企業や歯科医院でライティング業務を行う。
記事提供
© Dentwave.com




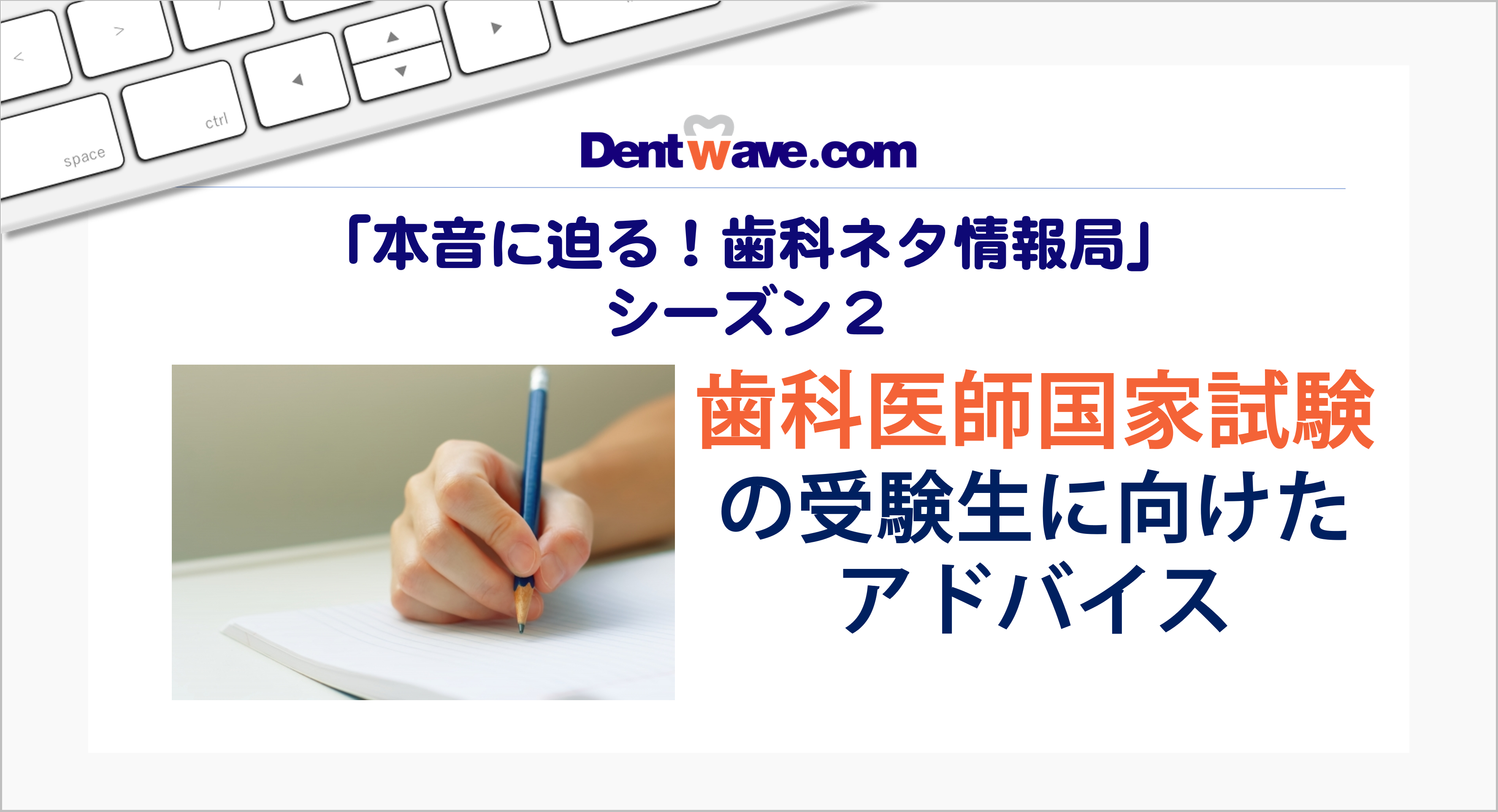
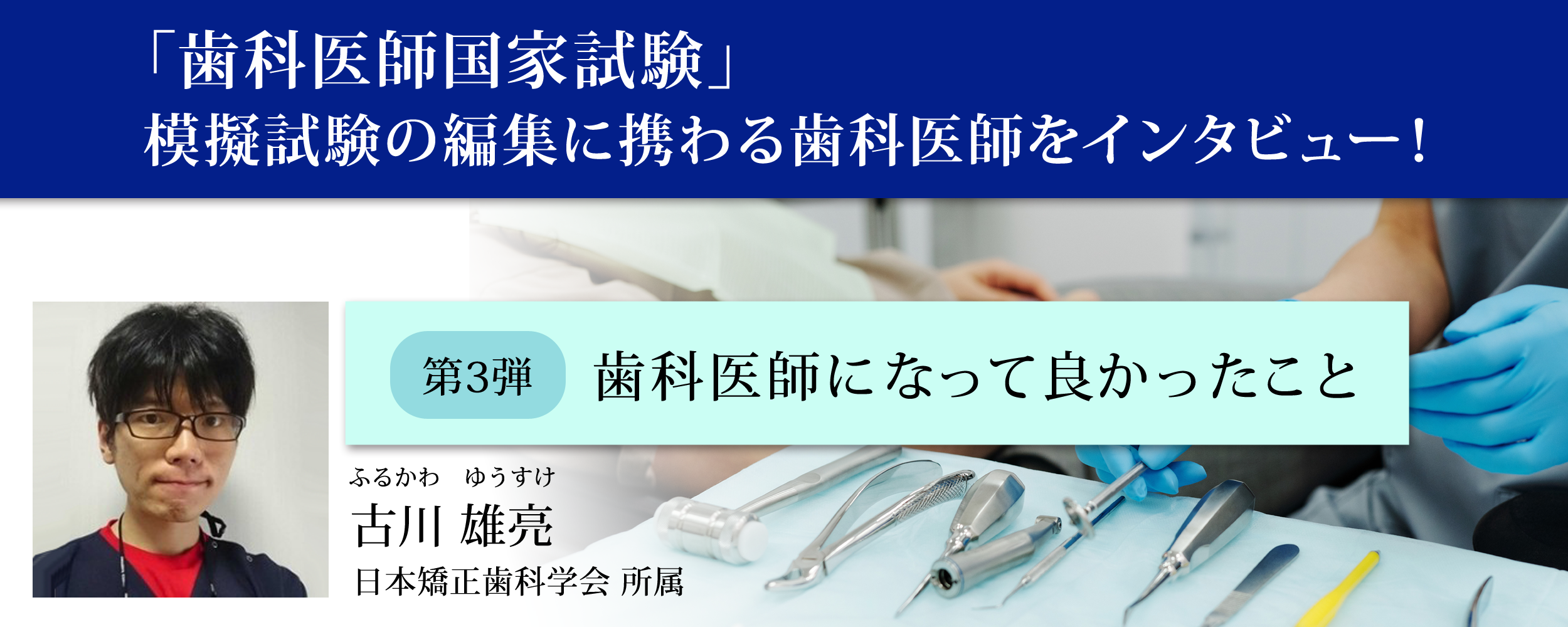
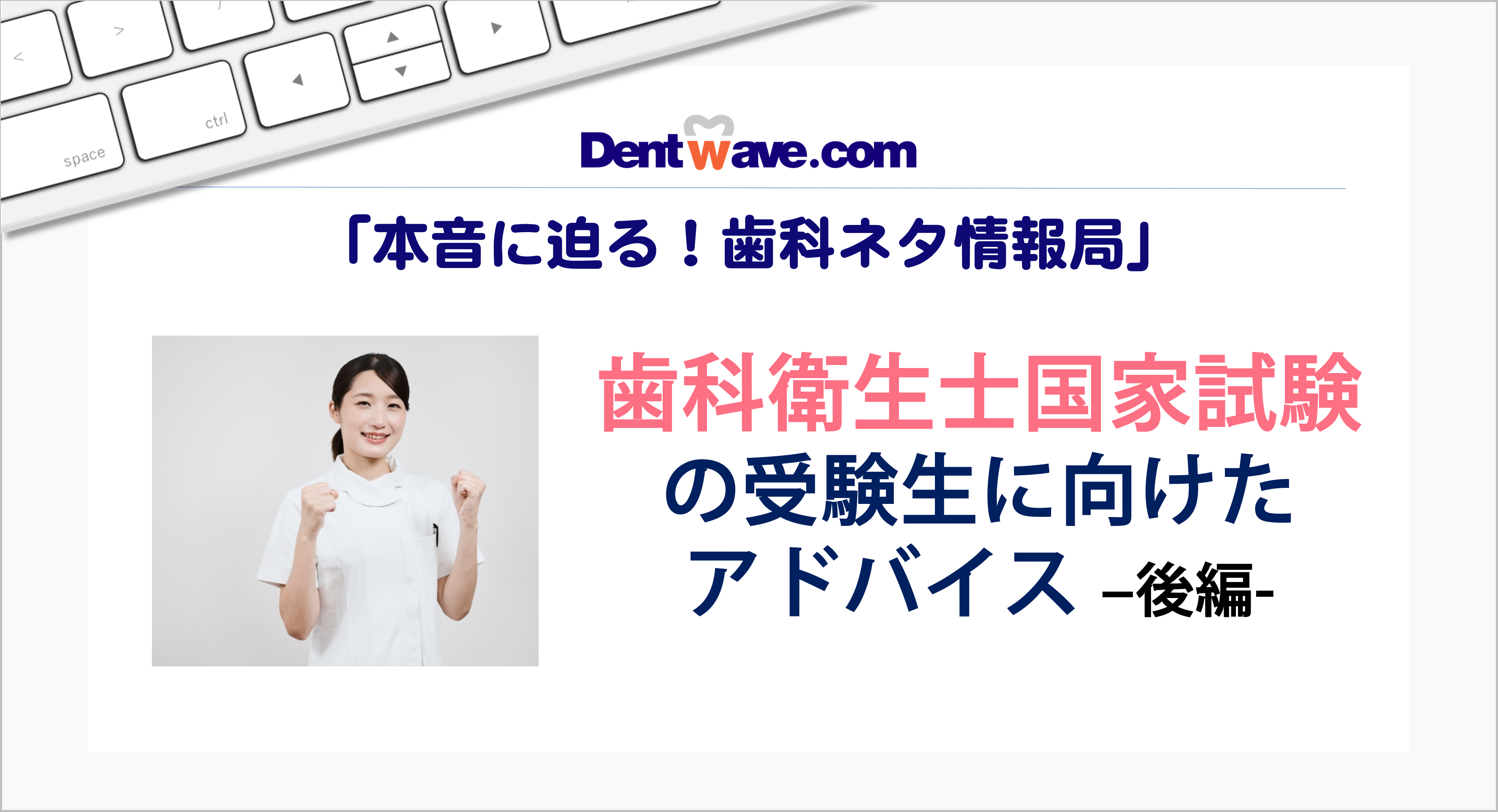
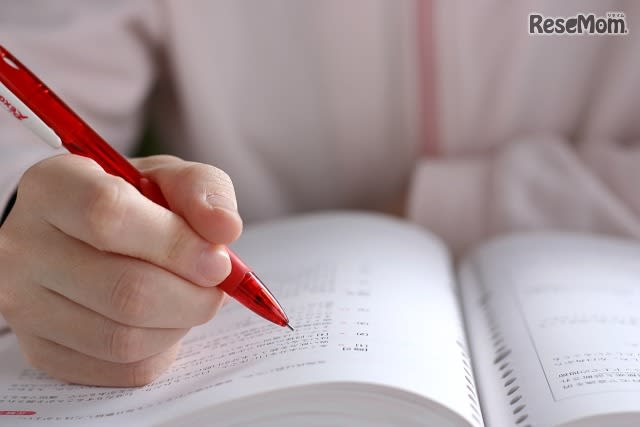

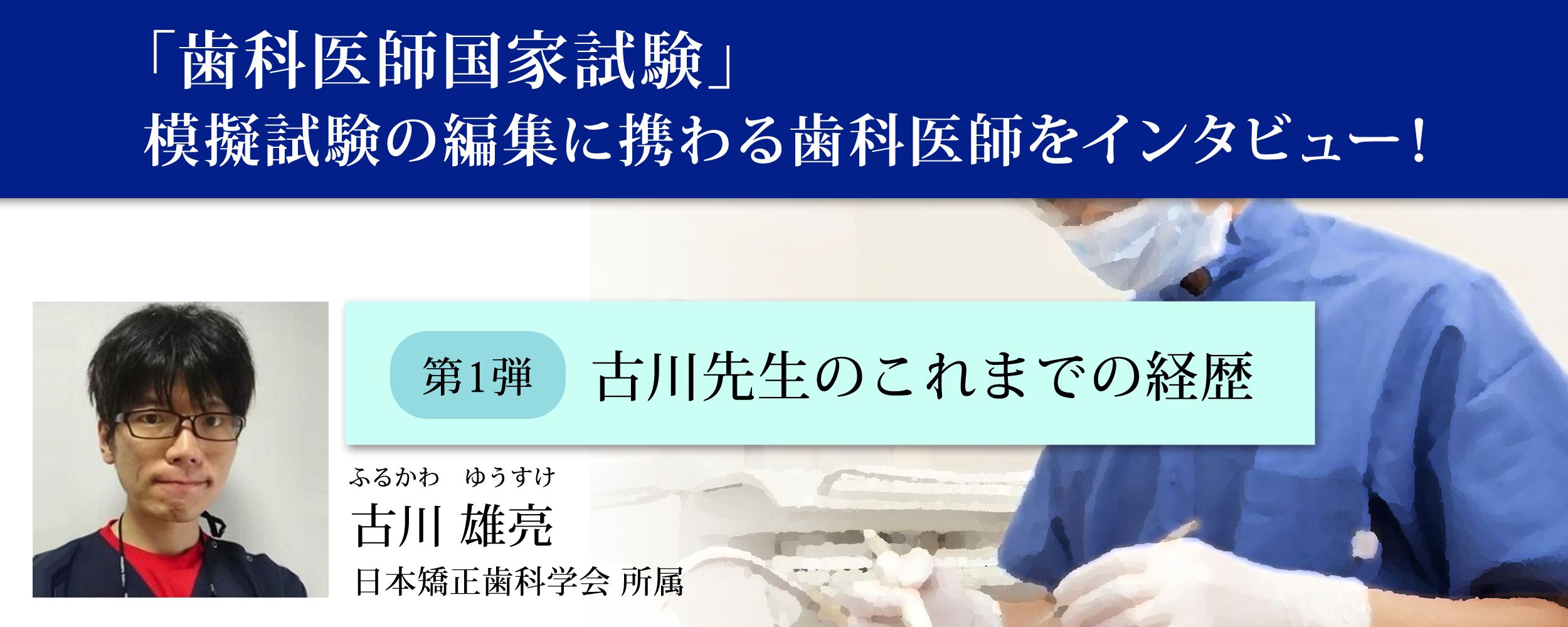
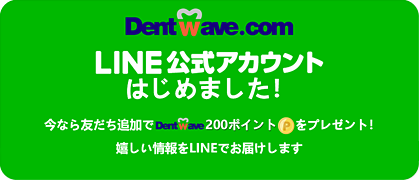 LINE公式アカウントはじめました!
LINE公式アカウントはじめました!
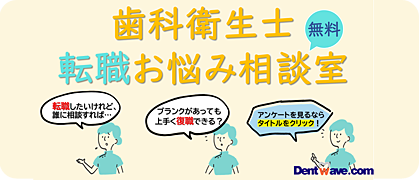 歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
 歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
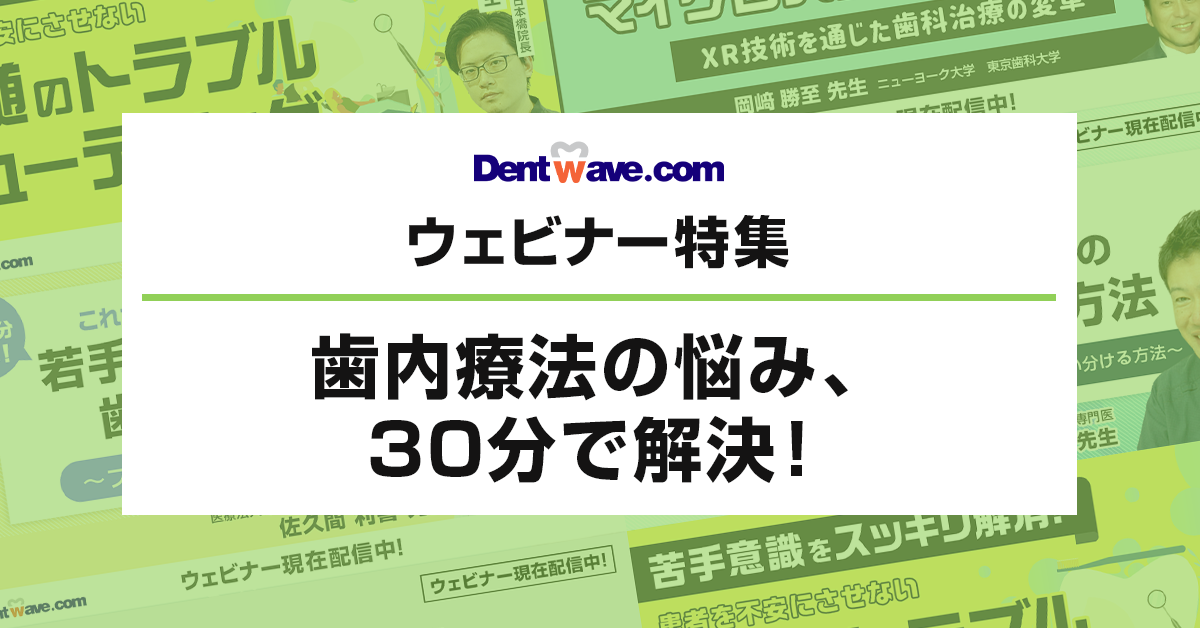 歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
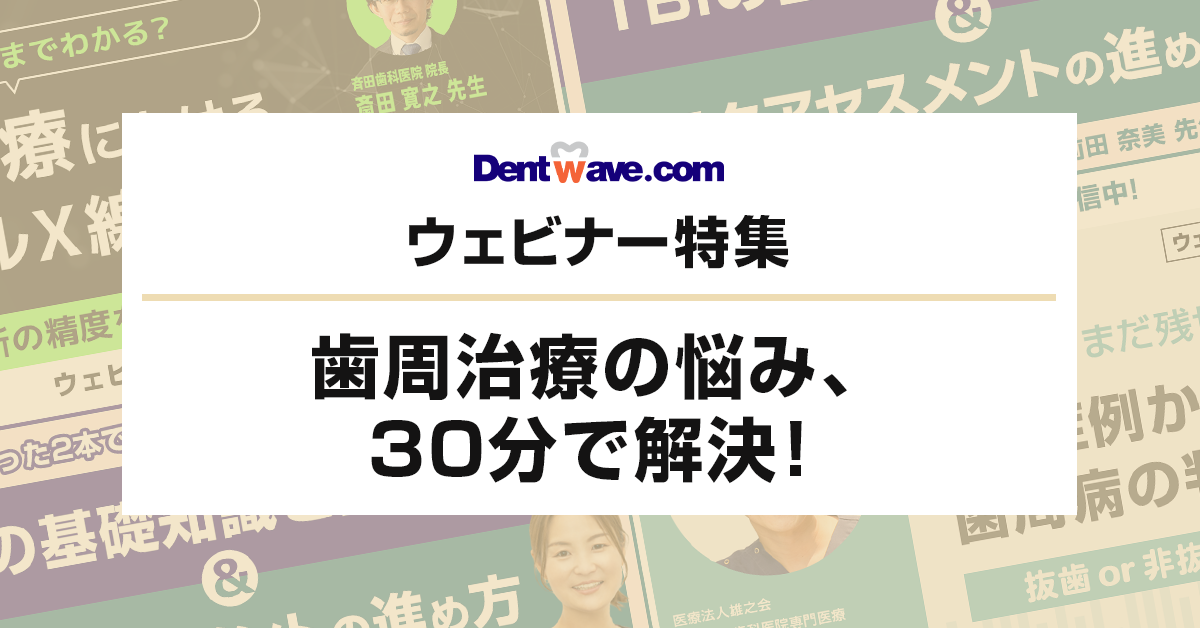 歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。