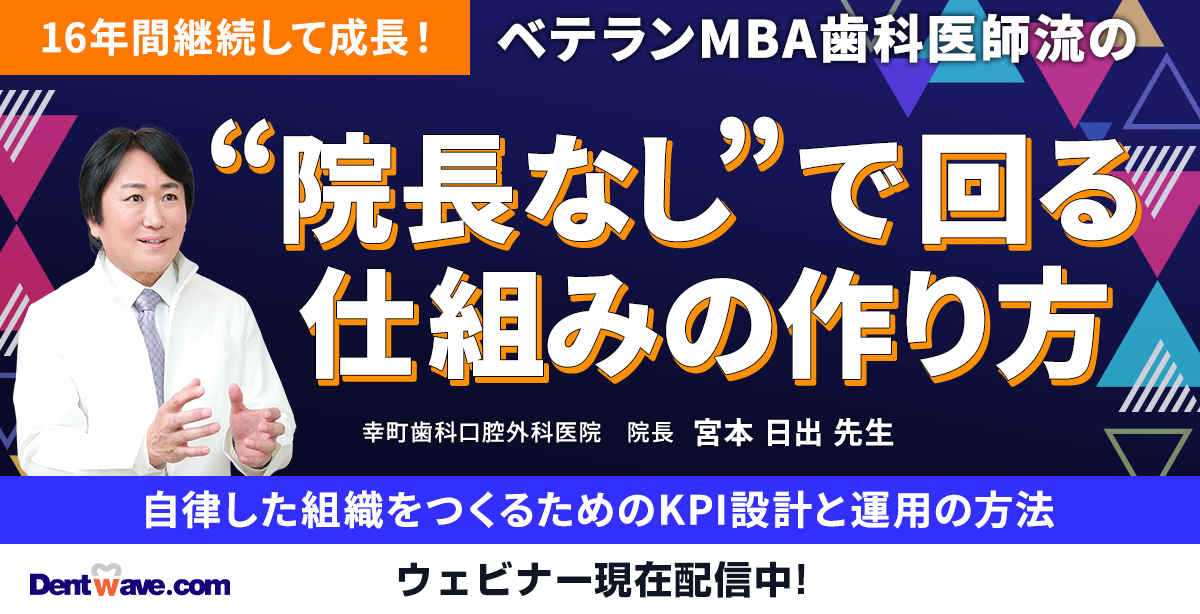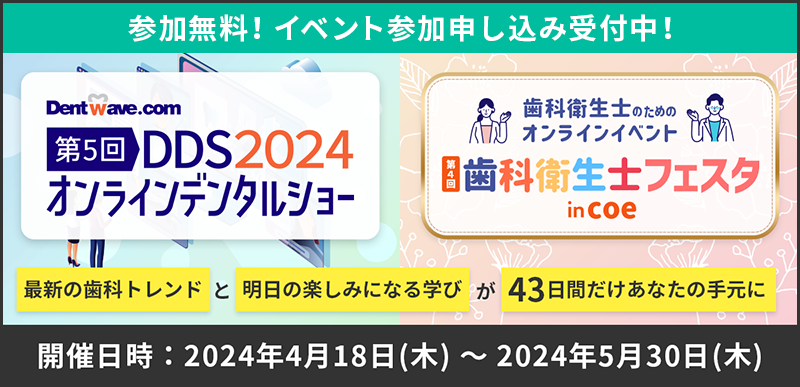骨細胞と足場材による大型顎骨欠損の再生に成功 〜新しい骨再生医療技術の開発〜
この記事は
無料会員限定です。
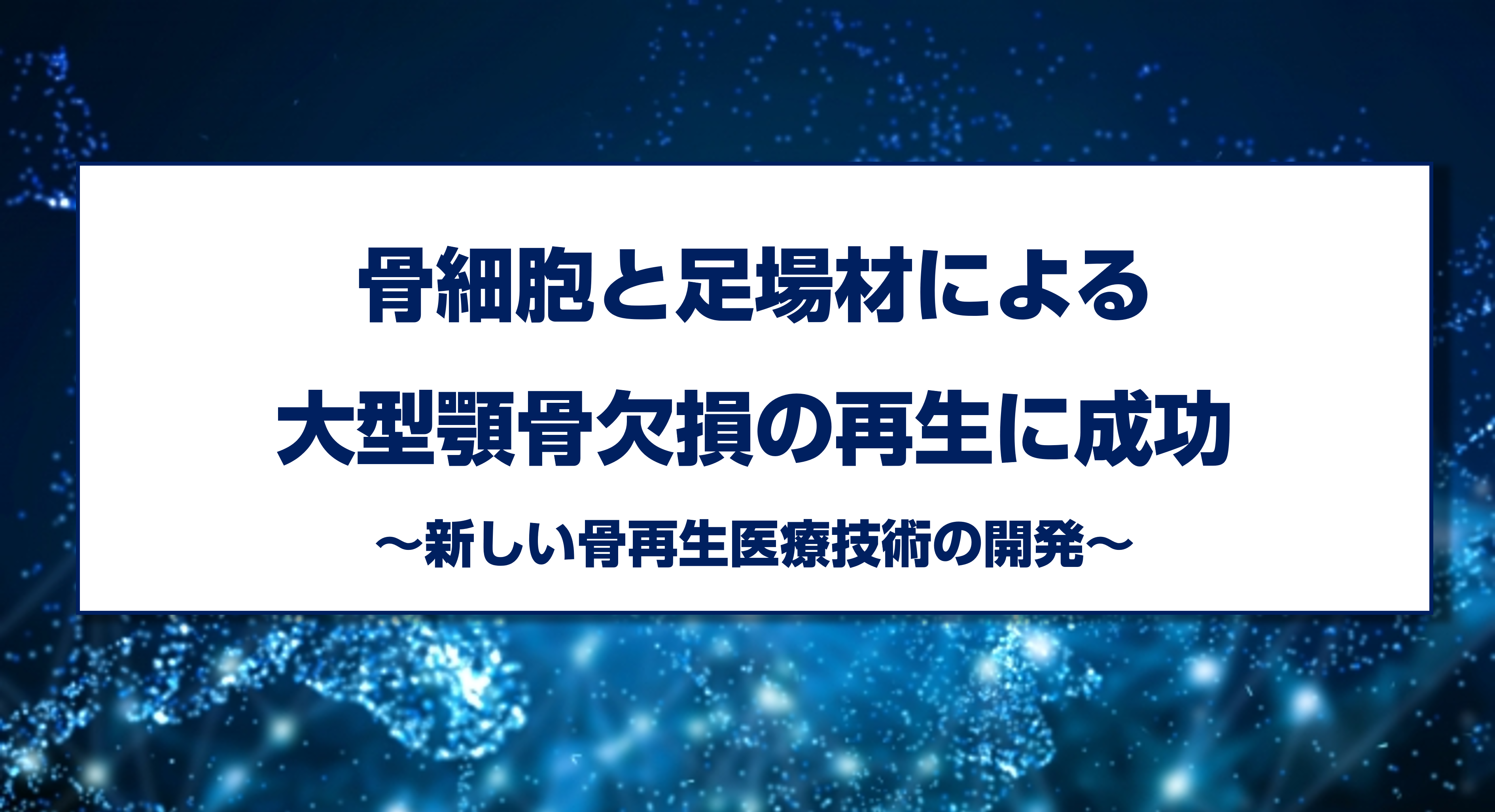
東北大学大学院・神奈川歯科大学の両大学の歯学研究所は、マウス骨細胞(MCOB)と足場材(3DPLA)を組み合わせ、大型のマウス顎骨欠損の再生に成功したと発表しました。
現在、歯科医院で実際に臨床で行われている骨の再生医療というと、骨補填材「リグロス®」や「エムドケインゲル®」等を使用した「歯周組織再生療法」については聞き馴染みがあるかと思います。それらは主に骨の再生を促進するもので、大きな骨欠損の治療法には適応外でした。これまで、失われた骨を再生させる様々な治療技術が開発されてきましたが、大きな骨欠損を伴う病気の治療法としては、実現されていませんでした。
しかし、この研究成果によって、骨再生医療においてこれまで不可能であった、顎骨を含む様々な骨欠損を伴う病気に対する再生医療への発展が期待できます。再生した骨は通常の骨と同じ位の強度を持ち、インプラント治療を行える可能性があることも示されています。
・東北大学病院歯内療法科の鈴木重人医員、東北大学大学院歯学研究科歯科保存学分野のVenkata Suresh助教、齋藤正寛教授、分子・再生歯科補綴学分野の江草宏教授、オステレナト社の北川全氏、産業技術総合研究所の稲垣雅彦主任研究員、神奈川歯科大学の半田慶介教授らのグループは、骨細胞と足場材を組み合わせることでマウスの大型顎骨欠損の再生に成功。
・この方法によって再生した骨は、通常の骨と同等の強度を示し、歯科用インプラント治療にも応用できる可能性が示された。
・この研究の成果は、骨再生を必要とする様々な病気の再生医療への応用が期待されている。
歯科において大きな顎骨欠損は、歯周病や外傷、腫瘍などの原因によって引き起こされますが、現在有効的な治療法がない状態です。
現在まで、様々な細胞に成長可能な幹細胞(病気によって失われた体の一部を補充する能力がある細胞)を様々な足場と組み合わせて使用し、再生医療技術が研究開発されてきましたが、臨床応用はされていないのが現状でした。
実際の臨床では、骨補填材による小〜中程度の骨欠損の治療法には、有効性があると言われていますが、大きな骨欠損の場合、骨補填材では十分な治癒は望めませんでした。
東北大学病院歯内療法科の鈴木重人医員、東北大学大学院歯学研究科歯科保存学分野のVenkata Suresh助教、齋藤正寛教授、分子・再生歯科補綴学分野の江草宏教授、オステレナト社の北川全氏、産業技術総合研究所の稲垣雅彦主任研究員、神奈川歯科大学の半田慶介教授らのグループは、大規模な骨欠損を効果的に解決できる再生医療技術を共同開発してきました。
そして本研究の結果、2つの重要な成果を得ることができました。
①骨細胞と足場材をマウス顎骨欠損部に移植した結果、骨が優位に造成され、マウスの大型顎骨欠損の再生に成功。
②骨細胞と足場材により形成された再生骨は、本来の骨に近い強度を持ち、歯科用インプラントを埋め込むと、歯科用インプラントの主な材料のチタンと骨が直接的に一体となった状態で再生骨と結合していることが明らかになった。このことから、骨細胞と足場材を組み合わせることで、大型顎骨欠損を再生でき、失われた咀嚼機能を回復するために、歯科用インプラント治療が可能であることが示唆された。
骨細胞―足場材は大型顎骨欠損の再生のみだけでなく、今後骨再生を必要とする様々な病気の治療にも応用可能な、「新規再生医療技術」として発展していく可能性が期待されます。
①マウスの顎骨に骨欠損部位を作成。大きな骨欠損が見られる。
②骨欠損部位に骨細胞と足場材を組み合わせて移植。
③骨再生の誘導。骨の欠損部分の治癒。
④歯科用インプラントの埋め込み後、再生骨とインプラントの結合の確認。機能の改善。
この研究成果は、2022年8月8日米国科学誌PNAS Nexusにオンライン速報版が掲載されました。
出典:東北大学HP「骨細胞と足場材による大型顎骨欠損の再生に成功 〜新しい骨再生医療技術の開発〜」
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2022/08/press20220825-02-mcob.html

松本歯科大学衛生学院卒業後、一般歯科医院にて勤務。歯科衛生士としてキャリアを重ねる一方で、働き方の多様性を模索していた時にライターという仕事に出会う。
現在は、歯科医院に勤務しながら、ライター活動を行う。
「歯科の専門家の書く分かりやすい記事」をモットーに歯科医院のHP記事やブログ執筆活動を中心に執筆を行なっている。
記事提供
© Dentwave.com







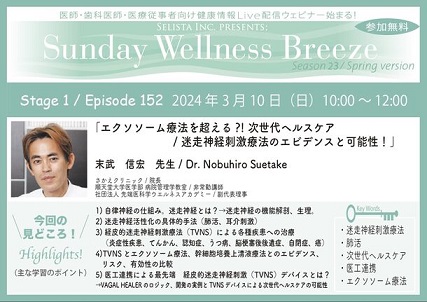



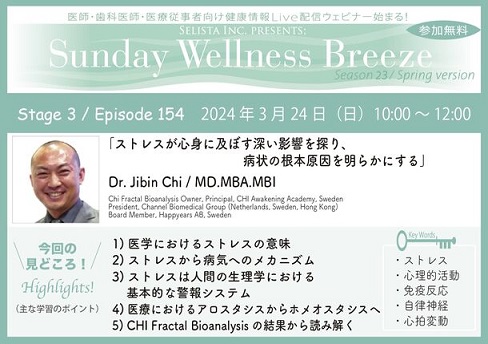
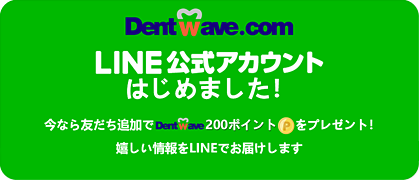 LINE公式アカウントはじめました!
LINE公式アカウントはじめました!
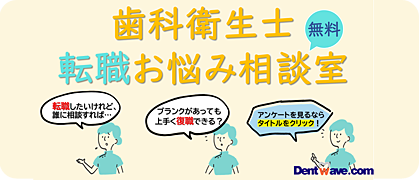 歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
 歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
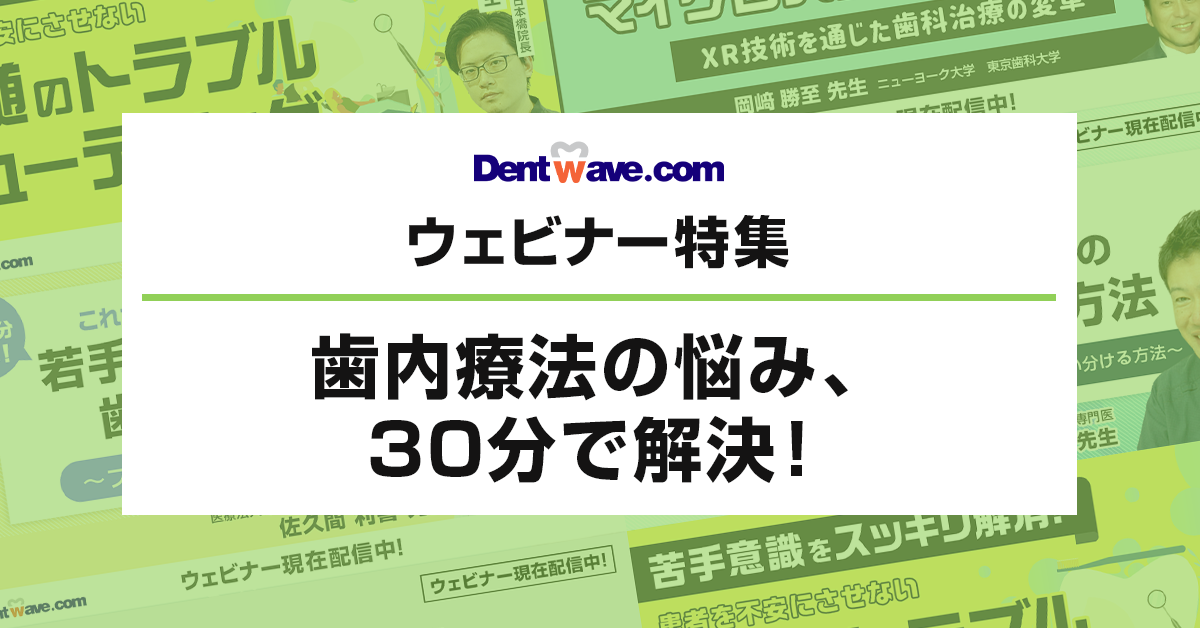 歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
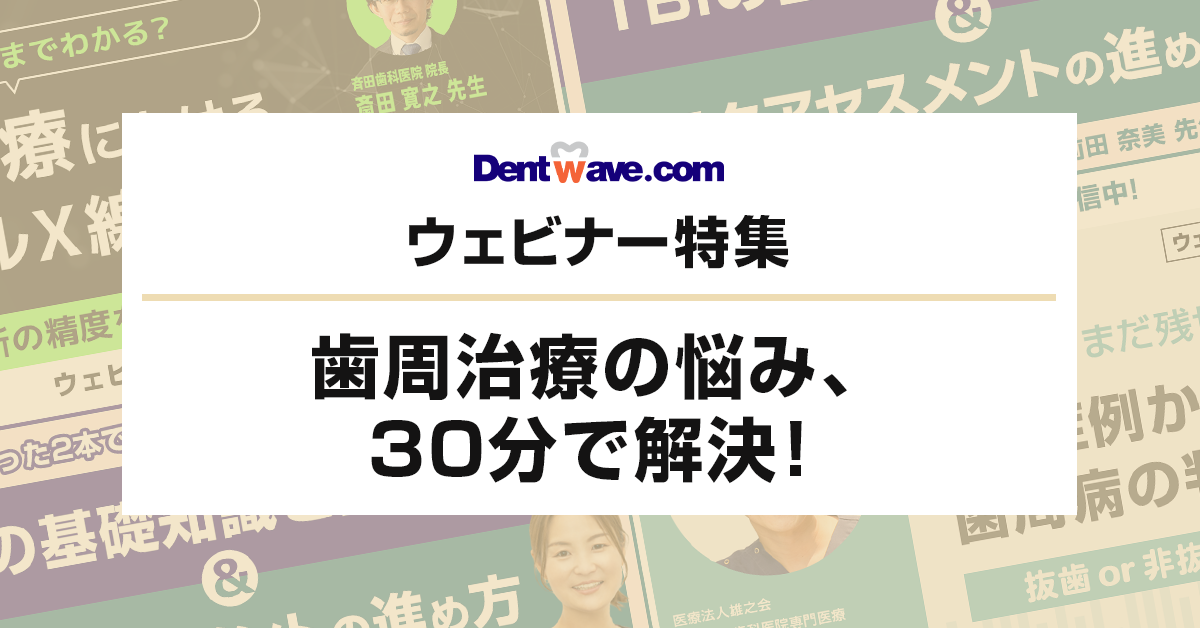 歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。