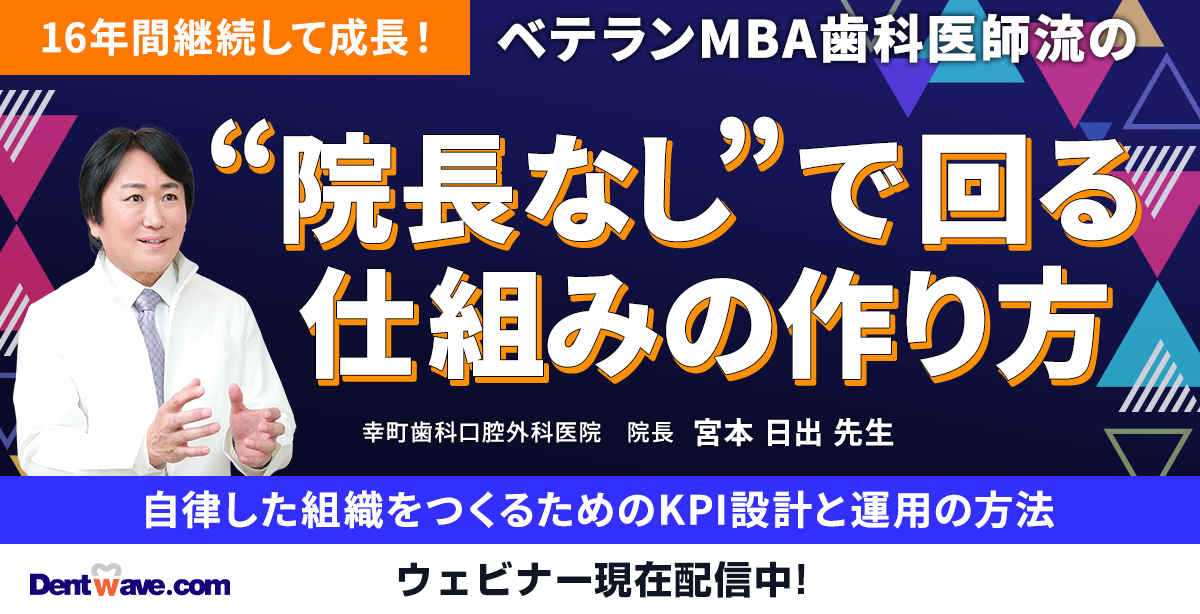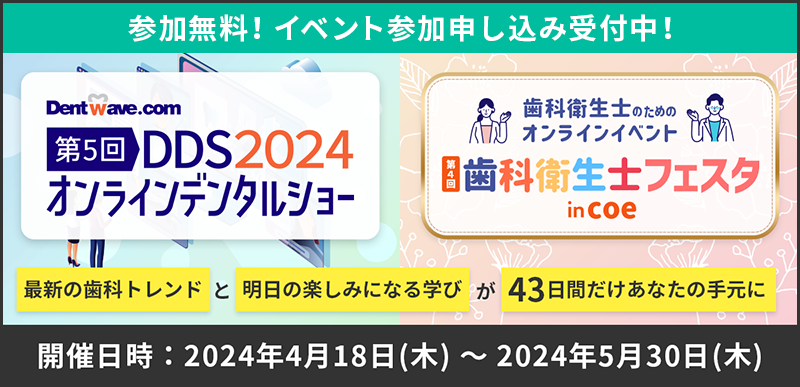第9回 事業承継や家族の絆も脅かす相続問題
カテゴリー
記事提供
© Dentwave.com
こんにちは、税理士の三沢です。
今回は【養子と相続税の関係】についてお話しします。
相続税の節税対策の一つとして、「養子縁組をする」と聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
具体的に何故節税となるのでしょう?実子の他に、1人と養子縁組する場合についてご説明します。
【節税メリット】
① 相続税の基礎控除が1,000万円(平成27年以降は600万円)増加する。
② 生命保険金等の非課税枠が500万円増加する。
③ 孫と養子縁組をする場合には、一代飛ばして財産を移転させる事ができる。
④ 相続税の税率が下がる可能性がある。
しかしメリットだけではありません。養子縁組をする際の注意点を以下にまとめます。
【養子の注意点】
① 養子の数の制限がある
「相続税の基礎控除」や「生命保険金等の非課税枠」は、以下の算式にある通り、法定相続人の数に比例し増加します。
「相続税の基礎控除」‥5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(平成27年以降は3,000万円+600万円×法定相続人の数)
「生命保険金等の非課税枠」‥500万円×法定相続人の数
相続人の数が多ければ多いほど非課税枠が増え、税金を抑える事ができます。
しかし、無制限に養子を認めてしまうと、養子を利用した節税が横行してしまうことになります。そこで、相続税を計算する上で養子の数に一定の制限がかけられています。
<養子の数の制限>
・被相続人に実子がいる場合 ‥養子の数は1人まで
・被相続人に実子がいない場合‥養子の数は2人まで
② 孫養子は相続税が2割増し
上記の【節税メリット】で、孫養子は「一代飛ばしの財産移転が可能」と述べましたが、この孫養子にも、一定の節税防止措置があります。それが、「相続税の2割加算制度」です。
孫養子が代襲相続人(被相続人より先に相続人が亡くなった場合の、相続人の権利義務を代襲相続する者のこと。簡単に言うと、親が亡くなってしまった孫のこと。)でない場合には、孫の相続税は2割加算されてしまいます。
③ 遺産分割の際に揉めてしまう事がある
民法上最低限保証されている相続人の権利として「遺留分」があります。養子も相続人ですので、当然遺留分が発生します。相続人が多ければ、個々の遺留分割合は減少します。
そのため、実子が2人以上いる場合等、相続人が複数いる様な場合においては、養子縁組をする際は他の相続人の了解を得た上で行わないと、遺産分割がまとまらなくなってしまう事もあります。
④ 氏が変わる可能性がある。
養子に入ると原則として養親の氏を名乗ることになります。
つまり苗字が変わってしまうのです。(一定の場合は変わりません)
では次に、具体的な金額を見ていきましょう。相続人は実子が2人、遺産総額が1億2,000万円(うち、生命保険金1,500万円)の被相続人のケースで、孫1人と養子縁組した場合。(税額は平成27年以降の金額を採用)
<養子縁組なし:相続人2人>
相続税の基礎控除額:4,200万円
生命保険金等の非課税金額:1,000万円
相続税額:960万円(税率15%)
<養子縁組あり:相続人3人>
相続税の基礎控除額:4,800万円
生命保険金等の非課税金額:1,500万円
相続税額:752万円(税率10%)
(2割加算額:47万円。其々1/3ずつ財産を取得した場合。)
このケースですと養子縁組により、208万円の節税となりました。
しかし、節税目的の養子縁組は税務上認められない場合もあります。さらに養子縁組は、相続税以外の様々な問題点も含んでいる点に注意が必要です。養子縁組の活用は、メリット・デメリットをしっかりと理解した上で行う必要があります。
ご興味がお持ちの方はぜひ一度ご相談下さい。
記事提供
© Dentwave.com



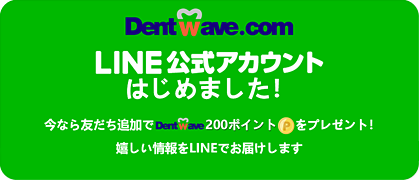 LINE公式アカウントはじめました!
LINE公式アカウントはじめました!
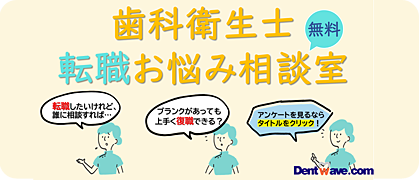 歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
 歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
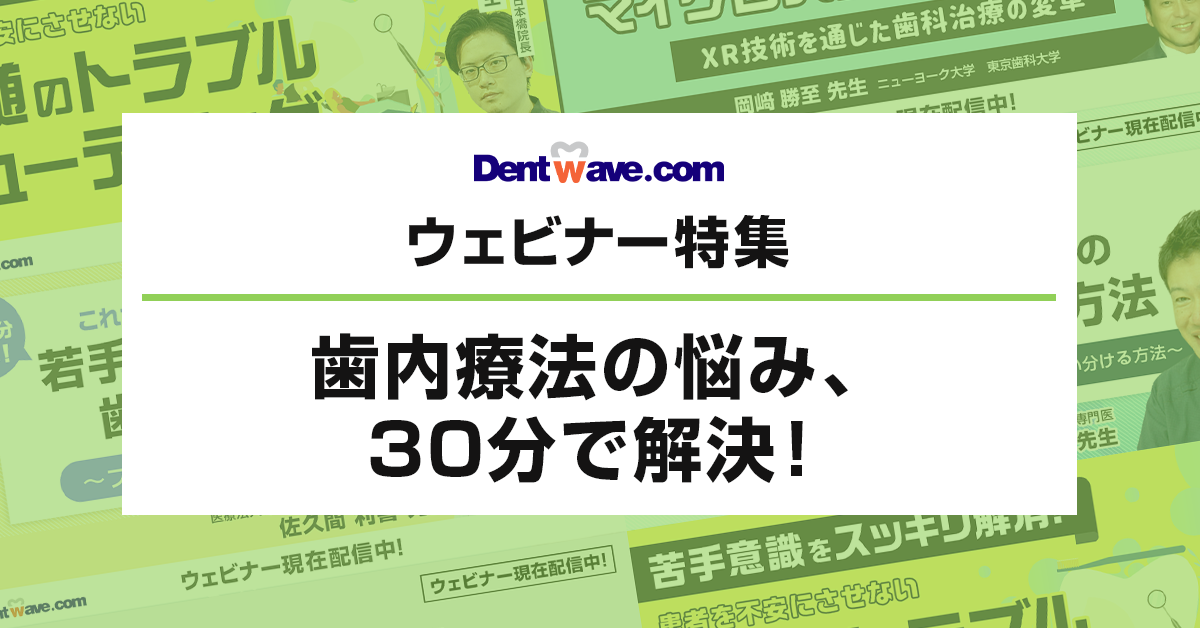 歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
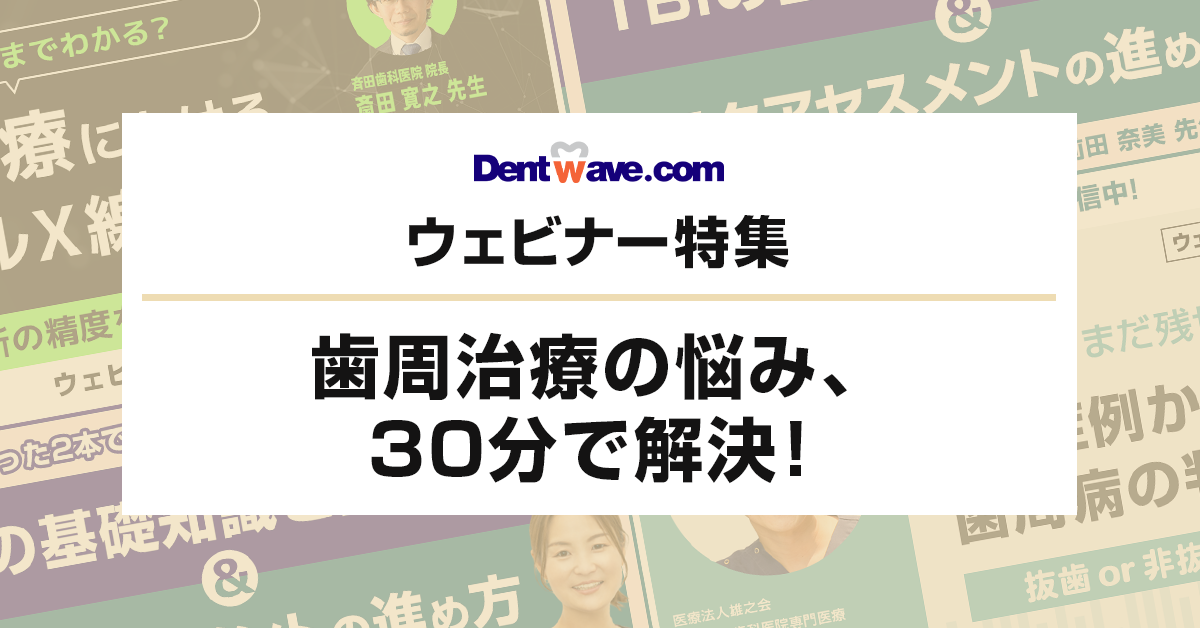 歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。