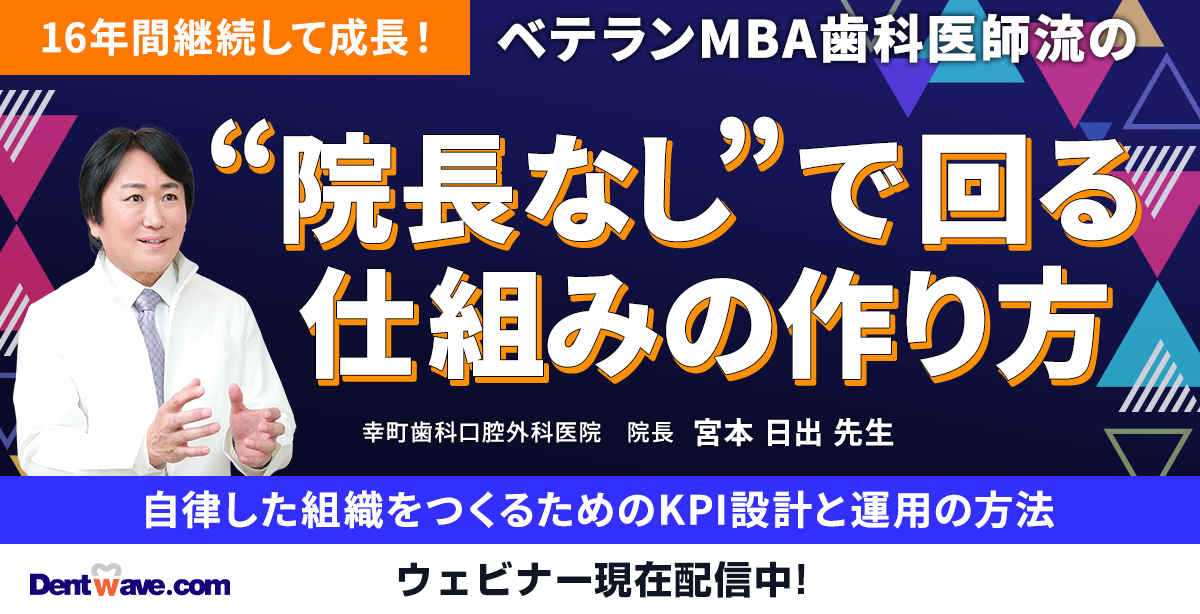第100回:歯科における接着―その源流
カテゴリー
記事提供
© Dentwave.com
最近歯科接着の初期の歴史を調べる機会があった。その過程でこれまで全く知らなかったことを見つけ、我が無知を恥じた。歯質接着の本家本元といえば1955年のJ Dent Resにエナメル質のリン酸エッチングを発表したBuonocoreであると何となく思っていた。しかし、それ以前に象牙質接着材を開発したHaggerがおり、彼こそ歯科接着のパイオニアというべき人であった。
Haggerのことがあまり知られていなかったのは、多分、歯科関係の学術文献にはその名前は見当たらず、1949年出願の特許文献のみであったためであろうと思われる。彼の名が学術誌に登場したのは、筆者が調べた範囲内では、1999年のMcLeanによるJ Adhes Dent 1巻3号冒頭掲載の「エナメル質と象牙質接着のパイオニア」と題する3頁の招待論説(Guest Editorial)である。それ以前の歯科接着に関する総説では取り上げられておらず、その後、同誌の2007年9巻増刊号2に掲載のSöderholmによる総説「歯科接着材―いかに始まりその後進化したか」には"近代歯科接着材の父"などと紹介されている。McLeanの論説がなければ、Haggerの業績は埋もれたままになったかもしれないと思うが、McLean(2009年84歳で逝去)にはぜひ書いておきたいという思いがあったのではないかという気もしている。McLeanもHaggerの開発した接着材を用いた研究結果を1952年に発表しており、両者は同時代に活躍していたのである。
HaggerはロンドンとチューリッヒにあるAmalgamated Dental Co.にスイスの化学者として勤務し、1949年7月に「表面の接着法」なる特許をスイスで出願、1951年11月登録、1952年2月公表された。特許には、グリセロリン酸ジメタクリレート(GPDM)の合成法、アクリル樹脂とポーセレン、象牙、金、スチール、アルミニウム、ガラスを接着し、1日および1か月水中浸漬後のせん断接着強さが記載されている。歯質に対する接着のデータおよび文言は明細書に見当たらない。この特許はその後1950年の6~7月に仏、英、独、オランダ、デンマークで出願され、1953年1月~1954年12月の間に各国で公表されたが、それらの明細書では象牙質接着に関する一文が付加されていた。象牙質接着の文言が初めて公表されたのは1953年1月のフランス特許であり、この日が文献的には象牙質接着の始まりとみなすことができよう。
以上のような特許出願以前に、重要な特許や論文がHaggerらから出されていた。それは、接着材と同時に使うSevritonレジンの最も重要な成分、重合開始剤のp-トルエンスルフィン酸についてである。それに関し1947年にスイスで特許出願、1948年にHelv Chim Actaに論文を発表している。当時のアクリルレジンでは常温重合開始剤として過酸化ベンゾイル(BPO)/アミンが使われ、重合に伴う変色が問題視されており、無変色性のものが求められていた。スルフィン酸は無色・無変色性であるばかりでなく、象牙質の接着でも画期的な性質を示すものであることがその後明らかにされた。
Haggerの開発した接着システムはAmalgamated Dental Co.からSevriton Cavity Sealとして上市された。その詳細は特許には記載されていないが、Buonocore の1956年のJ Dent Resの論文によれば、GPDM、メタクリル酸、MMAから成り、p-トルエンスルフィン酸を重合開始剤とする化学重合型のMMA/PMMA系レジン(Sevriton)とともに歯科修復で使われた。
この接着システムに関し、KramerとMcLeanが1952年のBrit Dent Jに2報の論文を発表している。1報目では、人歯の窩洞に接着材/レジンを充填し、抜歯後組織学的に検討したところ、象牙質上層部に約3 μmの染色変化層(altered staining zone of dentin)を認めた。2報目の15頁の長い論文では、まず、抜去歯に窩洞を形成しての色素浸透試験では、エナメル-レジン境までは色素が浸透したが、象牙質には浸透しないことを認めている。それに引き続き36名の被験者の歯の窩洞に充填し、最長10か月の歯髄反応を調べたところ、歯髄からの距離が1.4 mm以下では歯髄反応が強く、深い窩洞では裏層の必要性を示唆している。ここでKramerらが認めた象牙質の染色変化層は、研磨象牙質表面で接着材を硬化させると3~10μm幅の同様な層が形成されることを1958年にBuonocoreらも報告している(J Am Dent Assoc)。この層は、現在の言葉でいえば、樹脂含浸象牙質であるといってよいであろう。
接着性については、1956年BuonocoreらのJ Dent Resの論文がある。入手できるいろいろなアクリルレジンについて湿潤した象牙質への接着性を定性的に調べたところ、Sevritonのみが接着性を示すことを認めた。そこで、Sevriton Cavity Sealと成分的に同じ接着材を試作、それに使用時にスルフィン酸を添加し、研磨象牙質面での接着試験を行い、接着強さは1時間後28 kg/㎠、水中浸漬2週~3月後で約1/2に低下と報告している。
Haggerの開発した接着システムに関する報告は以上のようなものであったが、Kramerらの臨床試験からも推測できようが、歯髄反応が好ましいものではなく、臨床的に成功とは言えず市場から消えてしまった。臨床的に成功といえるものの出現には、MMA-TBB系レジンであるPalakavの1971年の登場までしばらくの時間を要した。この製品は、東京医科歯科大学の増原英一教授らの開発になるものであり、1963年発行の歯科材料研究所報告(歯材研報)の論文が出発点となっている。その中で、MMA-TBB/PMMAレジンが湿潤した象牙質や象牙に強く接着することを認めている。それは、接着界面観察のため未脱灰の組織学的薄切標本を作製したが、その過程でキシレンに浸漬してもレジンが象牙質表面に強く付着している(現在でいうところの樹脂含浸層形成)ことと関連しているとした(1964年歯材研報)。この結果をもとに、ドイツのデュッセルドルフ大学のFisher教授およびKulzer社の協力を得て歯科接着材の開発が進められた。TBBをワセリンでペースト化したものをバルビツル酸系重合開始剤と併用したMMA-PMMA/ガラス粉末からなるレジンが試作された(F1レジン)。このF1レジン(Palakavと同等品)を裏層なしに各種窩洞に充填する臨床試験を3年間にわたり行ったところ、治療後12か月までの歯髄失活は434症例中わずか9症例であった(1968年のDeutsche Zahnärztliche Zeitschriftで報告)。こうした臨床での好成績をもとに、1971年接着性充填材Palakav(パラカーフ)が誕生した。しかし、充填材としては耐摩耗性などの問題のあるPalakavは、その頃登場したBis-GMA系コンポジットレジンに押され、1974年市場から姿を消した。
MMA-TBBレジンのその後であるが、エナメル質向けの歯科矯正用接着材「オルソマイト」を1971年に持田製薬が上市、1983年に多目的接着システム「スーパーボンドC&B」がサンメディカルから上市され、30年以上基本的に当時とほとんど変わらずに、象牙質接着性のすぐれたレジンとして広く利用されている。このへんの我が国での接着の初期の歴史は、長くなるのでここでは省略するが、第44回「増原英一先生のご逝去を悼んで」および付録につけた日本歯科理工学会誌29巻6号(2010)DEのヒストリア欄の「歯科における接着の始まり」を参照されると好都合である。
ところが、その後、接着の歴史が歪められかねないことがDEのヒストリアに掲載されてしまった。それは、2012年の理工学会誌31巻3号に中林宣男教授が「樹脂含浸象牙質」と題して書かれ、その中に「湿潤象牙棒には接着できるが、象牙質には接着できないことを日常的に観察していた」という記述がある。増原英一研究室在籍17年の人の記述とは信じ難いのであるが、これは全くの誤りである。歯科接着の歴史を歪めないためにも事実を検証しておきたい。1963年発行の歯科材料研究所報告に増原・小嶋・樽見らによる「歯科用即硬性レジンの研究(第3報)アルキルボロン触媒を用いたときの象牙および歯質への接着性」と題する論文がある。それにはMMA-TBBレジンの湿潤したヒト抜去歯象牙質に対する接着性は象牙への接着性と同等であると記されている。象牙の利用は、多数の抜去歯を揃えることが困難である一方、当時は象牙を容易に入手できたため便宜的に代用使用されていた。
ところで、「日常的に観察していた」のはいつ頃であったのか?これへのヒントになると思われる、中林先生の書かれた一文が2011年12月発行の東京医科歯科大学生体材料工学研究所60年史という冊子に載っている。「故・増原英一先生は象牙質のモデルとして湿潤象牙棒とPMMA棒をMMA-TBBレジンで接着できることを1968年に報告したが、象牙質には接着できなかった」。これによれば1968年でもまだ象牙質には接着できず、さらに湿潤象牙棒とPMMA棒のMMA-TBBレジンによる接着は1968年に初めて報告があったかのような印象を与えている。"1968年に報告したが"を手がかりに1968年の増原先生らの論文を探すと、医用器材研究所報告に「歯科用即硬性レジンの研究(第10報)―反応性高分子が歯質とレジンの接着性におよぼす影響について―)があった。この論文は、象牙棒と牛歯エナメル質を用いてMMA-TBBレジンによる接着を検討したものであり、象牙質での検討はない。接着強さは象牙棒で大きく、エナメル質では非常に低くなっている。このことは、"象牙棒には接着できても象牙質にはできなかった"ことは示しておらず、接着できなかったのは象牙質ではなくエナメル質であったことを示している。
Haggerの開発したスルフィン酸やGPDMは、現在に至るまでいろいろな製品に利用され、遺産として引き継がれている。スルフィン酸そのものは安定性を欠き、油剤と混ぜてチューブに入れた包装であったSevriton の場合の有効期限は約6か月であったらしいが、この物質はその後30年ほどの時を経て、安定なナトリウム塩と酸性モノマーの組合せで活用されることになった。例えば、クラレの化学重合型レジンであるクリアフィルFIIやクリアフィルSC、サンメディカルのAQボンド、メタシールあるいはハイブリッドシール(海外製品)であり、さらに、GPDMはKerrのオプチボンドなどである。
1950~1960年代において、Haggerは化学者としてスルフィン酸、リン酸系モノマーの提供だけでなく、現在での樹脂含浸層の概念やセルフエッチングプライマーを示唆することにも寄与したように思われる。一方、増原教授は臨床的に満足し得る象牙質接着材を世界に先駆けて開発し、いわゆる樹脂含浸層の形成も認めており、Haggerと並んで象牙質接着のパイオニアというのがふさわしいと思っている。残念ながら、当時の論文が日本語、ドイツ語でしか発表されていなかった影響もあろうが、増原教授の業績は世界の接着の歴史の中では全く無視され、海外雑誌の歯質接着の総説でも取り上げられたことはない。
最後にぜひ付け加えておきたいことがある。TBBや4-METAにつながるメタクリロイルオキシエチルフタル酸の合成など、小嶋邦晴助教授(当時)の化学者としての貢献がなければ、MMA-TBB系レジンは生まれることはなかった。
(2014年6月6日)
付録:日本歯科理工学会誌(2010)ヒストリア:「歯科における接着の始まり」(PDF:209KB)
記事提供
© Dentwave.com



 LINE公式アカウントはじめました!
LINE公式アカウントはじめました!
 歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
 歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
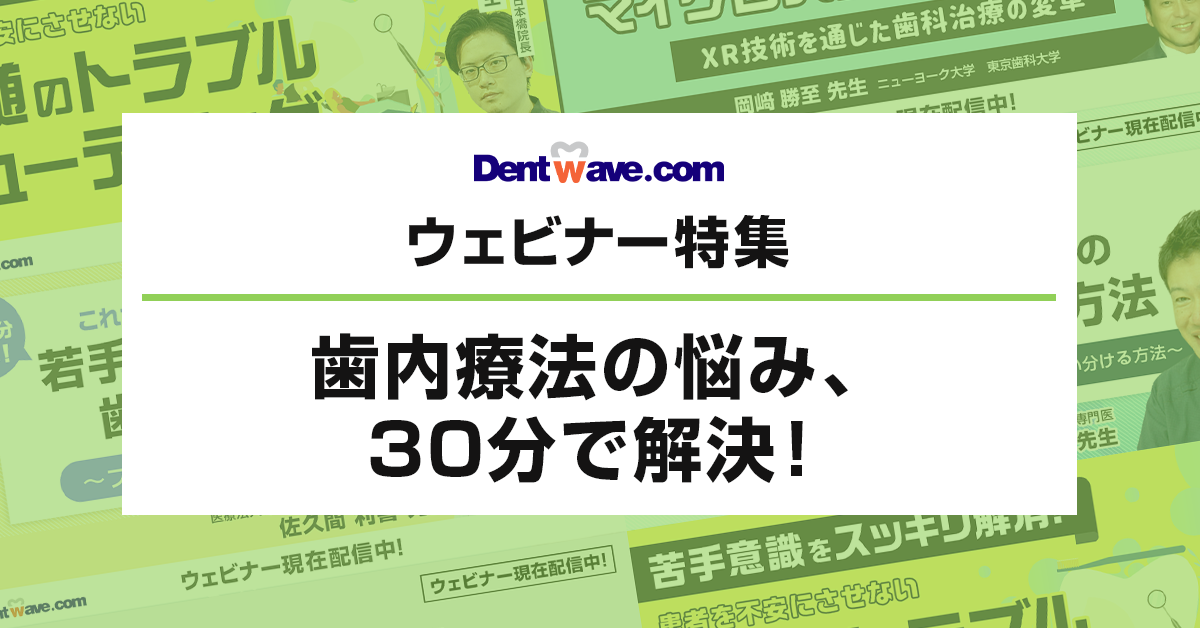 歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
 歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。