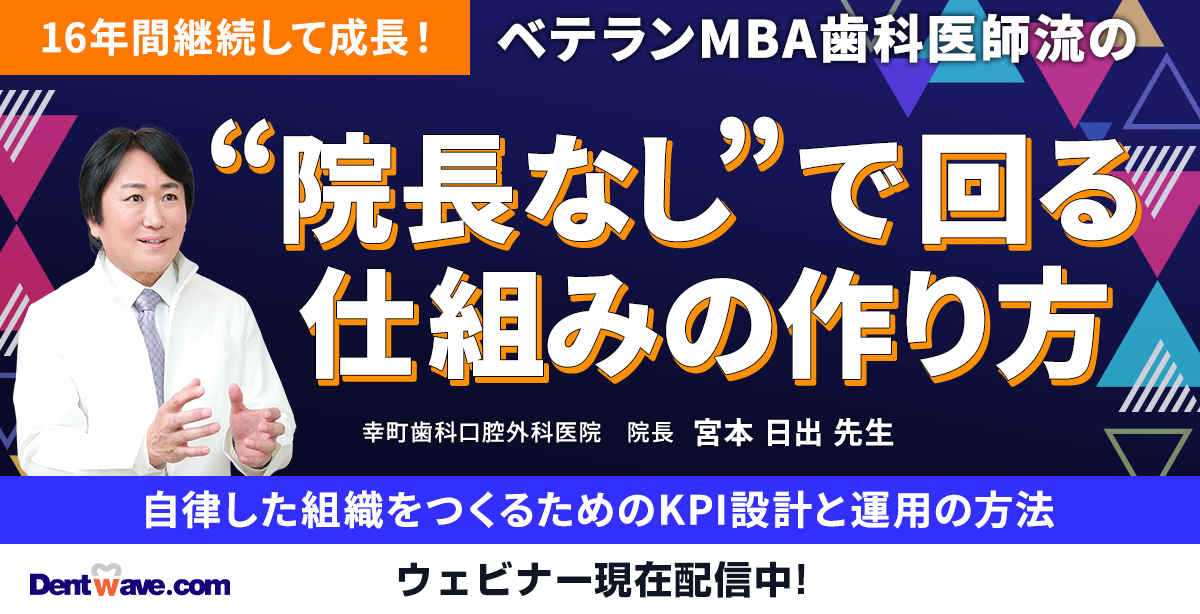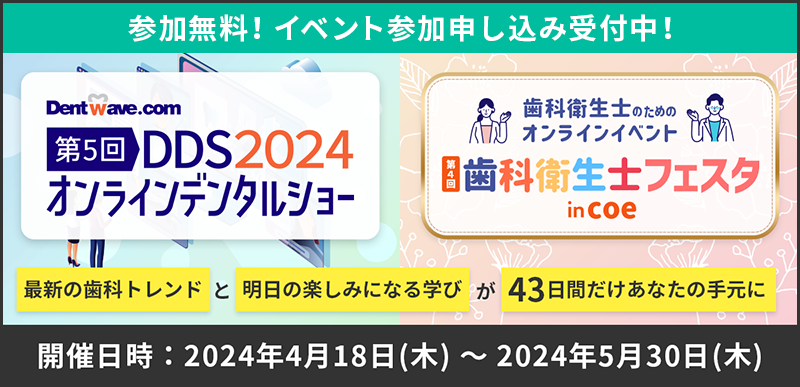歯科医師会離れが起きている。
歯科医師会に魅力がないからか?あるいは、不況続きで、経済的な余裕がなく歯科医師会に入会できないのであろうか。では、非入会者にとっては、まったく無縁な歯科医師会の活動は、どのようなものなのであろうか。
非入会者向けに、一つの例として東京都歯科医師会の活動について紹介する。歯科医師会の役割、活動、存在意義を見直す機会になればと思うのである。
http://www.tokyo-da.org/pdf/prevent.pdf
http://www.tokyo-da.org/citizun/pdf/lifestage.pdf
http://www.tokyo-da.org/citizun/pdf/leading_2008.ppt#305,12,
3 歯を失う原因と対策
1)未入会者対策関係
「入会促進対策プロジェクトチーム」を立ち上げた。
大学病院等を含む公的医療機関に勤務する歯科医師の入会で、各大学関係者と交渉を重ねた。
2)平成19年度から、東京都と連携し、医科と歯科が一堂に会して医療機関における虐待児童の早期発見を行うシステムの構築で協議。
合わせて、地区歯科医師会では、医師、歯科医師むけにドクターアドバイザーシステム研修を実施。
3)平成18年度から、東京都と連携し、東京都健康推進プラン21に掲げる「ガンの減少」とりわけ、乳がん死亡率の低下を目指す、「ピンクリボンin東京」に歯科医師会としてブースを出展。
4)平成17年度から、都民の健康づくり行動を支援する。企画・立案に参加。
5)東京都8020運動推進特別事業として、歯科保健普及啓発で「今が大切!お口は健康の源」リーフレット・ポスターを作成し、会員や都内640健康保険組合、地域産業保健推進センターを中心に配布。
6)平成18年度に、歯科保健医療情報ニーズ調査。
会員、区市町村、都立心身障害者口腔保健センター利用者を対象に、同センターにおける情報提供体制の整備に関する調査を行う。
7)在宅歯科診療等実態調査。
会員、区市町村、老人福祉施設を対象に在宅における歯科診療の実態調査を行う。
8)高齢者向け(退職時)歯科保健普及啓発。
退職前の勤労者(55歳以上)の口腔内状況や歯科保健意識の実態を調査し、「豊かなシニアライフはお口から」を作成し配布を行う。
9)平成19年度に、在宅歯科医療研修会を実施。
在宅歯科医療に関する知識の習得や在宅医療への関わり方に関する研修を行い、地域で核となる人材を養成。
10) 在宅歯科医療マニュアルを作成。
歯科医師、歯科衛生士を対象に具体的な処置方法や症状にあわせた対処法などの実践マニュアルを独自に作成。
区市町村、道府県、地区歯科医師会等に配布。
11)「おいしく食べられる」ための機能型健康評価のスクリーニング試験法の開発。
保険者における歯科保健を推進するため、保険者に受け入れやすい口腔機能を視点とした簡易型機能健診を開発し、普及を図った。
歯科衛生士が中心になって行うアンケート、混合ガム、だ液チェック等によるスクリーニング方法を標準化した。
12) 食育支援事業の実施。
子育て支援や生涯を通じた健康づくりの支援策を推進するために、歯科医師、歯科衛生士を対象に食育ガイドブックの作成や、会員、食育推進関係者等向けに食育推進シンポジウムを実施。
食育のノウハウや地域における食育の具体的な推進方策を示す。
食生活を支える口腔機能の支援を通してかかりつけ歯科医として、さらなる地域広域を目指す。
13)「8020運動」20周年記念事業の実施。
記念誌の発行や記念シンポジウムを開催を通じて、8020の更なる実現に向けて都民へ広くアピールする。
平成17年から、農林水産省東京農政事務所と連携して、国の食糧備蓄倉庫である深川政府倉庫を活用した「親子で楽しく食育体験」を実施している。
体験コーナー(混合力ガムやだ液チェック・咬合力測定器等)に2日間で延べ2000名を超える参加者がある。
14) 在宅歯科医療における
摂食・嚥下評価専門研修会の開催では、東京都、東京都医師会、東京都歯科医師会連携による内視鏡検査(VE)を中心とした医師、歯科医師対象の研修を実施。
15)生活機能評価における口腔関連としては、平成18年度から実施された介護保険制度改正に対応すべく、歯科関係者が関わる取り組みとして、地域支援事業、予防給付、さらに介護給付サービスにおきても「口腔機能向上」が導入された。
特に、地域支援事業、特定高齢者施策においては、基本チェックリストとともに、医師による基本健康診査(生活機能評価9の結果によって対象者が選定されることになっている。
そいこで、医師会向けに口腔関連の理学的検査も兼ねた口腔関連5項目のチェックリストを作成した。
16)「お口の健康は元気の近道」というテーマのチェアサイドパネルを作成。
母子領域では妊婦の口腔ケアやフッ化物の応用、成人領域ではたばこと歯周病,メタボリックシンドロームとの関係、高齢者領域では口腔機能の向上を中心にわかりやすく解説。
記事提供
© Dentwave.com






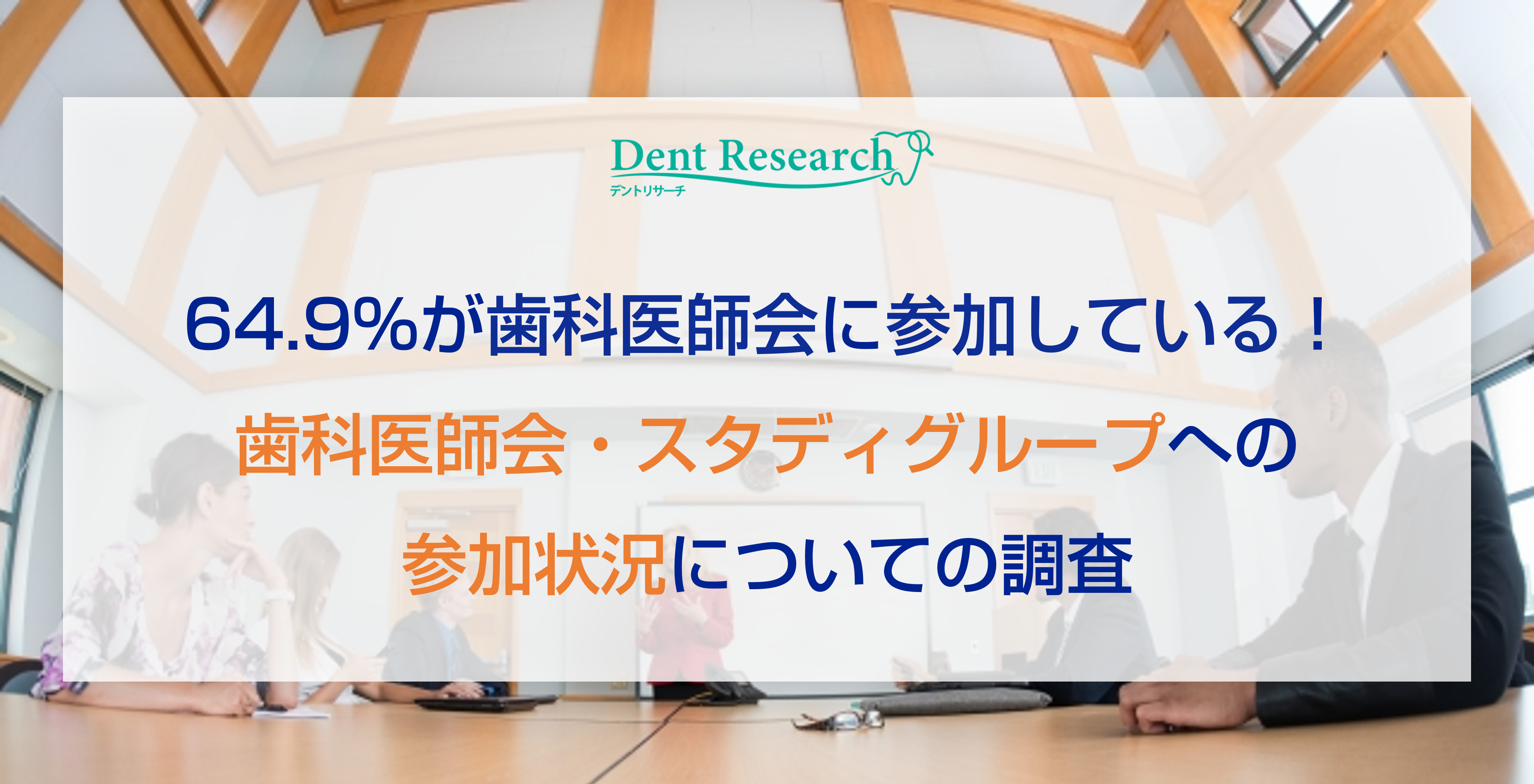




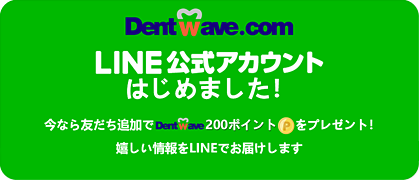 LINE公式アカウントはじめました!
LINE公式アカウントはじめました!
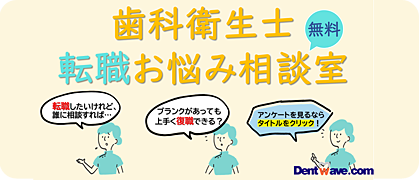 歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
 歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
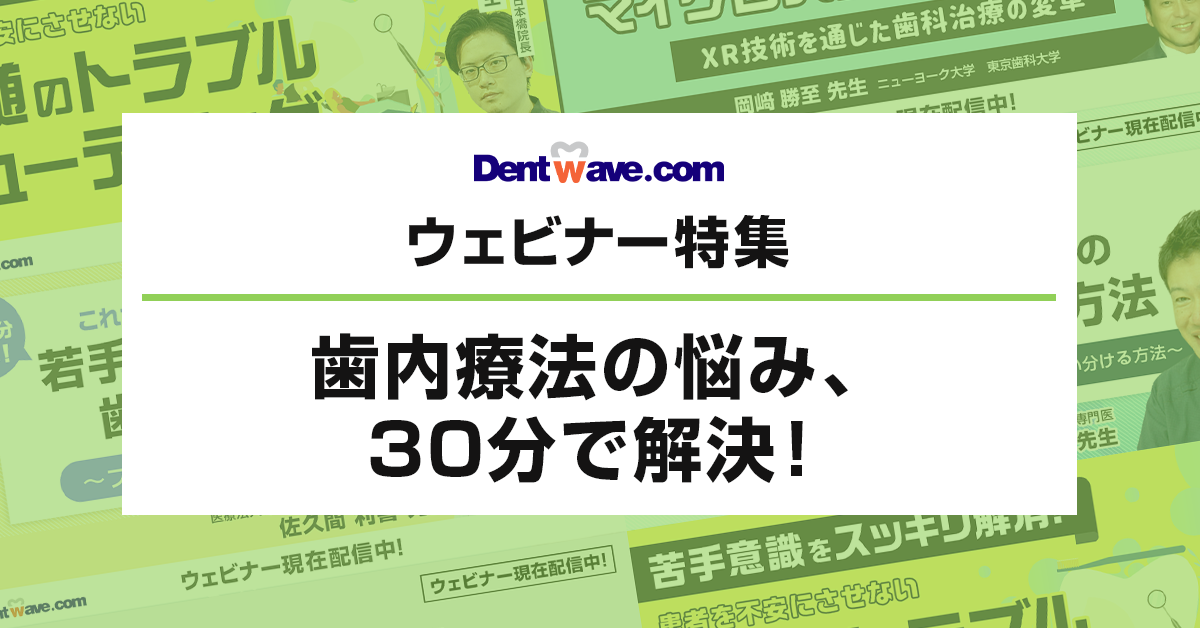 歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
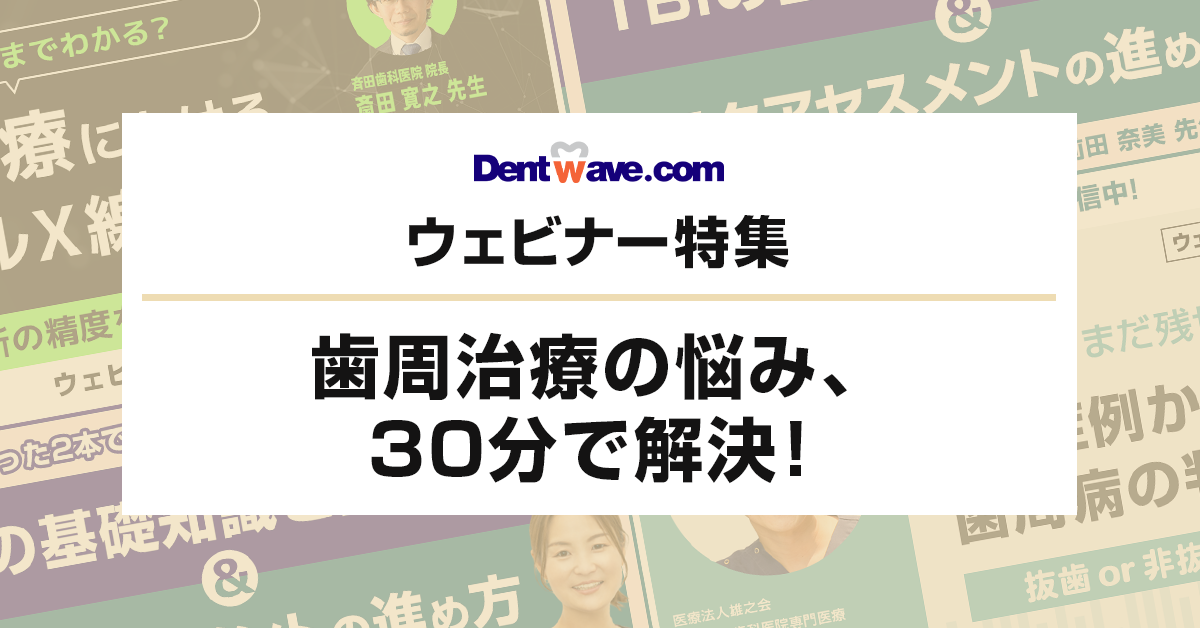 歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。