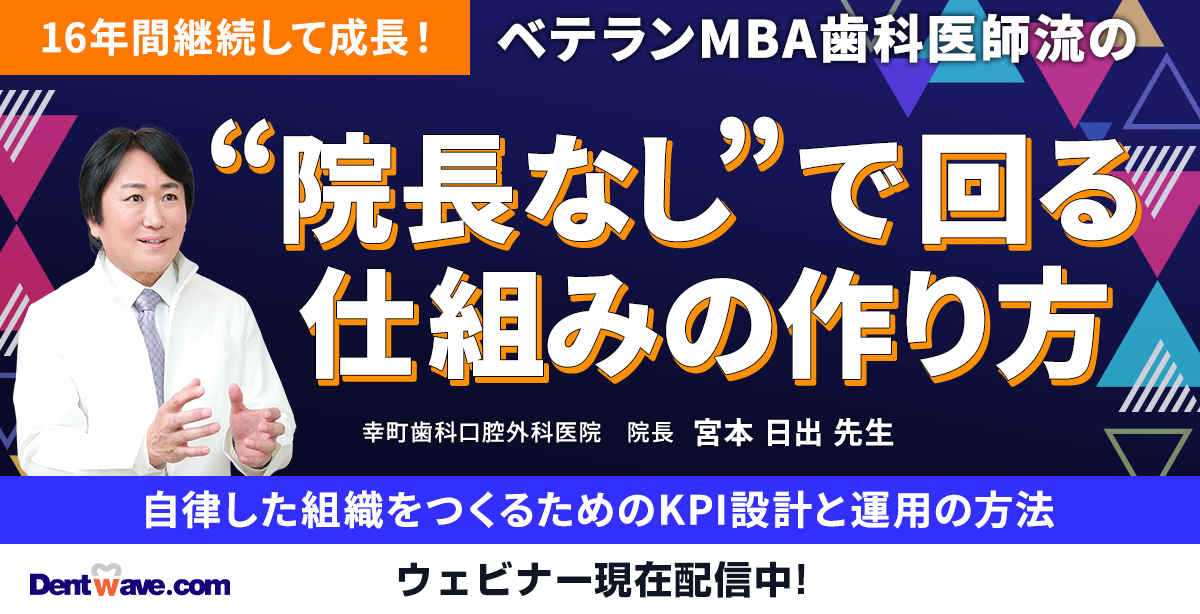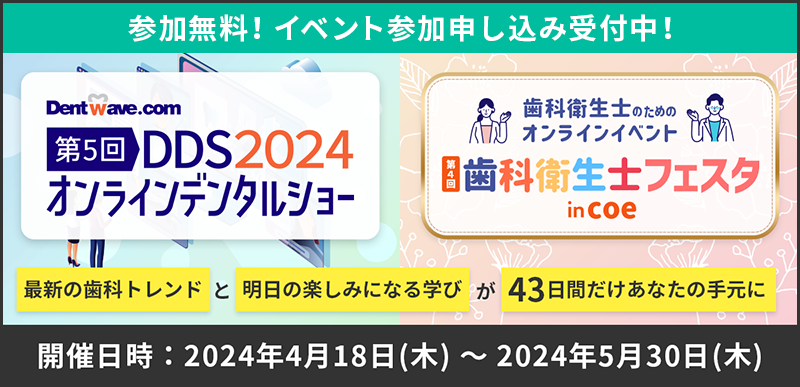レーザー治療のエビデンスの問題
カテゴリー
記事提供
© Dentwave.com
東京歯科大学創立120周年記念学術講演会から
東京歯科大学創立120周年記念学術講演会と第289回東京歯科大学学会が5月8、9の両日、東京千代田区丸の内の東京国際フォーラムで開かれた。
口腔科学研究センターシンポジウム「口腔アンチエイジングによる生体制御」、基調講演「未来の歯科医療としての歯科再生医療」特別講演「iPS細胞を用いた再生医学・疾患研究」、国際シンポジウム「40年を迎えたインプラントの光と影」、国内シンポジウム「食に関わる口腔機能」、市民公開フォーラム「本当に怖い歯周病! 歯周病が糖尿病を狙っている」、ポスター展示と討論、ランチョンセミナー、歯科企業展示などが各会場で開かれた。
ランチョンセミナー「歯科用レーザーの変遷 —レーザーは日々の臨床をどのように変えるか—」篠木毅さん(埼玉県開業)を取材した。
歯科用レーザーをもっているが使っていない歯科医師が少なくないようだ。
歯科用レーザーが、『魔法の杖』のように過大評価された時期もあった。
しかし、現在、歯科臨床への応用の範囲は絞られてきたそうだ。
日本の歯科分野でのレーザーの応用は、海外と違う、ワールドスタンダードではない、と篠木毅さんは指摘していた。
それは、レーザーとは何かが分かっていないことに起因するようだ。
日本ではこれまで、レーザーは軟組織に用いられてきた。
炭酸ガスレーザーなどを用いて、軟組織への応用が主流であった。
一方、齲蝕除去など硬組織への応用は遅れていた。
また、レーザーの性質は直進性であるために、根管などの曲がったところへの応用が難しかった。
レーザーは波長で決まる。
照射モードが変わると変わる。
そこで、レーザーの機能の違いが分かれば、有効に使用できる。
海外のレーザーとリンクされていないことも、問題点の一つ。
最先端のレーザーが日本に導入されていないことを意味しているようだ。
水に反応するレーザーやヘモグロビン、メラニンに反応するレーザー。
軟組織の表面に反応するのか、透過性があるのか、どのレーザーの波長が何に反応するのか。
つまりレーザーの使用は、レーザー治療のエビデンスの問題となる。
「パルス波なので表面にしか反応しない」などと無知なことを言う企業担当者もいるそうだ。
表面で反応するレーザーばかりではなく、深い組織まで透過するレーザーでは、パルス波であろうと深い部分の組織まで照射される。
さらに問題なのは、患者にメガネを使用していない。
子どもの患者でもメガネの使用は不可欠で、タオルで顔を覆えば安全という誤解もある。
安全性への警告である。
また、インプラント周囲組織への応用では、レーザーが反射して直進することもある。
口腔内のインレー、クラウンなどの金属でレーザーが思わぬ方向に反射する危険性もある。
以上が篠木さんの講演のポイントで、使い方如何では目の障害も起こっているそうだ。
記事提供
© Dentwave.com

- 前の記事政治家は真面目に政策を勉強しない

- 次の記事歯科診療報酬点数表関係の疑義解釈


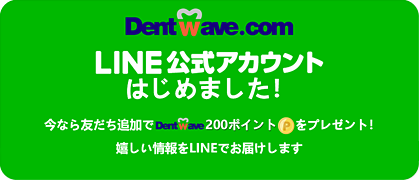 LINE公式アカウントはじめました!
LINE公式アカウントはじめました!
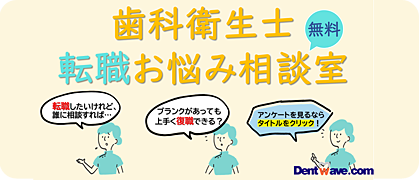 歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
 歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード
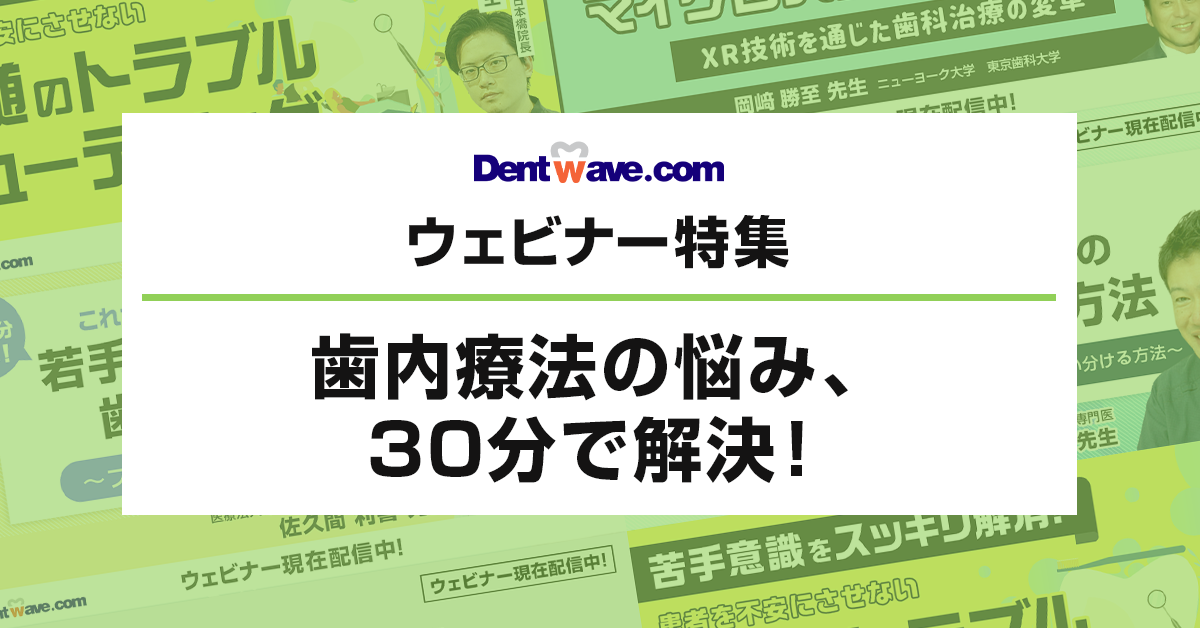 歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
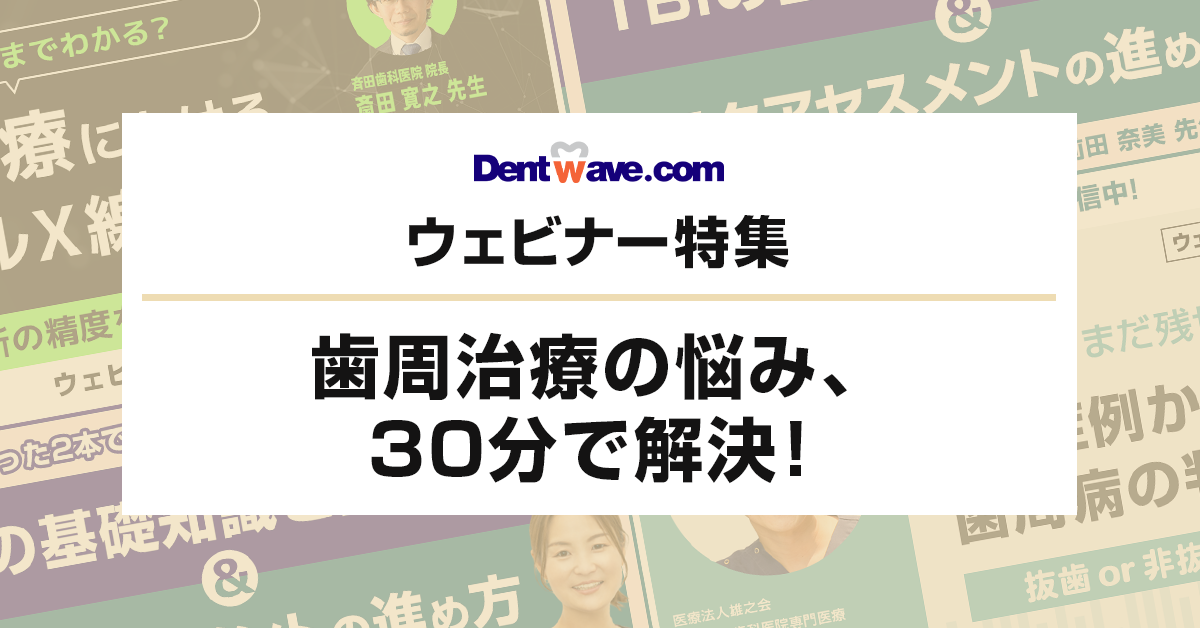 歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。