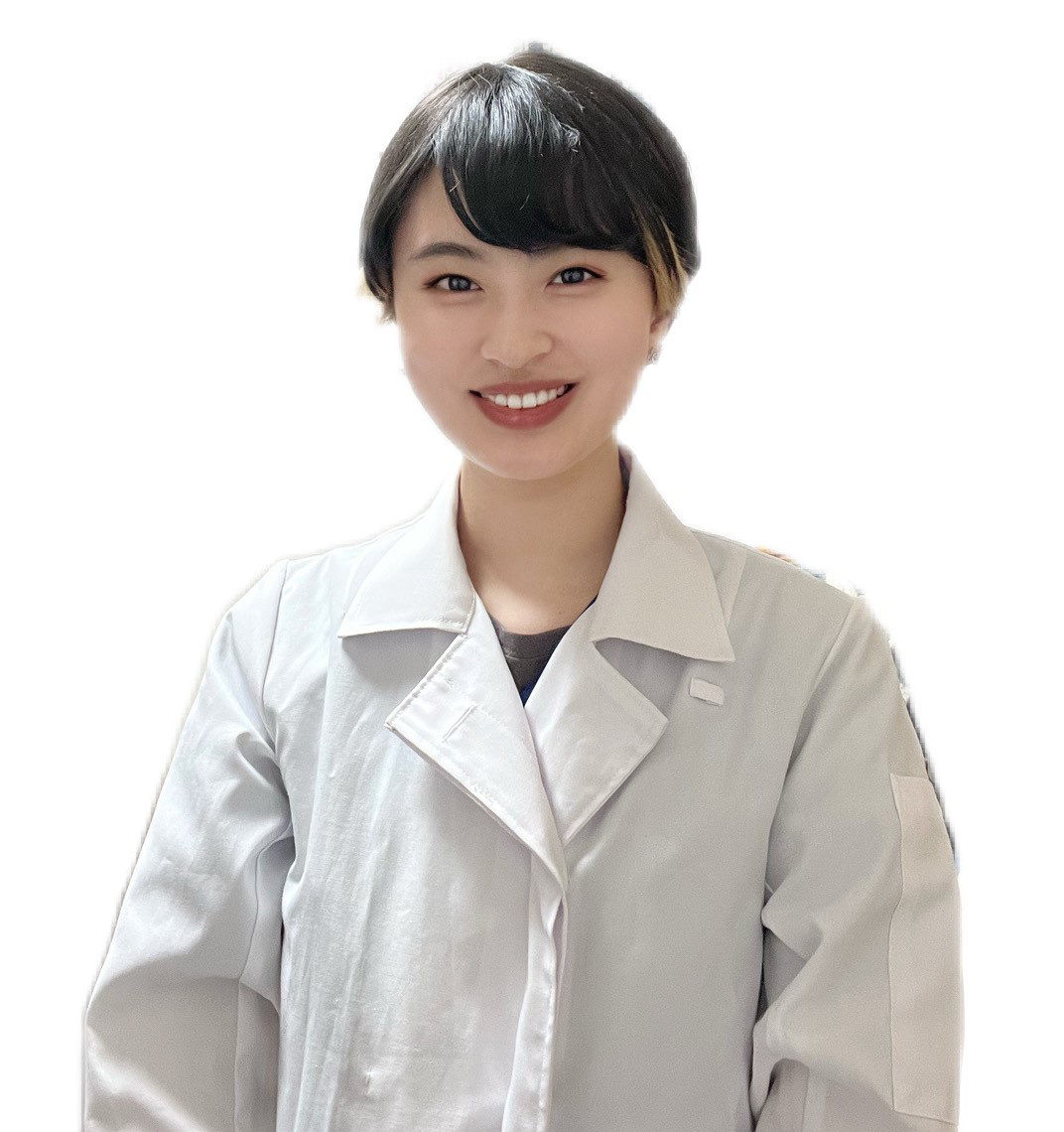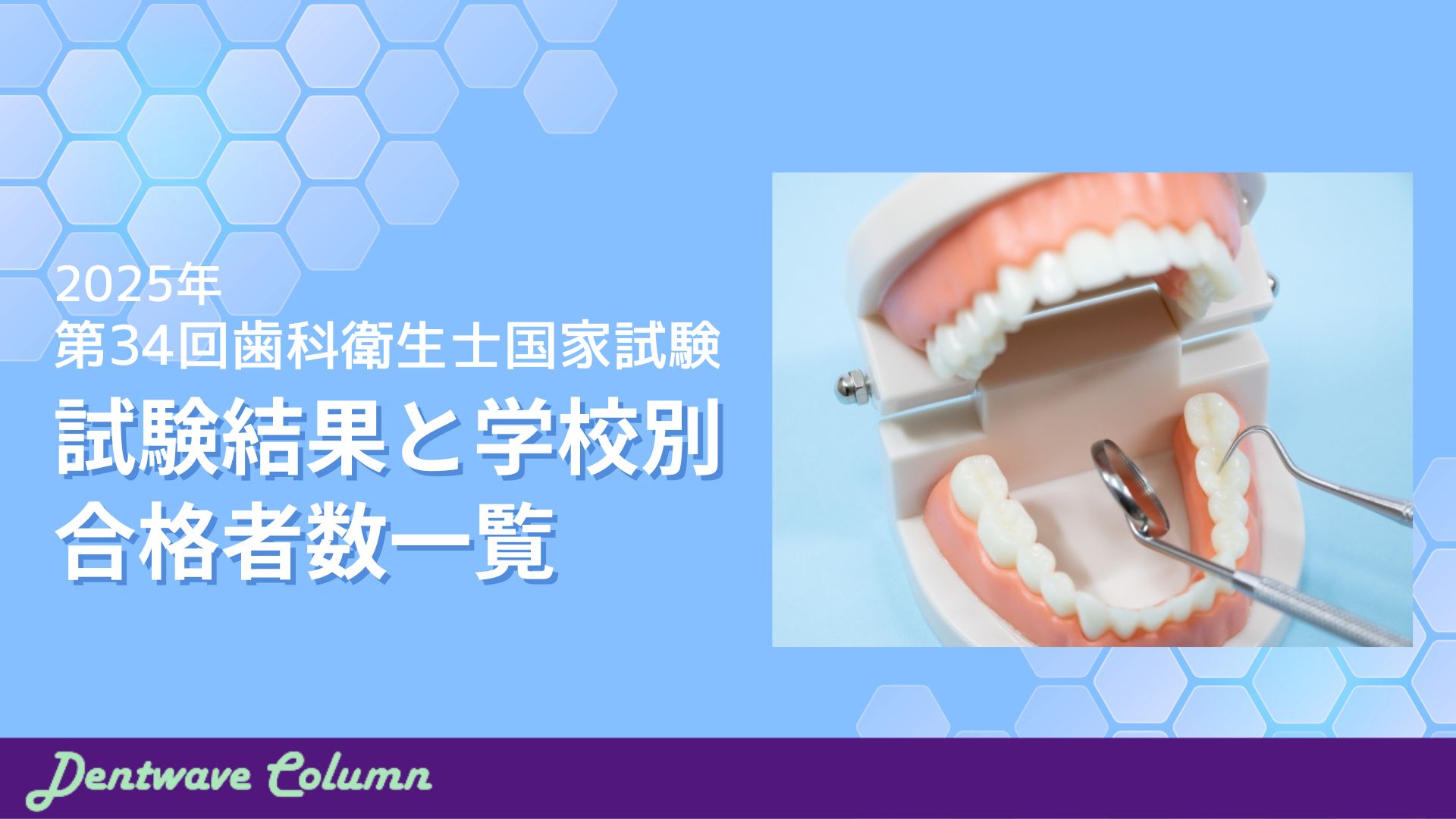コラム - 記事

実は、歯科こそが“食べる入口”として、患者の食生活を支える重要な役割を担っています。近年では、口腔機能と食習慣の関連性が広く認識され、歯科でも栄養指導や食生活のアドバイスを行うことが求められるようになりました。
本記事では、歯科が食事相談に関わる意義とその効果、さらに日常診療で取り入れられる指導のポイントを解説します。
食事の相談も歯科で受けるべき!食事指導の大切さ
1.なぜ歯科が「食事指導」を行うのか?
食事は、歯の健康を守る上で欠かせない要素です。歯科での食事指導には、他職種とは異なる意義があります。
1-1.食べ方のクセとう蝕・歯周病の関係
甘いものの摂取頻度や間食の習慣は、う蝕リスクと直結します。加えて、よく噛まずに食べる・片側だけで咀嚼するといった“食べ方のクセ”も、歯列の乱れや歯周病リスクを高める原因となります。こうした生活習慣は、歯科診療中の観察や問診で発見されやすく、早期の対応が可能です。
1-2.咀嚼力・嚥下機能の状態と食事選択
咀嚼力が低下している患者では、「固いものを避けてやわらかい食品中心の食生活になっている」といった偏りが生じがちです。これにより栄養素の摂取バランスが崩れ、低栄養やフレイルを引き起こすことがあります。口腔の評価とあわせて食生活を確認することで、全身の健康支援にもつながります。
1-3.食生活のアドバイスは予防歯科の延長線上にある
「フッ素」「シーラント」などの予防処置だけでなく、食べ方や食材の選び方に対するアドバイスも、口腔疾患の予防につながります。定期健診の中で「食べる内容・回数」にも目を向けることで、真に包括的な予防歯科が実現します。
2.実際に歯科で行える食事相談の進め方
限られた診療時間の中でも、歯科ならではの視点で実践できる食事指導の工夫をご紹介します。
2-1.食事に関する問診をルーティン化する
初診時や健診時に「1日の食事内容」や「間食のタイミング」を簡単にヒアリングするだけでも、食習慣の傾向がつかめます。子どもなら「おやつは何を食べる?」、高齢者なら「噛みにくいものはある?」など、対象に応じた質問項目をあらかじめ準備しておくとスムーズです。
2-1.“提案型”の指導を
食事内容の指摘はときに患者に抵抗感を与えるため、「だめ」ではなく「こうしてみるといいかもしれませんね」といった提案型のアプローチが有効です。「キシリトールガムを噛む習慣をつける」「砂糖の少ないおやつに変える」など、小さな改善から始めることで継続しやすくなります。
2-2.家族や保護者への関与も重要
特に小児や高齢者の場合、食事の内容やタイミングは家族の影響が大きいため、保護者・介護者への説明も欠かせません。口腔機能の変化に気づいてもらうだけでなく、「この子は咀嚼が弱いので、切り方や食材の選び方に工夫を」など具体的なアドバイスが効果的です。
3.食事指導によって得られる効果と連携の重要性
歯科が行う食事指導は、単なる口腔疾患の予防にとどまらず、全身の健康や生活の質にも大きく関与します。
3-1.患者の“気づき”を引き出せる
食事に関するアドバイスは、患者自身が自身の生活習慣を振り返るきっかけにもなります。「食べるスピードが早いかも」「噛まずに飲み込んでいた」など、行動変容の第一歩を促せるのは、日常的に口腔を扱う歯科の強みです。
3-2.医科・管理栄養士との連携が効果を高める
栄養状態の改善や摂食嚥下の支援が必要なケースでは、医科や管理栄養士との連携も大切です。歯科からの食事評価を共有することで、より総合的な生活支援が可能になります。地域包括ケアシステムの一端を担う視点も求められます。
まとめ|「食べる力」を支える歯科の食事支援
歯科における食事指導は、口の健康を守るだけでなく、患者の全身の健康・生活の質向上にもつながる重要なアプローチです。
特に、日々の診療で食習慣や口腔機能の変化を目の当たりにする立場にある歯科医療従事者だからこそ、生活に根ざした食事アドバイスができます。小児から高齢者まで、それぞれのライフステージに応じた支援を行うことで、真に地域に信頼される歯科医療の実践が可能となります。
日々のちょっとした気づきが、患者の食生活と健康に大きな影響を与えるかもしれません。明日からの診療で、ぜひ一言「食事はどんな感じですか?」と声をかけてみてはいかがでしょうか。