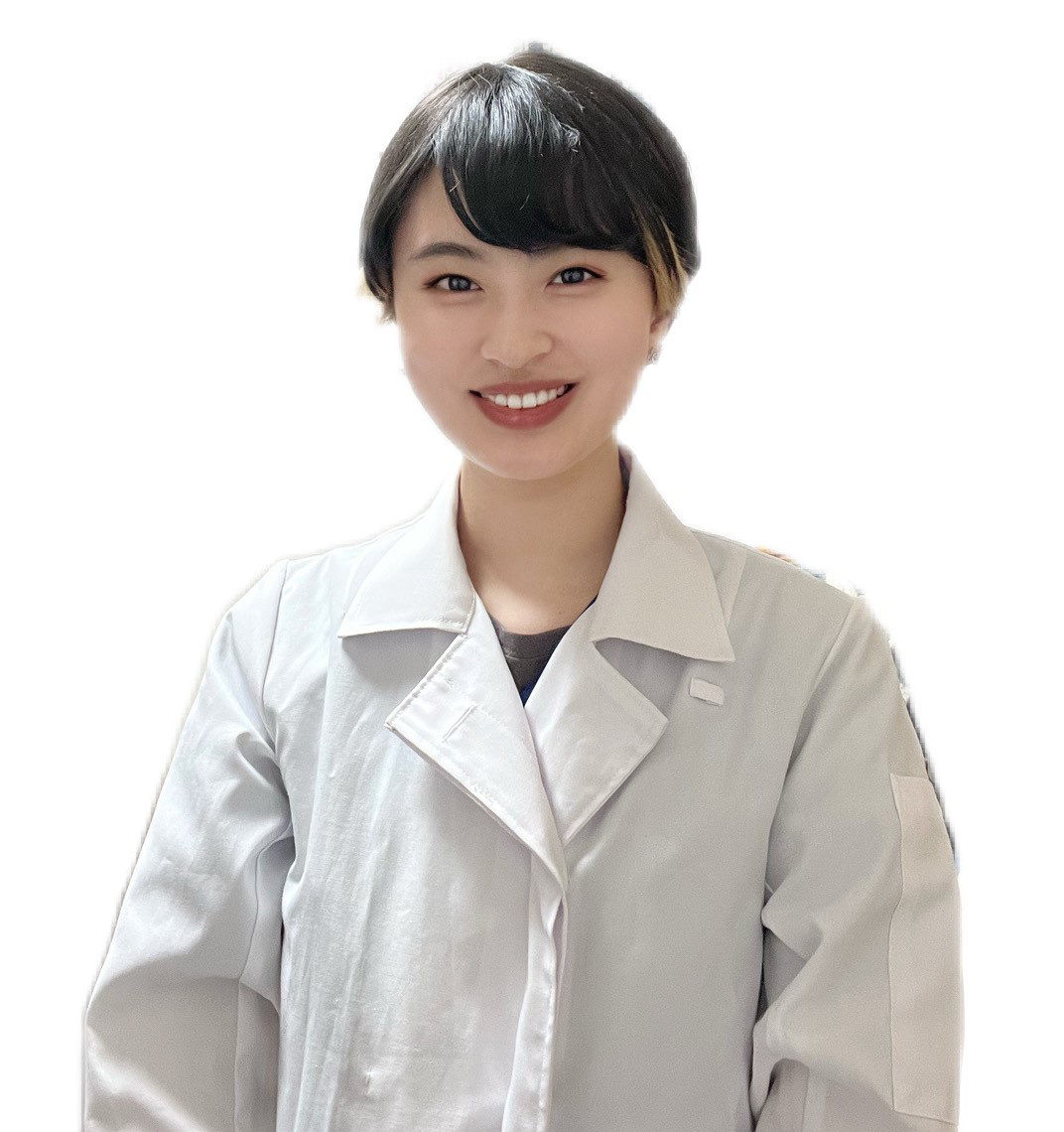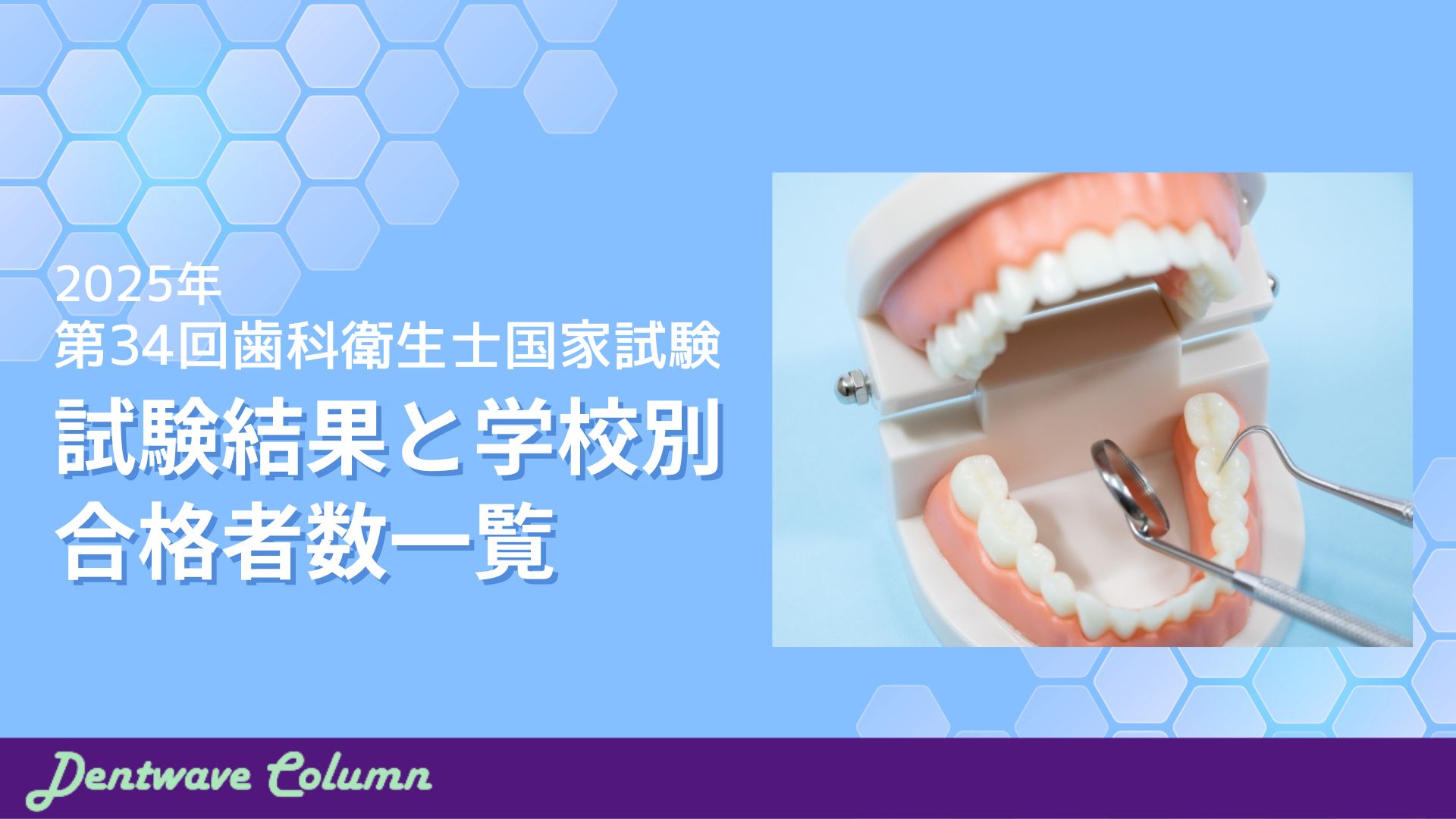コラム - 記事

近年、小児の食べる機能に関する関心が高まる一方で、咀嚼や嚥下の発達に課題を持つ子どもが増加傾向にあります。歯科医療従事者として、単に歯の健康を守るだけでなく、「食べる力=口腔機能」を育む視点が重要です。
本稿では、小児患者とその保護者に伝えるべき「食べる機能の大切さ」と、現場での支援のポイントを解説します。
小児患者と保護者に伝える食べる機能の大切さ
1.「食べる機能」とは何か?
まずは、「食べる」という行為がどれほど複雑な機能の連携によって成り立っているかを整理しましょう。
1-2.咀嚼・嚥下だけではない「食べる力」
「食べる機能」とは、単に咀嚼(噛む)や嚥下(飲み込む)だけではなく、食べ物を認識し、口に運び、咀嚼し、嚥下し、消化に送り込むまでの一連のプロセス全体を指します。この機能には、感覚統合(味・匂い・見た目)、唇や舌、頬の協調運動、呼吸との連動など、多くの要素が関与しています。
1-3.発達の過程で育てる機能
乳児期から幼児期にかけて、「食べる力」は段階的に育ちます。初期の哺乳行動から始まり、離乳食、幼児食へと移行する過程で、舌や顎の動き、飲み込みの能力が獲得されていきます。こうした口腔機能の発達が不十分なまま成長すると、将来的に偏食や嚥下障害、う蝕リスクの増加につながる可能性があります。
1-4.発達段階に応じた支援がカギ
食べる機能の発達は年齢や個人差によって大きく異なります。乳児期には嚥下の安定性、幼児期には咀嚼・舌の動きの発達、小学校以降では「正しく噛む」「食事のリズムを整える」といった生活習慣への移行が重要になります。発達が遅れている子どもには、機能的な未熟さだけでなく感覚の問題が潜んでいることも多く、早期の評価が望まれます。
2.食べる機能と全身の健康の関係
口腔機能の未発達は、単なる“食べにくさ”にとどまらず、子どもの成長や社会性にも影響を及ぼします。
2-1.栄養摂取の偏りと発育への影響
咀嚼や嚥下が苦手な子どもは、柔らかい食事や好みのものばかりを選ぶ傾向があり、タンパク質・鉄・亜鉛などの不足を招きやすくなります。これは成長障害や免疫力低下の要因となり、保護者も気づきにくい“隠れた栄養障害”につながるおそれがあります。
2-2.社会性や発話にも影響
「食べる機能」は、口唇・舌・咽頭の協調運動によって支えられており、これは発話機能とも密接に関係しています。つまり、口腔機能の不全は、「言葉が出にくい」「発音が不明瞭」など、コミュニケーションの発達にも影響を及ぼす可能性があります。
3.保護者に伝える際のポイント
医療現場では、限られた診療時間の中で保護者に理解してもらう工夫が求められます。
3-1. “口の使い方=健康の入り口”と伝える
難しい専門用語よりも、「よく噛むことで顔が育ちます」「正しく噛む・飲み込む力があるとう蝕になりにくい」など、生活に即した実感のある言葉が効果的です。「食べることが苦手な子どもは、心と体のSOSを出しているかもしれません」といった伝え方も有効です。
3-2.保護者の「心配」に寄り添う
「偏食がひどい」「お肉が噛めない」「すぐに飲み込んでしまう」などの相談に対し、頭ごなしに否定するのではなく、「一緒に成長を見守りましょう」と前向きに支援する姿勢が信頼形成につながります。
3-3.継続的なフォローの重要性
初回のアドバイスだけで終わらず、定期健診のたびに「変化」に注目し、「前よりよく噛めるようになったね」とポジティブなフィードバックを伝えることで、保護者のモチベーションも維持できます。
4.歯科医院でできるアプローチ
日常診療の中でも、「食べる力」を育むためにできる取り組みがあります。
4-1.咀嚼・嚥下のスクリーニングを習慣に
定期健診の場で、咀嚼能力や口の動かし方を観察することから始めましょう。「一口が大きすぎる」「前歯で噛めていない」「丸飲みしている」などの兆候を見逃さず、早期介入が必要なケースを把握できます。
4-2.教育的アプローチの工夫も重要
待合室に「噛む力の大切さ」や「正しい食べ方」を紹介する掲示物を用意することや、簡単な家庭用トレーニングシートの提供なども啓発につながります。また、地域の保育園・小学校と連携して「よく噛む」習慣を啓発する出前講座などを行う例もあります。
4-3.多職種との連携
咀嚼・嚥下に課題がある場合は、小児科や言語聴覚士、管理栄養士などと連携した対応が望まれます。
まとめ
まとめ|「噛むこと」は成長を支える土台
「食べる機能」は、単なる栄養摂取の手段ではなく、身体の成長・心の発達・社会性の形成に関わる“生きる力”の一部です。歯科医療従事者がその重要性を認識し、保護者に伝えていくことが、子どもたちの健やかな未来を支える第一歩になります。