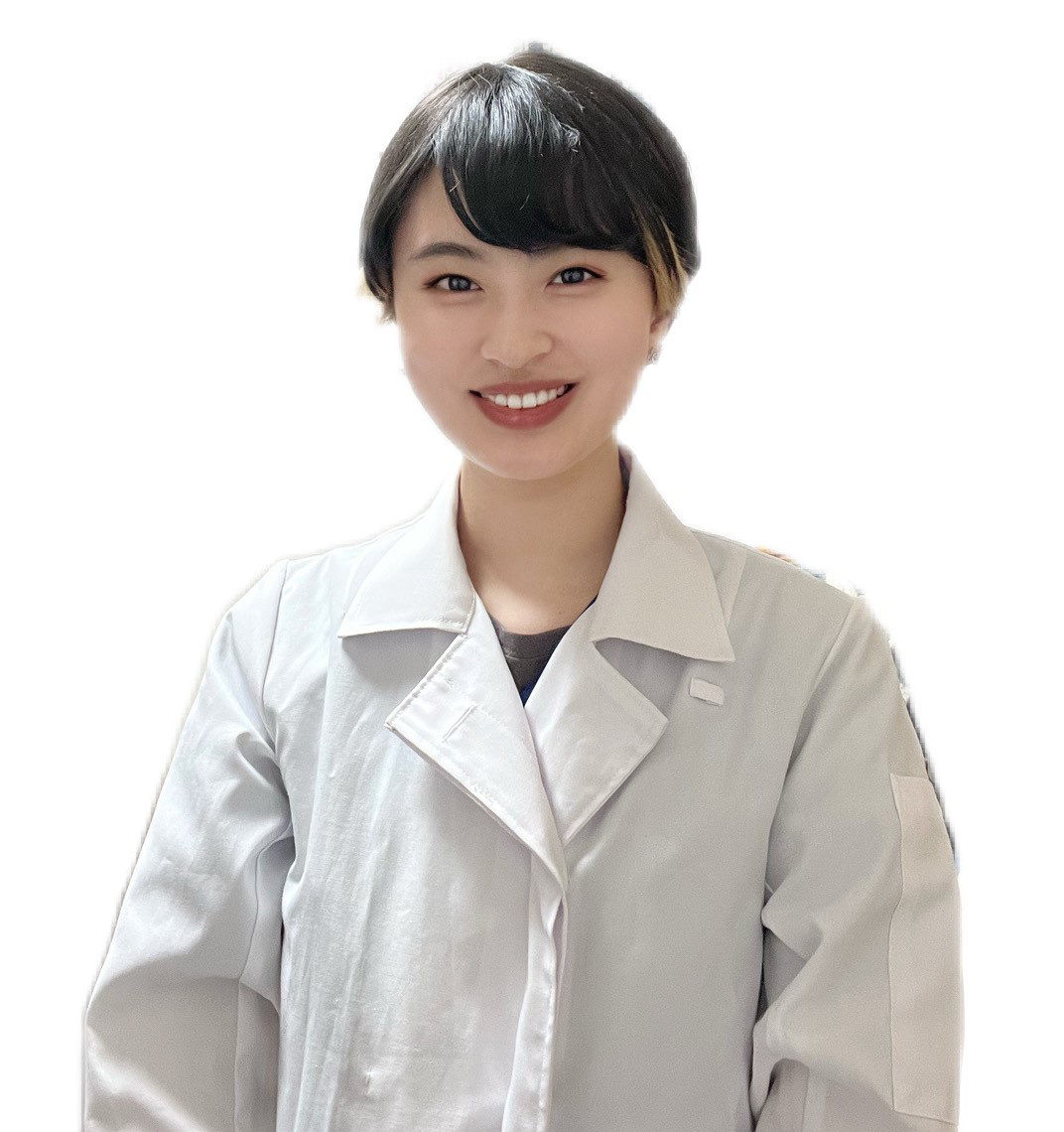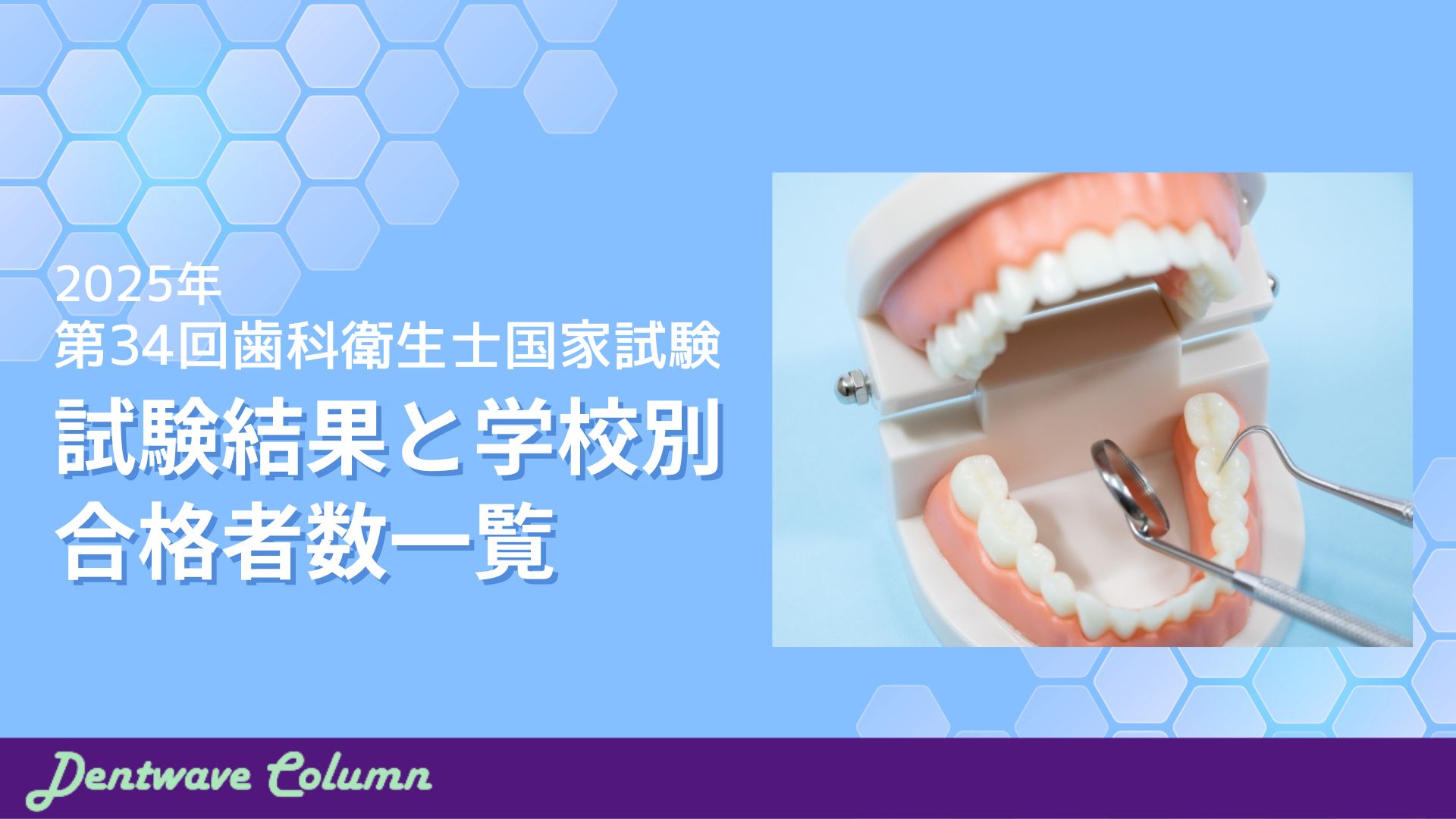コラム - 記事
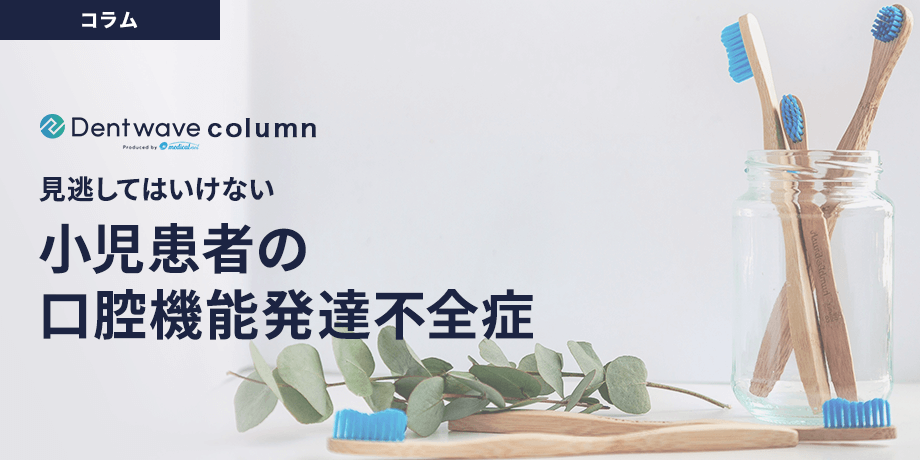
小児の口腔機能発達不全症は、う蝕や歯並びといった“見える問題”の陰に隠れて見逃されやすい疾患です。しかし、放置すれば咀嚼・嚥下・発話の遅れを招き、全身の発達や社会性にまで影響を及ぼす可能性があります。歯科医療従事者は、日々の健診・治療の中で小児の口腔機能に目を向け、早期発見・介入を図ることが求められています。
本記事では、口腔機能発達不全症の基本と診療現場でのアプローチ方法を整理します。
見逃してはいけない小児患者の口腔機能発達不全症
1.口腔機能発達不全症とは何か?
「口腔機能発達不全症」という名称は比較的新しい概念ですが、実際には歯科診療の中で頻繁に出会っている可能性があります。2018年に保険病名として認定されたことで、臨床現場での評価・介入がより求められるようになりました。機能発達の遅れは、見逃されやすく放置されやすいため、まずは正しい定義と診断のポイントを把握しておくことが不可欠です。
1-1.定義と診断基準
口腔機能発達不全症とは、食べる・話す・飲み込むといった口腔の機能が年齢相応に発達していない状態を指します。診断には、厚生労働省の定める「評価項目」のうち2項目以上の異常があり、かつ機能的問題が生活上支障をきたしていることが条件です(例:咀嚼・嚥下困難、口呼吸、構音障害など)。
1-2.どのような子に多いのか?
乳幼児期から発達の遅れや偏食傾向がみられ、食事に時間がかかる・丸呑みが多い・噛まない・むせやすいなどの訴えがある子どもは、口腔機能発達不全症の可能性があります。特に、発達障害や低出生体重児、口腔習癖がある児には注意が必要です。
2.見逃されやすい“兆候”に気づくために
口腔機能発達不全症は、外見や検査結果には現れにくく、保護者や本人も“問題”と認識していないことが少なくありません。しかし、食事や会話など日常生活の中に、機能不全を示唆するさまざまなサインが隠れています。歯科医療従事者として、こうした“違和感”に気づく感性と観察力が求められます。
2-1.食事行動の観察は必須
咀嚼が不十分なまま飲み込む、食事中に姿勢が崩れる、口を開けたまま咀嚼するなどの行動は、単なる“食べグセ”ではなく機能的な課題を反映している可能性があります。診療中に「食事に時間がかかりますか?」「飲み込みにくそうな様子はありますか?」といった問診を加えることで、保護者の気づいていない問題が浮かび上がることもあります。
2-2.発音や会話にも注目を
口腔機能は発音にも深く関わっています。「サ行・ラ行の発音が不明瞭」「滑舌が悪い」などの指摘は、舌や口唇の運動発達が不十分な場合にみられます。構音障害の可能性も含め、言語聴覚士との連携を視野に入れるべきケースです。
3.歯科診療における支援のポイント
診断がついた後、または口腔機能発達不全症の傾向があると判断された子どもに対して、歯科としてどのような支援が可能かを具体的に考える必要があります。口腔機能の発達は、診療室の中だけで完結するものではなく、家庭・園・学校生活を通じた支援体制と連携していく視点が欠かせません。
3-1.多職種と連携したチーム支援を
医科・小児科・ST(言語聴覚士)・栄養士・保育士などとの連携は、評価・支援の精度を高めます。例えば、歯科では咀嚼と嚥下の観察に強みがあり、医科は嚥下内視鏡(VE)やバリウム検査、STは構音や食具の使い方の指導を担います。多職種チームで「子どもの食べる・話す力」を育てる体制が理想です。
3-2.家庭でできるトレーニング提案
歯科では、家庭で実践できる簡単な咀嚼トレーニングや、遊びの中でできる舌の体操などを紹介すると継続的な支援につながります。「一緒にガムを噛もう」「大きな声で“パタカラ”体操をしよう」など、楽しくできる工夫が保護者からも受け入れられやすいです。
4.医療機関としての早期介入の重要性
機能的な課題は“様子を見る”だけでは改善しません。子どもの成長に伴い、その困難が固定化・複雑化する前に、医療機関が早期に気づき、介入のきっかけをつくることが極めて重要です。介入は早ければ早いほど、改善の可能性が高まり、子ども自身の自信にもつながります。
4-1.放置によるリスクとその後の影響
口腔機能発達不全症を放置すると、以下のような影響が懸念されます。
・偏食や栄養バランスの偏りによる発育不良
・誤嚥リスク・むせの慢性化
・学校生活での会話・発表への消極性
・社会性・自己肯定感の低下
機能の遅れは成長とともに「癖」として固定化するため、就学前までにアプローチを始めることが理想です。
4-2.保護者への理解促進と情報提供
保護者に対しては、「今できないことは、練習でできるようになります」と希望を持ってもらうことが大切です。診断に至らない場合でも、定期的な経過観察や「成長の様子を一緒に見ていきましょう」といった言葉が、支援の第一歩になります。
まとめ|小さな違和感こそ、口腔機能への手がかり
小児の口腔機能発達不全症は、見逃されやすいが支援の必要性が高い領域です。
健診や日常診療の中での「なんとなく気になる」兆候に目を向け、早期にアセスメントを行うことで、子どもの将来の食事・発話・社会性を守ることができます。
歯科医療従事者は、単に歯を見る存在ではなく、「食べる・話す・生きる」を支える専門職です。今後ますます注目される口腔機能支援において、私たちが果たす役割は非常に大きいと言えるでしょう。