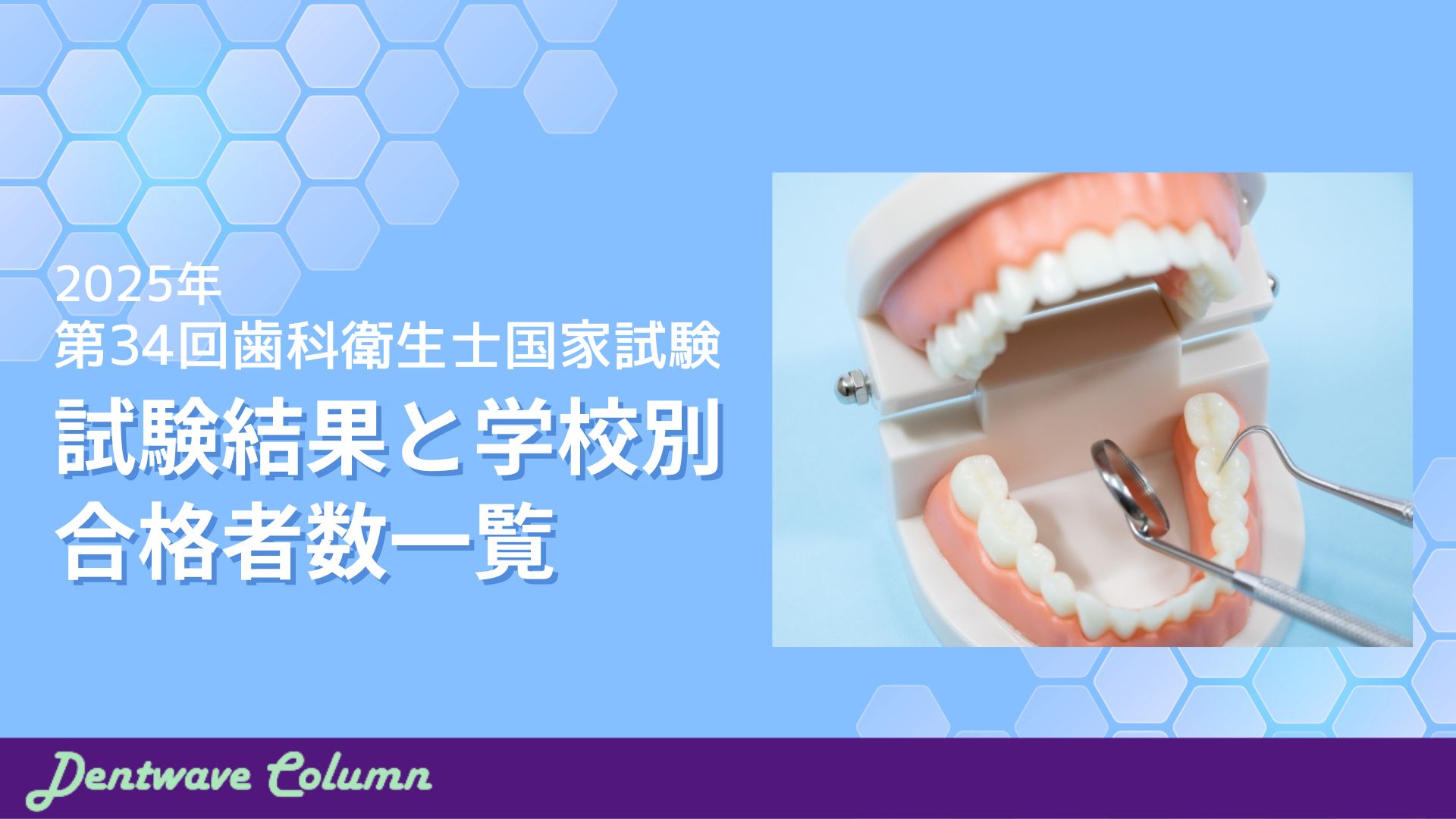コラム - 記事
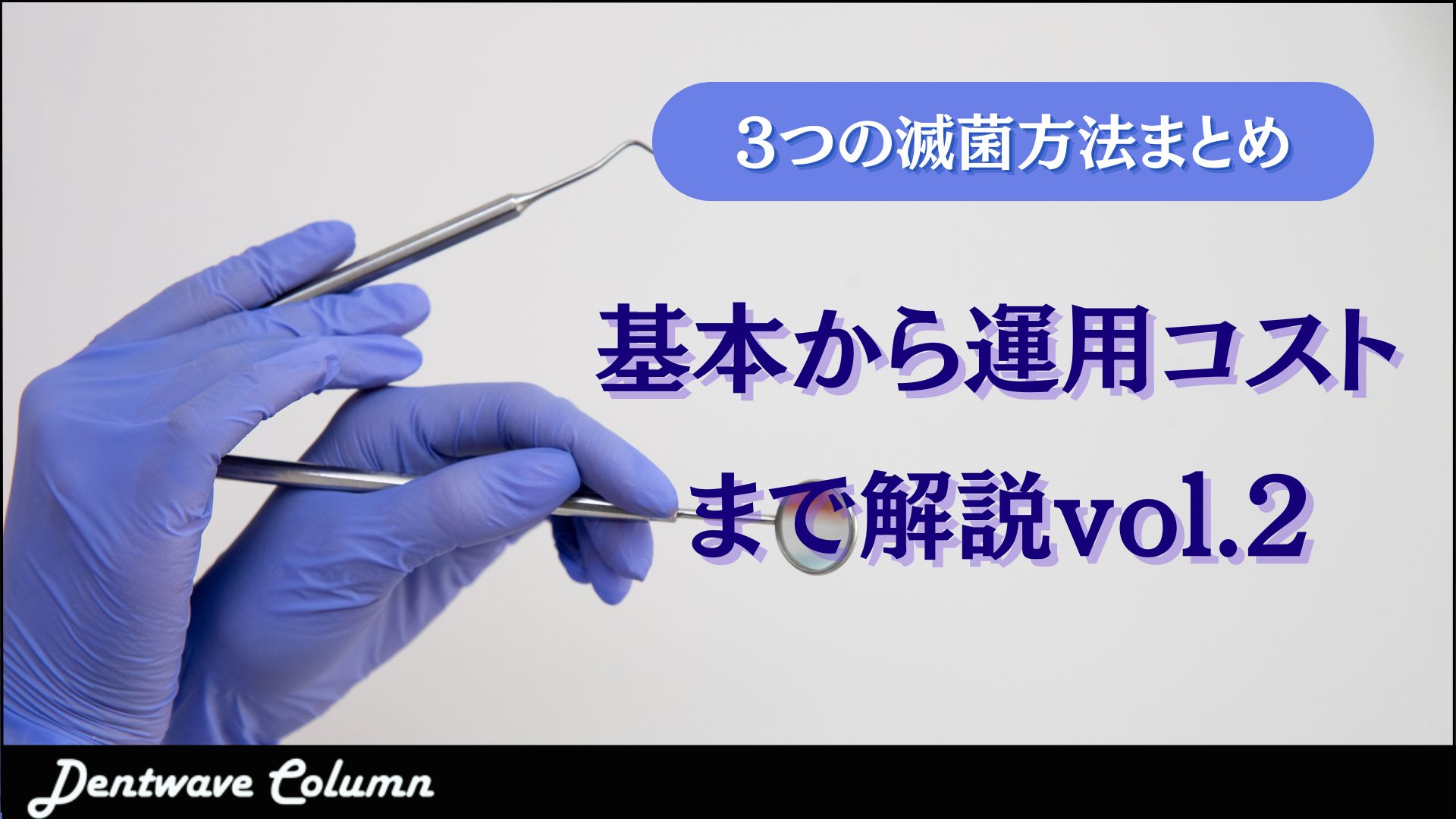
【3つの滅菌方法まとめ】基本から運用コストまで解説vol.2
- 著:ミホ /
-
関連タグ:
クラスBオートクレーブについて
クラスBオートクレーブとは、ヨーロッパ規格に準拠した最高ランクの高圧蒸気滅菌器です。「B」は「Big sterilization(あらゆる器具に対応する大規模滅菌)」の略とも言われています。日本では2010年代前半から普及が始まり、2020年以降のコロナ禍による感染対策の強化により、一気に注目が高まったものです。
なおオートクレーブは、大きく「クラスB」「クラスS」「クラスN」の3つに分けられます。そのランクはクラスB>クラスS>クラスNの順(クラスBが最高ランク)です。
クラスBオートクレーブの主な特徴は以下の通りです。
● 真空ポンプを内蔵していることで、複雑な形状や包装内部まで均一に蒸気を行き渡らせることができる(滅菌効果が高い)
● すべての器具に対応(包装済みの器具、ハンドピース等の中空の器具なども可能)
● ヨーロッパの医療基準に準拠しており、日本でも厚生労働省の院内感染対策指針で推奨されている
歯科衛生士視点でのメリットとしては、滅菌できる器具の種類が広がり、滅菌後の保管・管理がしやすく滅菌にムラが出にくい点等が挙げられます。逆にデメリットとしては、価格が高い点、滅菌にかかる時間が長め(乾燥時間を含め30〜60分)である点等が挙げられます。
とはいえ日本では、2020年以降に新規開業・改装した歯科医院等でなければ、クラスBではなくクラスNオートクレーブを使用している歯科医院が多いと推定されます。
乾熱滅菌器
乾熱滅菌器とは、乾燥した高温の空気を用いて滅菌を行うものです。水蒸気を使うオートクレーブと異なり湿気を伴わず、酸化によって微生物を死滅させます。一般的に170℃で60分の処理が多いです。
現在の歯科医療現場ではオートクレーブが主流であり、乾熱滅菌器の使用頻度は少なく、バーなどの乾熱専用器具にのみ使用されます。
メリット・デメリット
● メリット:湿気を伴わないため、錆びや腐食の心配が少ない。電気代が安い
● デメリット:滅菌に時間がかかる
滅菌可能なもの・不可能なもの
● 滅菌可能なもの:金属製器具など
● 滅菌不可能なもの:ゴム製品、プラスチック製品など
滅菌にかかるコスト
オートクレーブと同じく、ユニット3台で1ユニットあたり毎日30分〜1時間の予約が10〜18時まで入っている歯科医院があるとします。この場合の乾熱滅菌1回あたりのコストは以下の通りです。
| 項目 | 条件・想定 | 概算コスト |
|---|---|---|
| 電気代 | 約1.0〜1.5kWh × 1時間 | 約30〜45円 |
| 滅菌パック | 簡易的であったり使用しないことも | 約0〜30円 |
| 乾熱滅菌器の償却費 | 約50万円 ÷ 7年 ÷ 年300日 × 1日1回の稼働 | 約80円 |
| 合計 | 滅菌1回あたり 約110〜150円程度 |
電気代や滅菌パックの部分で、オートクレーブに比べてコストを抑えられます。しかし用途は限られており滅菌時間も長いです。そのため器具の回転効率が低下しやすく、オートクレーブの補助的役割という認識で良いでしょう。
乾熱滅菌の使用頻度は低く、1日1回の稼働であることも多いです。そのため1日あたりのコストは130円ほど、1ヶ月で見ても3,900円ほどです。
使用方法
器具を洗浄・乾燥後、滅菌器に入れ、規定の温度・時間で滅菌を行います。
使用時の注意点
器具が高温に耐えられるか確認し、過熱による変形や劣化に注意しましょう。
ケミクレーブ(化学蒸気滅菌器)
ホルムアルデヒドやアルコール系の薬液の蒸気を用いて、120℃程度の比較的低温で滅菌を行う方法です。滅菌時間は約30〜60分です。
メリット・デメリット
● メリット:熱に弱い器具の滅菌が可能
● デメリット:薬品の取り扱いに注意が必要
滅菌可能なもの・不可能なもの
● 滅菌可能なもの:熱に弱いプラスチック製品、ゴム製品など
● 滅菌不可能なもの:薬品に反応する材質の器具など
滅菌にかかるコスト
ケミクレーブも同じくコストを計算してみましょう。
| 項目 | 条件・想定 | 概算コスト |
|---|---|---|
| 電気代 | 約1.5〜2.0kWh × 1時間 | 約50〜70円 |
| 薬液代 | ホルマリン系薬剤:約100〜200円/回 | 平均約150円 |
| 滅菌パック・インジケーター | 10個~20個を使用する想定 | 約50〜100円 |
| ケミクレープの償却費 | 約100万円 ÷ 7年 ÷ 年300日 × 1日1回の稼働 | 約100円前後 |
| 換気設備・消臭対応(間接コスト) | フィルター・排気装置等 | 数円〜10円想定 |
| 合計 | 滅菌1回あたり 約350〜450円程度 |
主なコストは薬液です。それに伴う換気設備・臭気対応等、機械を導入した場合はさらにコストがかさみます。このようにケミクレーブはコストがやや高めですが、熱に弱い器具の滅菌という明確な役割があり、とても有効な方法です。
使用方法
器具を洗浄・乾燥後、専用の薬品を用いて滅菌します。
使用時の注意点
薬品の取り扱いや換気、使用後の残留物にも注意が必要です。
歯科衛生士が滅菌機を使用する際の注意点
3つの滅菌器の特徴がわかったところで、歯科衛生士が滅菌機を使用する際の注意点を改めて見てみましょう。
● 滅菌前の注意点
○ 器具の材質を確認する:滅菌機の種類によって使用できる器具が異なるため、材質を確認し適切な滅菌方法を選択すること
○ 洗浄・乾燥の徹底:滅菌前には器具を十分に洗浄・乾燥させ、汚れや水分が残らないようにすること
○ 滅菌パックの使用:滅菌後の再汚染を防ぐため、専用の滅菌パックを使用し密封すること
● 定期的なメンテナンス:滅菌機の性能を維持するため、定期的な点検・メンテナンスを行うこと
まとめ
滅菌機の正しい使用は、患者さんの安全を守るだけでなく医療従事者自身の感染リスクを下げるためにも重要です。滅菌方法にはそれぞれの特徴と役割があり、器具の材質や使用状況に応じて使い分けることが重要です。
オートクレーブは幅広く使える万能型、乾熱滅菌器は金属器具に最適、ケミクレーブは熱に弱い器具の味方と覚えておきましょう。歯科衛生士として滅菌機を正しく理解し、現場でのスキルの一つとして活かしてください。