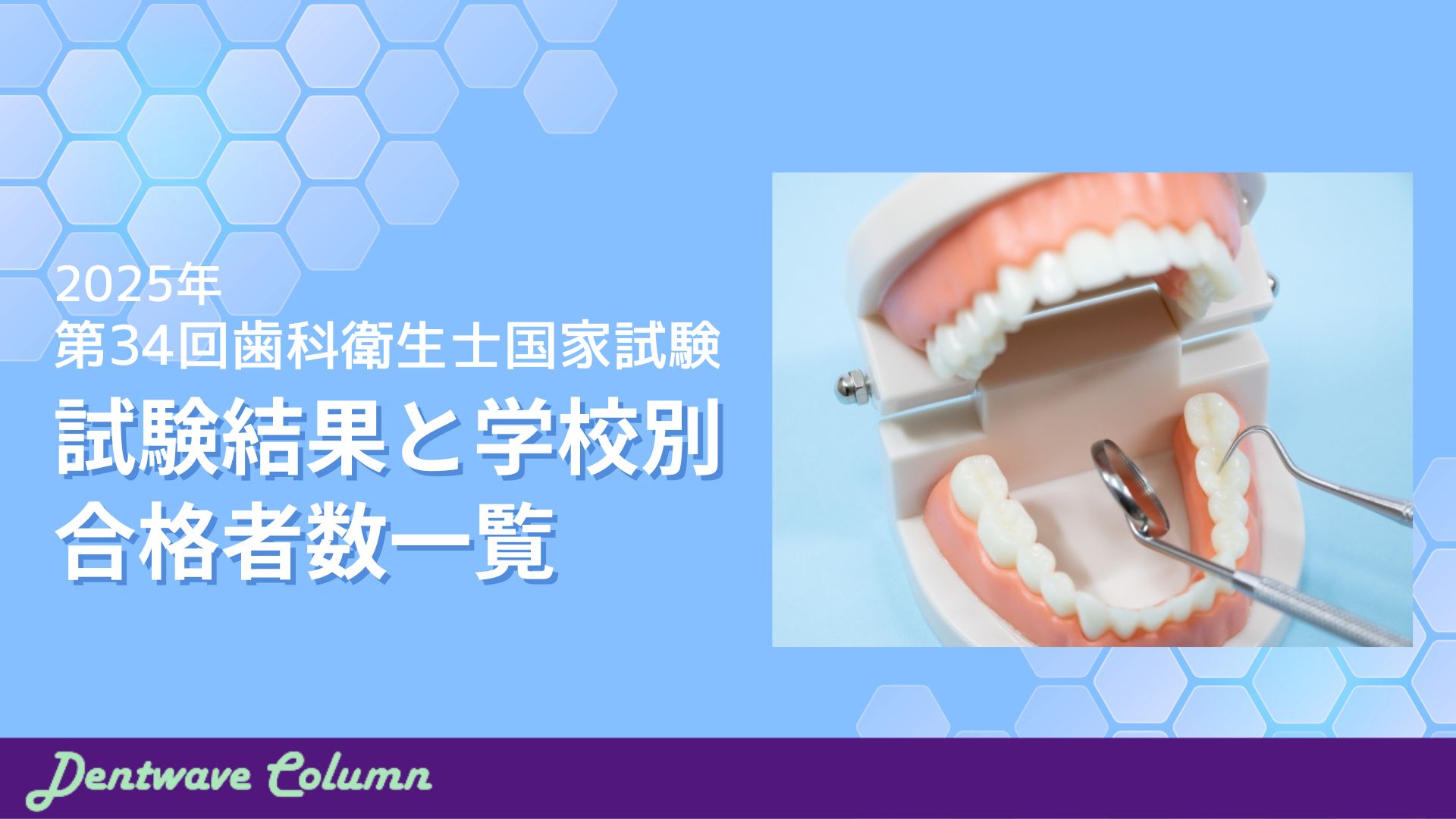コラム - 記事

プロのインプラント治療専門家を続々と輩出! 世界基準のインプラントを学べる「NYU」のススメ
はじめに
ニューヨーク大学(以下、NYU)の卒後研修プログラムを経験された先生方にお集まりいただき、その経験や学び、ネットワークの広がりについてお話しいただきました。日本における歯科医療の発展に寄与する国際的な研修プログラムの魅力を、実際の体験談を交えてお届けします。
ご参加いただいた先生紹介
鈴木仙一先生 (銀座・町田・海老名でインプラントセンターを開業)
NYU卒業(第2期)。NYU同窓会会長。
2019年から2022年まで世界最大のインプラント学会かつ、インパクトファクターが世界第8位のICOI国際口腔インプラント学会の世界会長を3年務める。
池田寛先生(江東区で開業)
NYU卒業(第10期)。ICOIの理事を務めながら、バイスディレクターとしても活動。グアテマラで国際客員教授としてサイナスリフト実習など指導を務める。
野瀬冬樹先生(調布市で開業)
2013年から2015年までNYUでレジデントとしてインプラント科に所属し、診療に従事。
その後、2015年から2016年の1年間、クリニカルフェローとして学生への指導を行いながら、臨床を行う。
落合久彦先生(恵比寿で開業)
NYU卒業(第8期)。ICOI理事を務めながら、プログラムリーダーを担当。
高山剛栄先生(中央区で開業)
NYU卒業(第8期)。ICOIの理事を務めながら、プログラムリーダーを担当。
佐藤明寿先生(港区で開業)
NYU卒業(第11期)。プログラムリーダーやアシスタントディレクターという形で受講生のサポートを担当。
池田先生:NYUの卒後研修コースは、インプラント治療を専門的に学べるコースです。1981年に誕生し、今では世界26カ国、3,200人を超える卒業生がいます。2年にわたりインプラントを基礎からサイナスリフト、GBR、CTG、リカバリー等を学び、ニューヨークだけでなく、青島市(チンタオ)での解剖実習、グアテマラでのサイナスリフトやCTGの実施を通して知識だけではなく、技術を修得することができます。
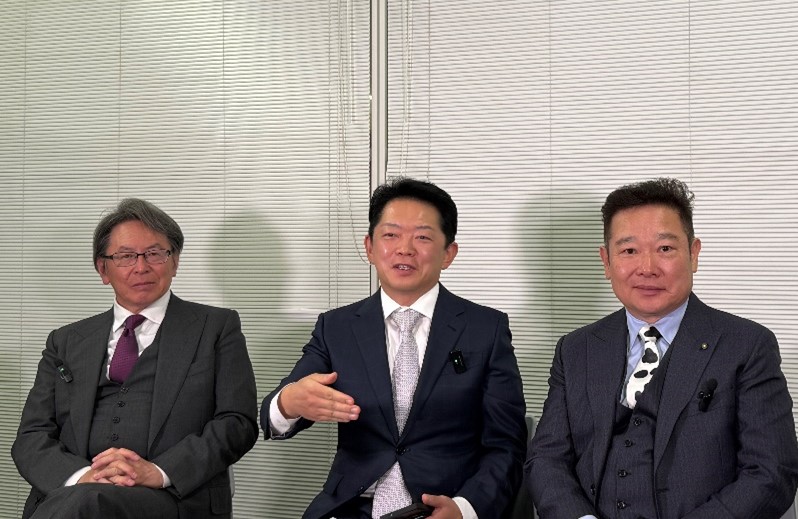
Dentwave編集部:ありがとうございます。では、NYU発足の経緯についてお話いただけますでしょうか?
鈴木先生:NYUのコースは、1981年から世界中の先生方がNYUに訪れ、学ぶものになっています。副学長のケン・ビージム先生がコースに取り入れ、継続教育(コンティニュイングエデュケーション)として続いています。日本では2003年から始まり、最先端の技術や知識を学ぶために発足に至りました。発足から20年続いており、ご高名な先生方を多数輩出しているプログラムになっております。

Dentwave編集部:とても歴史あるプログラムであると感じました。NYUとスタディグループ、どちらも自己研鑽の場であると思いますが、違いはどのような点にあるのでしょうか?
池田先生:そうですね。座学から始まり、実習を経て、献体実習やグアテマラで実際の患者さんに手術をする機会があったことです。日本では講義を受けて実習で終わることが多いですが、NYUではステップを踏んで実際に患者さんに治療する経験ができるのが大きな違いだと思います。治療する時は誰でも緊張や不安になるものですが、マンツーマンで指導を受けながら進めるので、それが一番の違いになっていると思います。
Dentwave編集部:ありがとうございます。患者さんに実際に治療を提供できるというのは大きな違いになるのですね。佐藤先生はいかがでしょうか?
佐藤先生:昨今、オンラインで手軽に受けられるレクチャーが増えていますが、個人的には、海外に行って実際に大学で学ぶことは他とは違うと感じています。ニューヨークの空気感や、講義室でニューヨーク大学や各国を代表する素晴らしい先生方の講義を実際に聞くというのは、オンラインと比べてすごく思い入れに残っています。ただ聞くだけでは記憶に残らず、実際の体験が自分に深く刻まれることが、他との大きな違いだと思っています。
Dentwave編集部:なるほど。学びに対しての覚悟が違うのだとお話を伺い思いました。野瀬先生ですとレジデントとして、対応されていたかと思いますが、現場で学ぶことの違いをお伺いできますでしょうか?
野瀬先生:僕が留学する際にNYUを選んだ理由は、まず立地。マンハッタンという人口が多い場所にあり、知名度も高いため患者数が非常に多かったことです。また、日本では卒後しばらくの先生が上級医の見学やアシストを通じて学びますが、アメリカではNYUをはじめ、若手のレジデントが実際に治療を行い、上級医はその治療をスーパーバイズするという逆のシステムが特徴です。これは知識や技術を学ぶ上で大きなメリットがあると感じました。さらに、NYUは歴史があり、学生数も全米で一番多く、教科書や論文で目にするような著名な医師が実際に廊下を歩いているような環境で学ぶことができ、非常に刺激的で貴重な経験でした。
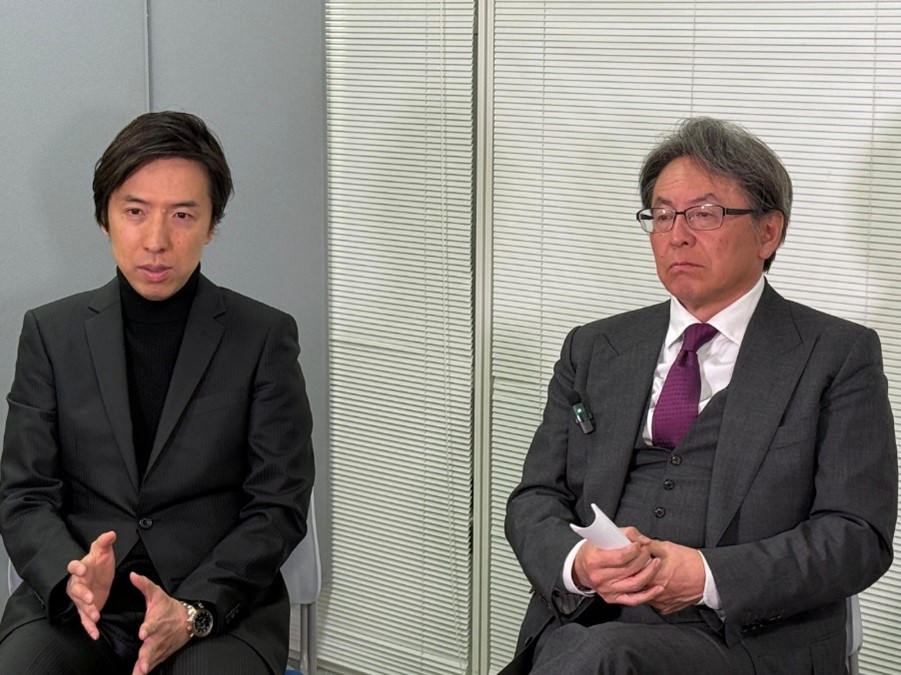
Dentwave編集部:ありがとうございます。自分の価値観が広がるというのは、歯科に対してだけでなく、人としても成長ができる機会になりますね。その部分に関して、以前プログラムに参加された際に成長を感じた体験などありますでしょうか?
高山先生:今ではインプラントが当たり前になっていますが、当時はまだそれほど普及しておらず、実際に多くの先生方がそれを取り入れた治療をしているのを見て、すごく刺激を受けました。
当時、7期~9期くらいの先生たちが今のスタディグループのトップで、彼らとゴルフや食事を共にしながら、横のつながりがとても強固になったことを実感しています。世代を超えた横のつながりが非常にできたと感じていますね。
日本だと単発で、懇親会で挨拶する程度で終わりますが、NYUのコースは2年間という長い期間を通して、再会する度に深い繋がりが生まれます。こうした経験は本当に貴重でした。

Dentwave編集部:ありがとうございます。では、実際にNYUの研修を終えて、どのような変化がありましたか?
池田先生:歯科医師として個人開業だと悩みを共有する相手が少ないかと思いますが、NYUで学んだ先生方からは、経験に基づいてアドバイスをもらえることが大きな助けでした。小さな悩みも誰かに話すことで解決し、気持ちが楽になります。みんなと過ごすうちに、最初は気取っていたことも徐々に深い話ができるようになり、つながりが強くなりました。NYUを終えた後も、定期的に会う仲間ができ、一緒に目指す方向性を共有することで、今までの友達とは違った深い関係が築けました。こうして切磋琢磨できる仲間が増え、歯科医師としての人生がより豊かになったと実感しています。
落合先生:そうですね、私の一番の変化は英語を学べたことです。日本にいると英語を話す機会が少ないですが、ニューヨークでは多種多様な方と接することで、患者さんとの会話もスムーズにできるようになりました。帰国後は、心のゆとりも生まれ、より自信を持って接することができるようになりましたね。
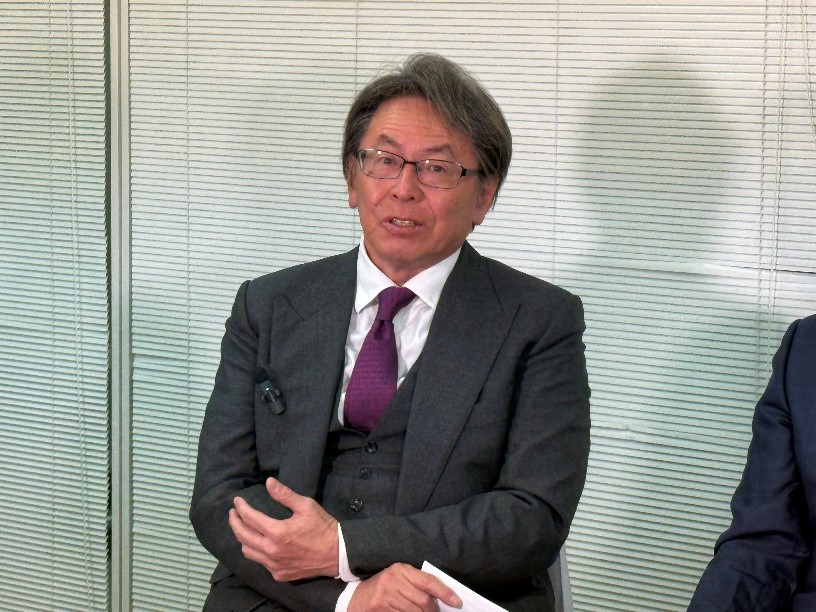
Dentwave編集部:同じ意識を持った仲間や日本との環境の違いは、自信を成長させる刺激になりますよね。今後NYUではどのような活動をされ、どのような先生方にご参加いただきたいですか?
鈴木先生:NYUのコースは進化を続けています。今後、インプラント治療やペリオなどを深めたい方にはぜひご参加いただければと思います。中でもNYUは、インプラント治療に関しては、圧倒的な本数を誇ります。また、教科書に載るような先生方から直接学ぶ機会がある点も大きな魅力です。今後においては、NYUは、ロボット治療等の最先端の技術を取り入れており、これからも進化し続けると思います。皆さん、ぜひ学びに来てください。

Dentwave編集部:最後に、NYUの研修コースについてご案内いただけますか?
佐藤先生:NYUコースは現在第20期の募集が始まっており、3月からオンラインレクチャーがスタートしています。このコースは長年続いており、他の海外研修コースとは一線を画しています。卒業生の皆様も臨床の第一線で活躍しております。コースやカリキュラムの詳細については、短期留学コースという形で公式サイトにてご確認いただけます。
実際にニューヨークまで行って留学するのは大変なことだと思いますが、NYUで学んだことは臨床に大いに役立っています。インプラントの細かい術式やサイナスイフトの技術を学んだことは自身の臨床の礎となっており、それを患者さんに還元できています。費用はかかりますが、貴重な経験や切磋琢磨できる仲間とのつながりを得ることができ、自分にとって大きな宝物だと思います。コースは途中からでも参加可能で、補講もあり、柔軟に対応していますので、ぜひご検討ください。ご不明点があれば、気軽に問い合わせいただければと思います。

Dentwave編集部:本日は貴重なお話をありがとうございました!

編集部より
今回、NYUで得られる学びや経験、そして「人との繋がり」の大切さを先生方のリアルな声から感じることができました。単なる研修ではなく、臨床力を高め、自信を持って診療に臨めるようになる。それは、オンラインなどの画面越しでは得られない“体験”がもたらす力なのだと思います。
これから海外で学ぶことを検討している方、また新たな一歩を踏み出そうとしている方にとって、この記事が背中をそっと押すきっかけになれば嬉しいです。