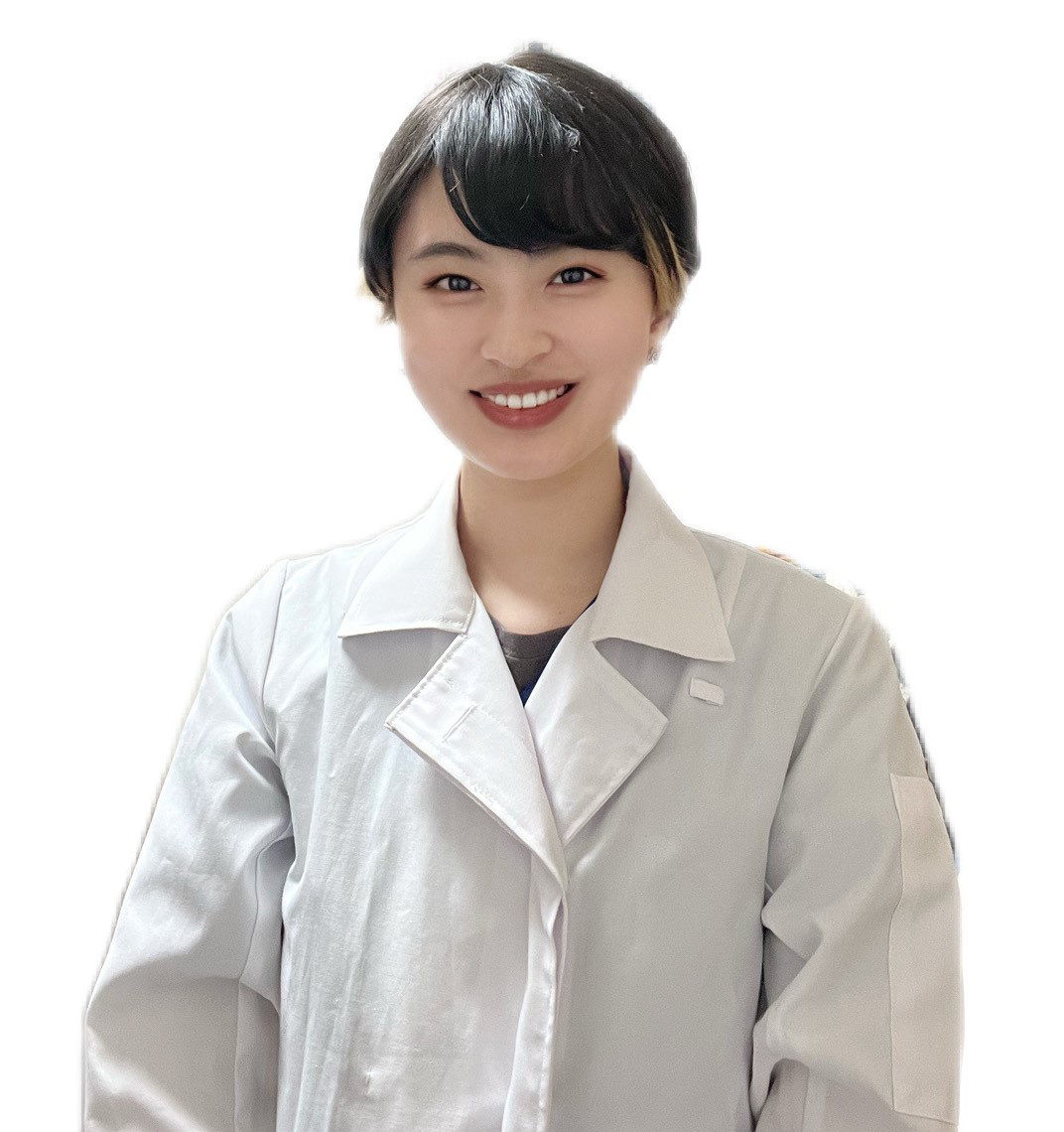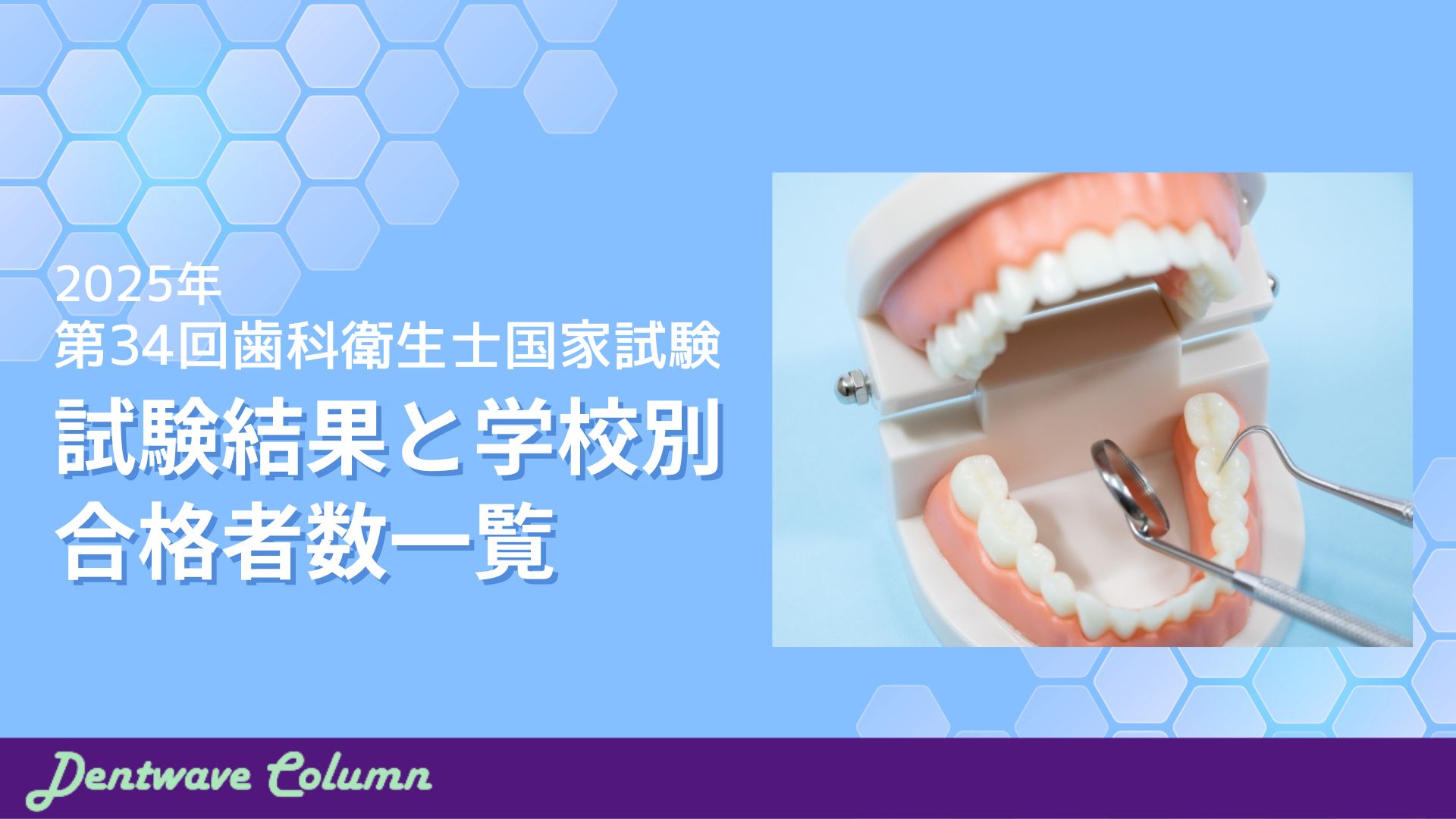コラム - 記事
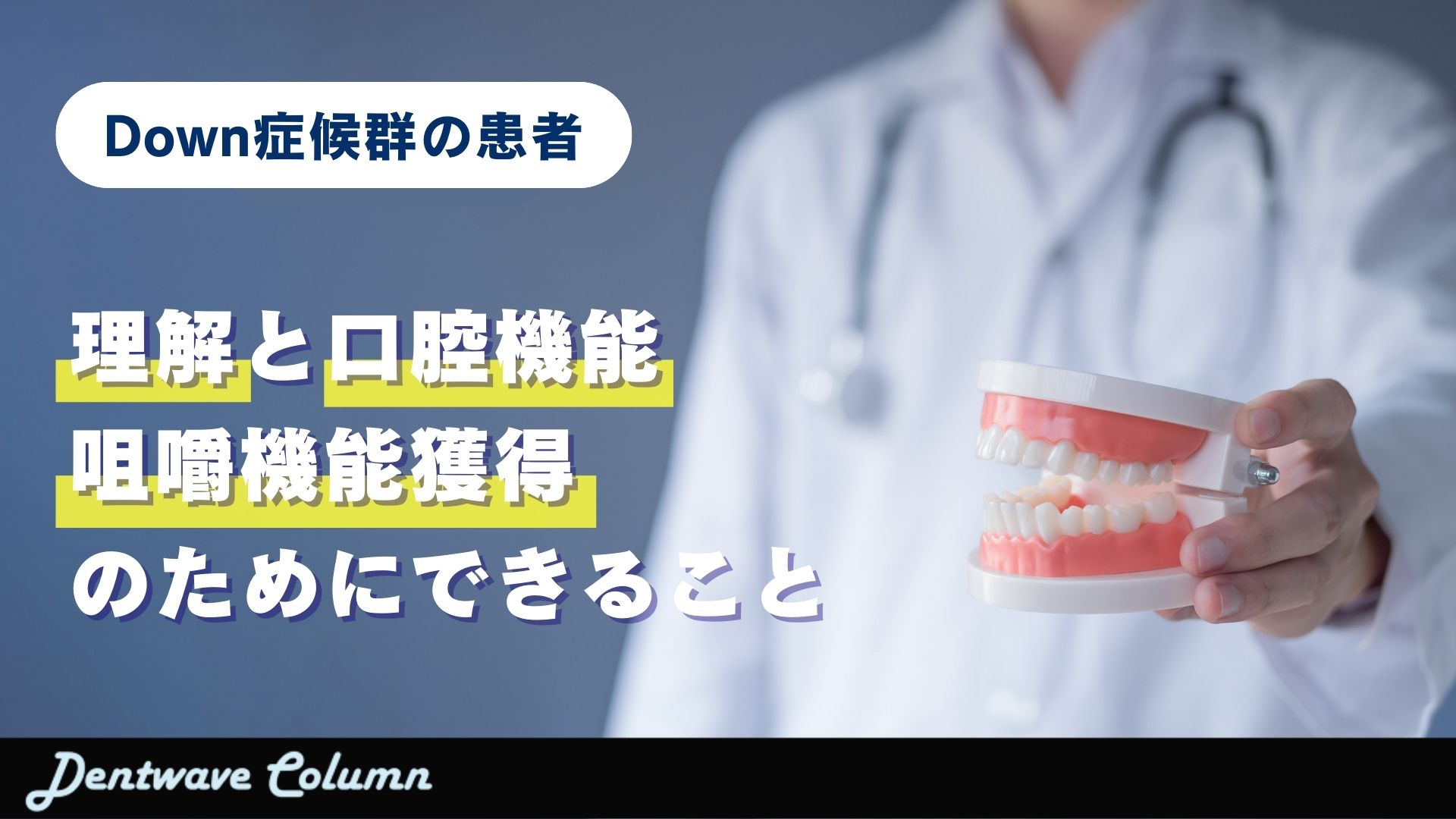
本記事では、歯科医療従事者として知っておきたいDown症候群の基礎理解と、口腔機能・咀嚼機能を高めるための具体的アプローチについて論じます。
Down症候群の患者への理解と口腔機能・咀嚼機能の獲得のためにできること
1.Down症候群に特有の口腔および全身的特徴
Down症候群は第21番染色体の過剰により発生し、全身的な特徴が歯科治療の場面にも直接的・間接的な影響を与えます。歯科的には以下のような特徴が見られます。
①低緊張(hypotonia)
咀嚼筋群や口腔周囲筋の筋緊張(トーヌス)が低いため、開口状態の保持、嚥下、発音等に支障をきたします。
②顎顔面の発育遅延
上顎の劣成長や舌の相対的巨大化(macroglossia)により、開口咬合、交叉咬合、不正咬合が高頻度で認められます。
③歯の形成異常・萌出遅延
歯数の欠如(先天性欠如)、小歯症、エナメル質形成不全、乳歯・永久歯ともに萌出が著しく遅れる傾向があり、口腔機能発達の遅延に拍車をかけます。
これらの問題は、単なる解剖学的特徴に留まらず、咀嚼機能、嚥下機能、構音機能のいずれにも影響し、生活の質(QOL)や全身健康にも深く関わります。
2.咀嚼機能の発達における課題と意義
咀嚼機能は単なる食物粉砕の動作にとどまらず、栄養摂取の効率化、消化器系の負担軽減、顔貌形成、さらには認知発達との相関も指摘されています。Down症候群では、発達遅延や筋緊張の問題により、硬い食物を避ける傾向が強く、結果として咀嚼刺激が不足し、機能の未発達や退行を招きやすい傾向があります。
また、舌突出や嚥下障害を合併することで、食塊形成が困難となり、誤嚥リスクや窒息の可能性が高まるため、単なる咀嚼訓練だけでなく、トータルな口腔機能訓練が必要です。
3.歯科医療従事者が担う多職種連携と臨床的アプローチ
3-1. 個別化された口腔機能発達支援
個々の患者の発達段階や口腔形態に応じたアセスメントを行い、個別のプログラムを設計することが基本です。具体的には、口腔周囲筋訓練、咀嚼誘導食の活用、感覚統合療法的なアプローチ(ブラッシングや舌刺激を通じた覚醒レベルの調整)などが効果的です。
3-2. 保護者・介助者の教育と啓発
咀嚼訓練は家庭内での継続的な取り組みが成功の鍵となります。食事環境の整備、姿勢保持の工夫、食材の調理形態の調整など、日常生活に組み込む形での支援を推奨します。定期的なフィードバックと教育プログラムの導入が、家族の不安軽減にもつながります。
3-3. 安心できる診療環境の構築
Down症候群のある患者は感覚過敏や予測不能な環境に対する不安を強く感じる場合があります。そのため、同じ診療スタッフが一貫して対応する「担当制」、視覚的支援ツール(絵カードやスケジュール表)の活用、処置内容の見通しを事前に説明する手法(ソーシャルストーリー)などを導入すると、協力的な姿勢を引き出しやすくなります。
3-4. 多職種連携による包括的支援体制の構築
言語聴覚士、作業療法士、栄養士、小児科医、特別支援学校教員との連携を通じて、単独の診療では対応しきれない領域を補完し、患者の全人的な発達支援を行うことが可能となります。地域における支援ネットワークの把握と活用も、歯科医療者の大切な役割です。
4.Down 症候群患者の定期健診の重要性
Down症候群を有する患者においては、口腔内の構造的・機能的特性により、う蝕、歯周病、不正咬合のリスクが高く、加えてセルフケアの困難さや保護者の支援への依存度の高さから、定期的な専門的評価と介入が不可欠です。特に、低緊張や免疫機能の低下は歯周組織に対する感受性を高め、若年からの歯周炎進行を助長します。
定期健診では、単なる処置にとどまらず、成長に伴う咬合変化のモニタリング、咀嚼・嚥下機能のチェック、保護者への生活指導など、多面的なアプローチが求められます。また、医科歯科連携や地域支援機関との情報共有を通じて、個々の健康状態や発達状況に即した包括的支援が可能となります。継続的な健診体制の構築は、生活の質の向上に直結する極めて重要な取り組みです。
まとめ
Down症候群のある患者への歯科的支援は、機能の回復や改善のみならず、彼らの「生活の自立」を後押しする重要な要素です。
歯科医療従事者が彼らの特性を正しく理解し、尊重しながら継続的な支援を行うことで、患者の生活に寄り添った医療の実現に近づくことができます。