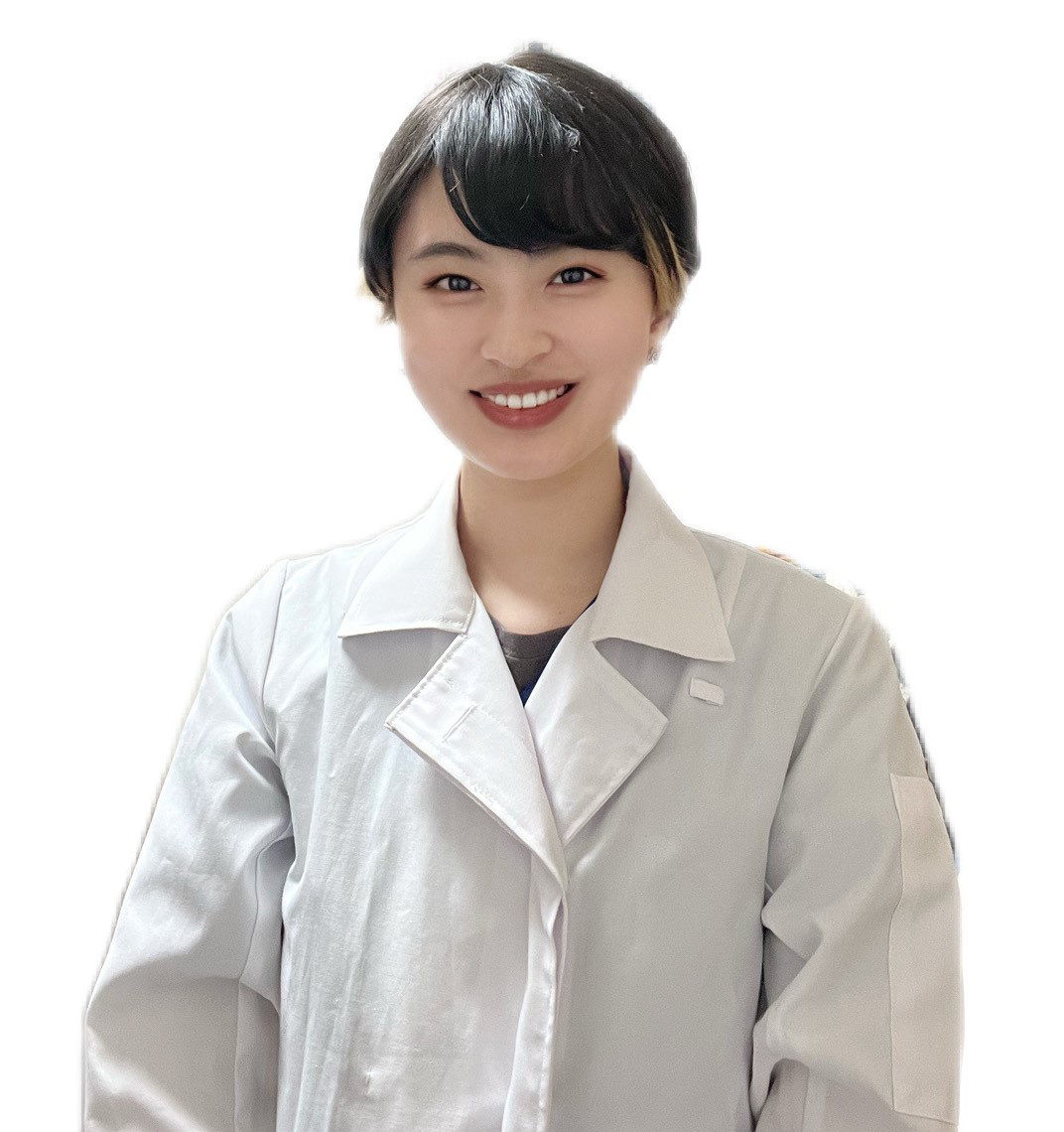コラム - 記事
小児期の機能的マウスピース型矯正装置プレオルソの概要とメリットデメリット
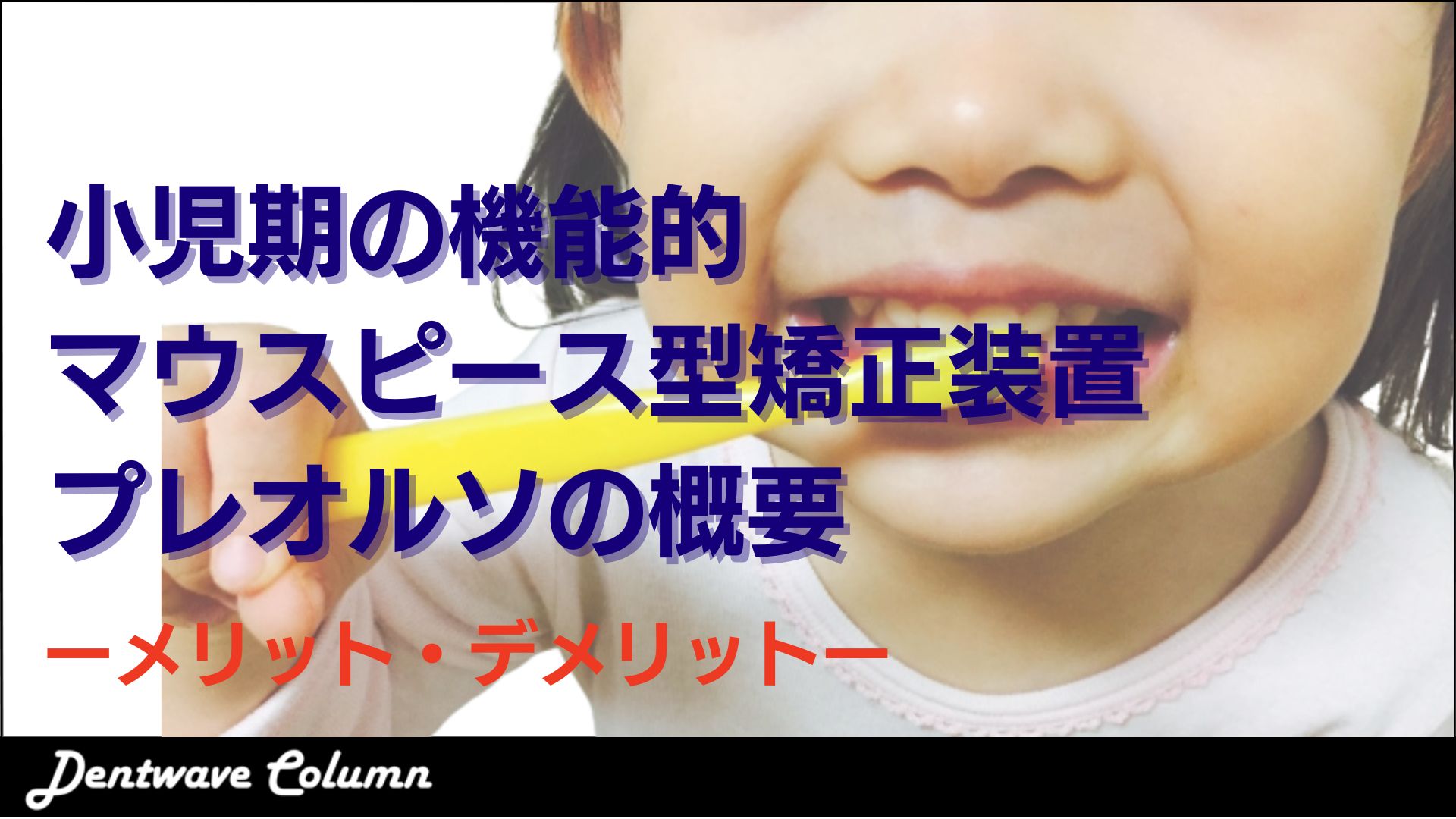
プレオルソとは
プレオルソは、主に6〜8歳頃の矯正治療で使用される矯正装置で、柔らかいシリコン素材で作られたマウスピース型の装置です。歯並びだけでなく、顎の成長や口腔周りの筋肉の発達を促す機能も備えています
使用方法
プレオルソは、基本的に夜間に装着することで効果を発揮します。日中も合わせて数時間装着することで、さらに効果を高めることができます
歯列矯正のプレオルソの適応年齢について
プレオルソの適応年齢は、一般的に6歳から10歳とされています。この時期は、小児の歯が永久歯に生え変わる段階であり、歯列や顎の成長が活発な時期です。プレオルソは適切な時期に開始することで、より効果を発揮します。
プレオルソを適切な時期に始める利点
①成長期の歯と顎の柔軟性を活かせる
6〜10歳の小児は、歯や顎の骨がまだ成長中であり、柔軟性が高い状態です。そのため、プレオルソを使用することで、歯や顎の位置を効率的に修正することができます。
②将来的な矯正治療への一歩となる
小児期よりプレオルソを使用することで将来的な矯正治療の必要性を減らすことができます。また、早期の介入により、複雑な矯正治療を避けることができる場合もあります。
③永久歯が生えてくるスペースの確保
乳歯が抜け、永久歯が生えてくる過程で、歯並びや咬み合わせの問題を予防または軽減することができます。これにより、永久歯がより正しい位置に生えるよう誘導することが可能です。
④指しゃぶりなどの悪習癖を改善できる
指しゃぶり、口呼吸や舌の位置の異常など、歯並びに悪影響を与える習癖を矯正することが可能です。特に指しゃぶりについては悩んでいる親御さんも多いため、プレオルソを使用することで、強制的に悪習癖をやめさせることができるとも言えるでしょう。
プレオルソのメリット
①自然な成長を促進
プレオルソは、歯や顎の自然な成長を促進する設計になっています。これにより、将来的な大規模な矯正治療の必要性を減らすことができます。
② 痛みが少ない
従来のブラケット矯正と異なり、プレオルソは柔らかいシリコンで作られているため、装着時の痛みや不快感が少ないです。これにより、小児が矯正装置を嫌がることが減ります。
③取り外し可能
プレオルソは取り外し可能なため、食事や歯磨きの際に装置を外すことができます。これにより、口腔内の清潔を保ちやすくなります。
④学校など外に持って行く必要がない
プレオルソは夜間寝る時のみの使用が推奨されることが多く、日中の活動には支障をきたさない点もメリットです。
プレオルソのデメリット
①適応外のケースもある
プレオルソは万能ではなく、すべての歯列矯正の問題に対応できるわけではありません。例えば、重度の歯列不正や顎の成長異常がある場合は、他の矯正治療方法が必要になることがあります。
②装着の習慣化が必要
プレオルソの効果を最大限に引き出すためには、定期的な装着が必要です。しかし、小児が装着を怠ると効果が減少します。そのため保護者の方のサポートが欠かせません。
③装置の管理が必要
取り外し可能なため、紛失や破損のリスクがあります。特に小さな小児の場合、装置の管理が難しく、間違えて捨ててしまったり、ペットを飼っているご家庭の場合、ペットが噛んでしまったりする可能性もあります。
④話しにくい場合がある
装置を装着した状態で話すと、発音が困難になることがあります。話すことで頬や顎の筋肉が鍛えられ、プレオルソの効果を発揮してくれるというメリットもある反面、話しにくいことが嫌で小児が装置の装着を嫌がることもあります。
⑤夜寝づらい場合がある
プレオルソは初めて使用する小児にとっては違和感が強く、就寝時に落ち着かないことがあります。その結果、睡眠の質が低下し、翌日の疲労感が増す可能性があります。さらに、プレオルソが口腔内に違和感を与えることで、無意識に取り外してしまうこともあり、矯正効果が十分に得られないリスクもあります。
まとめ
プレオルソは、小児期の歯並びや顎の成長をサポートする効果的な矯正装置です。自然な成長を促進し、痛みが少なく、取り外し可能な点が大きなメリットです。しかし、効果が限定的であり、装着の習慣化や管理が必要な点はデメリットとして挙げられます。
プレオルソを取り入れている歯科医院でお勤めの歯科医師・歯科衛生士の皆さんは、小児患者のモチベーションを保つために適したお声がけをしていかなければなりません。
関連記事
-

-
【プレスリリース】「ミュゼホワイトニング」サービス終了に伴い、歯科医師主導の新ブランド「ドクターズホワイトニング」始動 ~独自性と医療品質を両立できる、選ばれるホワイトニングブランドへ~
-
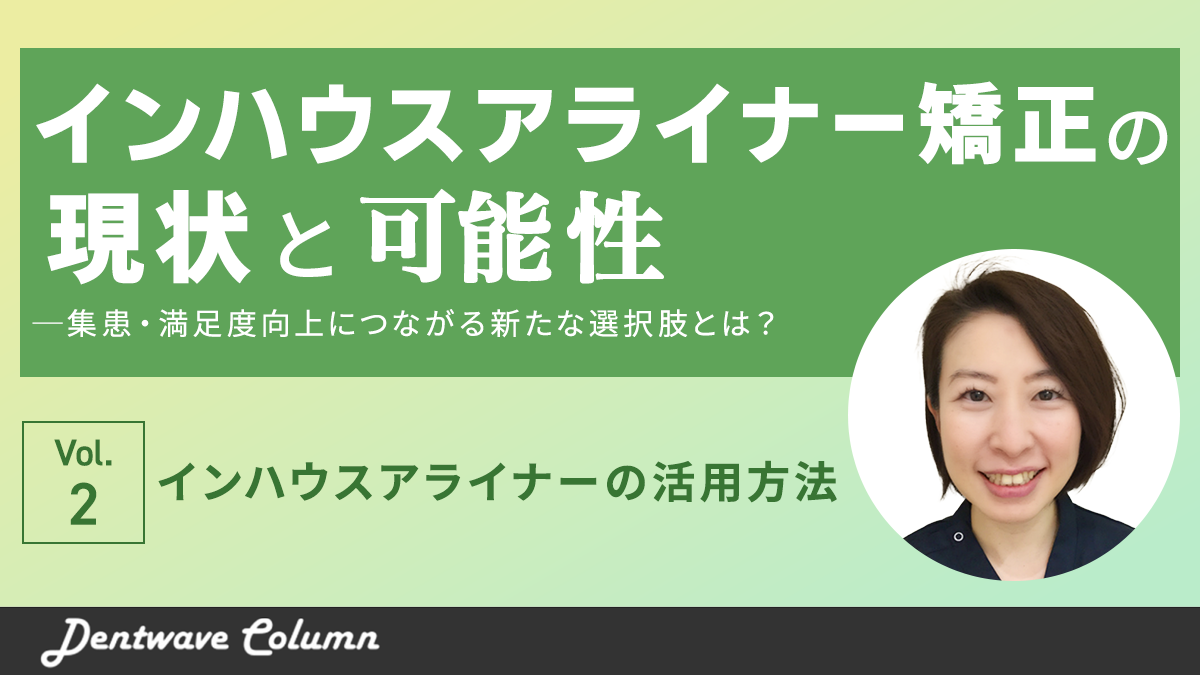
-
インハウスアライナー矯正の現状と可能性 ―集患・満足度向上につながる新たな選択肢とは?― Vol2 インハウスアライナーの活用方法
-
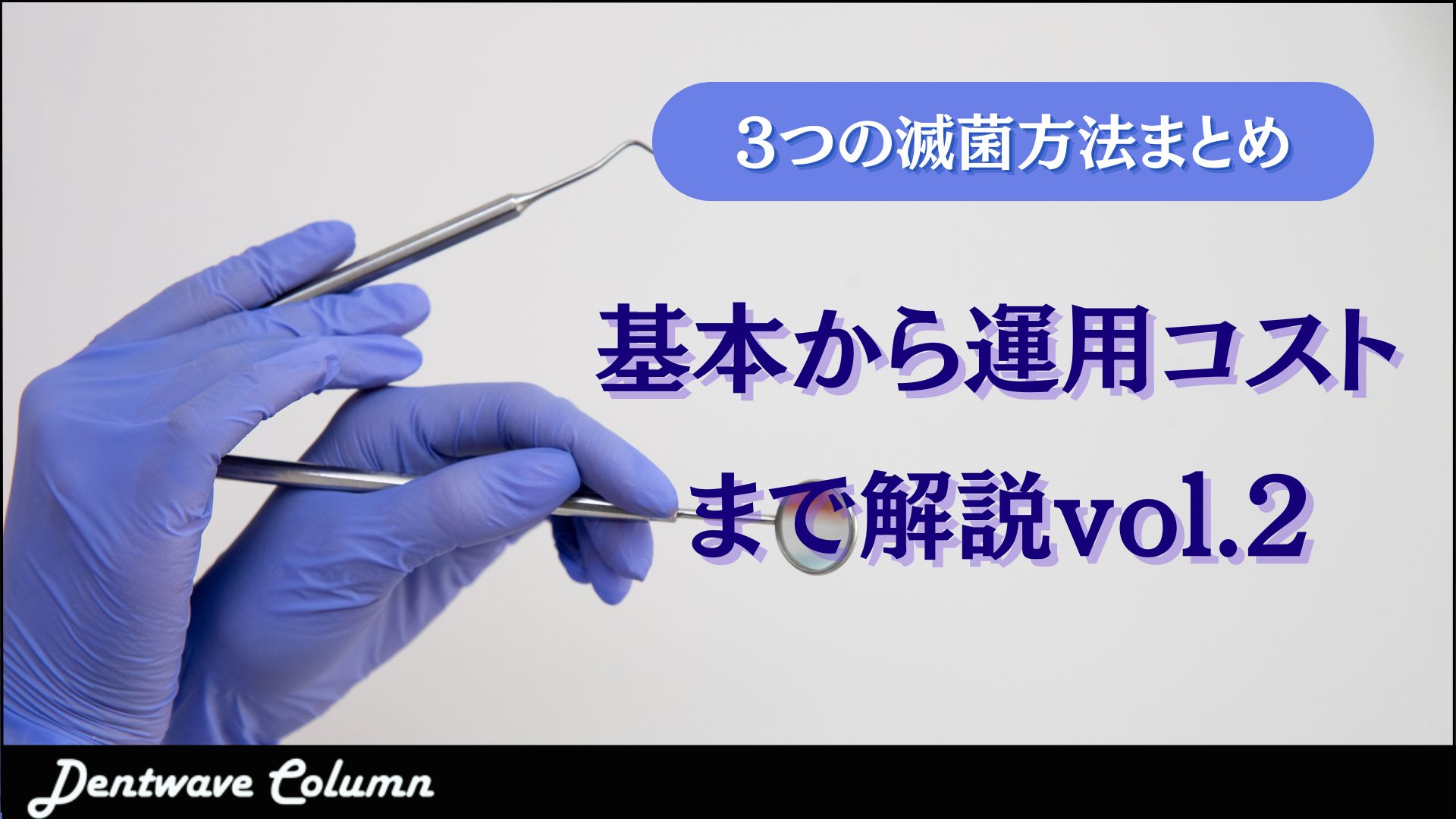
-
【3つの滅菌方法まとめ】基本から運用コストまで解説vol.2
-
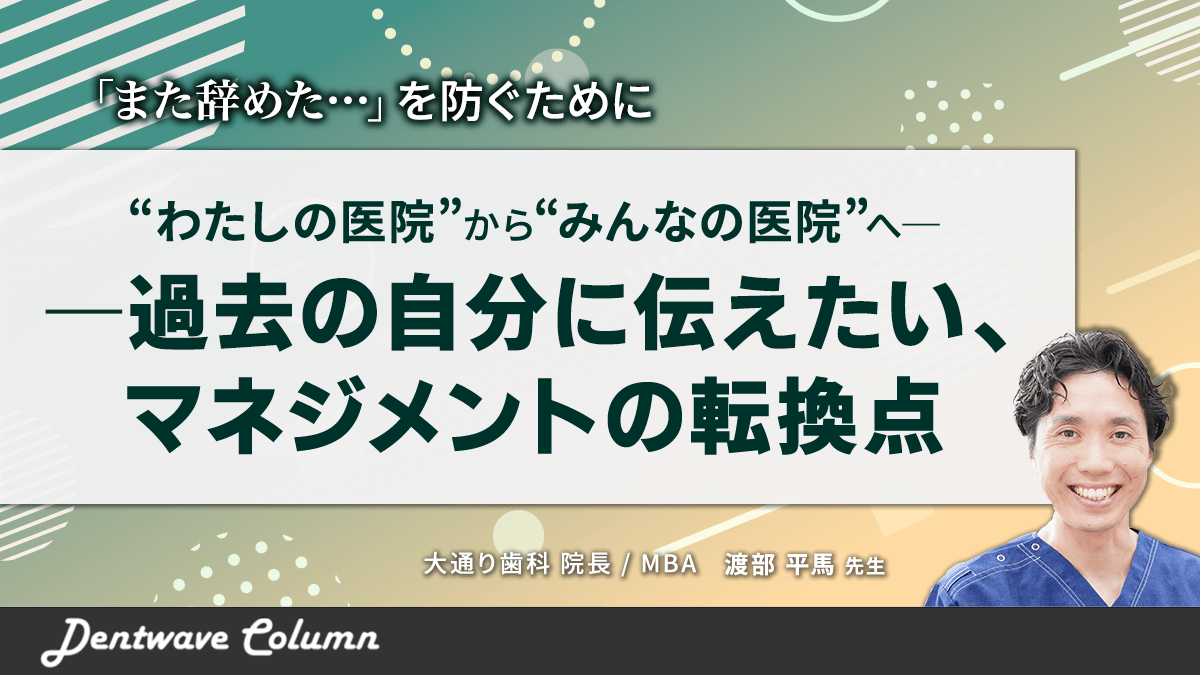
-
「また辞めた…」を防ぐために ― “わたしの医院”から“みんなの医院”へ ──過去の自分に伝えたい、マネジメントの転換点 ―
-

-
【プレスリリース】大阪矯正歯科グループ、最新のAI活用マウスピース矯正「スマーティー(Smartee)」を6月より導入 ~グローバル実績と最先端テクノロジーで、短期間かつ精密な歯科矯正を実現~
-
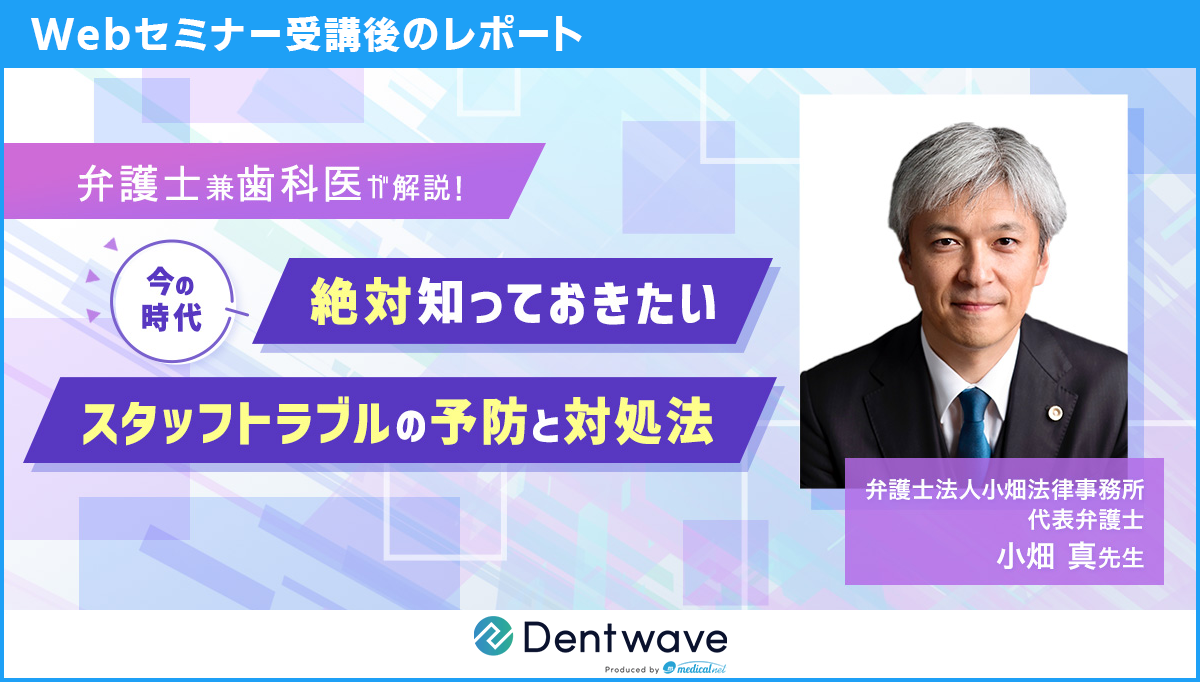
-
Webセミナー受講後のレポート 弁護士兼歯科医が解説!今の時代絶対知っておきたいスタッフトラブルの予防と対処法
-
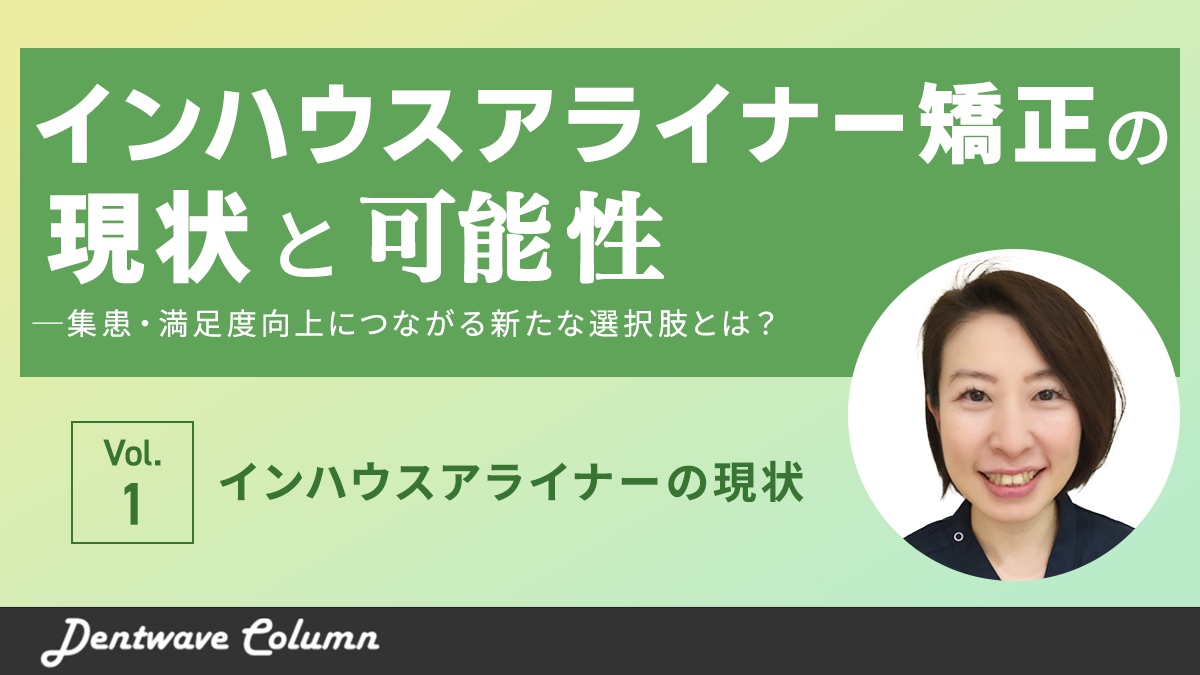
-
インハウスアライナー矯正の現状と可能性 ―集患・満足度向上につながる新たな選択肢とは?― Vol1 インハウスアライナーの現状
-

-
【プレスリリース】株式会社OSSTEM JAPAN、「第43回日本顎咬合学会学術大会・総会」にて口腔保健向上のためデンタルフロス800個を寄贈