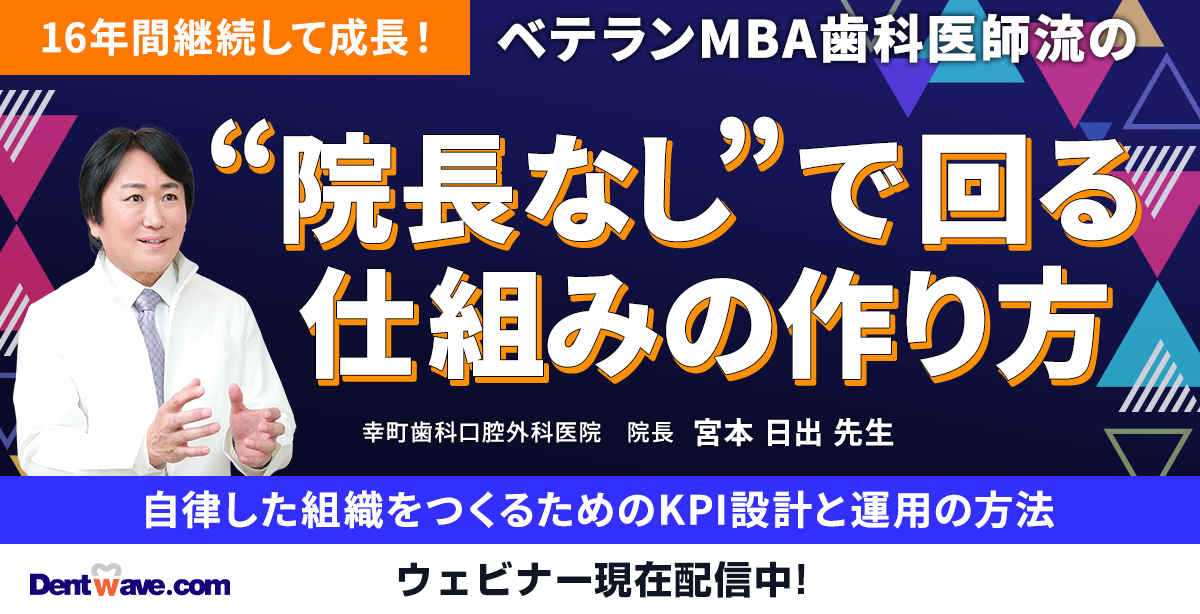第3回 事業承継や家族の絆も脅かす相続問題
カテゴリー
記事提供
© Dentwave.com
相続対策で最も大事なことは遺産分割です。相続税は二の次といっても過言ではないと思います。しかし、相続税の負担は最大で55%(平成27年以降)となり、相当な負担となることは間違いありません。そこで、今回は相続税の負担を大きく減額することが可能となる小規模宅地等の特例について記載したいと思います。
小規模宅地等の特例とは
相続が発生し、相続税を納付するために、生活の基盤となっている住宅や事業用の土地を処分しなければならないようなことがあっては、事業承継が困難となる場合や生活基盤が奪われてしまうことになりかねません。
そこで、相続人が事業又は居住を継続していく上で欠くことのできない資産については一定の限度面積の範囲内の部分について、相続税の計算において相続税財産の課税価格から一定の減額ができる特例があります。この特例を小規模宅地等の特例といいます。
小規模宅地等の特例は適用要件が複雑すぎる
小規模宅地等の特例は条件に合致すれば、被相続人(お亡くなりになった人)の事業用(クリニックの敷地等で条件によっては医療法人が使用している場合も含む)や居住用(自宅)の宅地については、相続財産の評価額から最大80%減、駐車場等の貸付用の敷地については、評価額から最大50%減されるのですが、適用条件が非常に複雑です。
> 小規模宅地等の特例について詳しくはこちら
医療機関における【小規模宅地等の特例の落とし穴】
小規模宅地等の特例が適用できるか、できないかによって、納付する相続税の額が大きく変動してしまうことも多々あります。
以下の2つの例はこの小規模宅地等の特例が適用できない事例です。
事例1 個人の診療所で事前に事業承継をしていた場合
父親(被相続人)が個人経営をしていた診療所(息子も勤務)を父親の体力的な問題から生前に息子に事業を承継し、ご自身は引退した場合です。この診療所の土地建物は父親が所有し(相続直前まで)息子に無償で使用させており、息子もそこで個人診療所を引き続き経営している場合
 上記の場合、父親と息子が同居や生計を一(別居でも父親の生活費の大半を息子が仕送り等をしている場合)としていれば、【同一生計親族の事業用の宅地】のため、限度面積(400㎡まで80%評価減が可能です。しかし、別生計(別居で生計も別)の場合は、評価減が一切使えないこととなります。
事例2 父親が経営している医療法人(持ち分の定めのない医療法人)への貸し付けの場合
事例1のケースが、個人経営ではなく医療法人の場合ですが、その医療法人が【持ち分の定めのある医療法人】である場合は条件を満たせば【特定同族会社事業用宅地等】に該当し、限度面積(400㎡)まで80%評価減が可能となります。※しかし、その【医療法人が【持ち分の定めのない医療法人】の場合は、一定の条件を満たさないため評価減の適用を受けることができません。
一定の条件とは、
(1) 相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有していること。
(2) 相続税の申告期限において、その法人の役員である親族が相続等により当該宅地等を取得。
(3) その宅地等を相続税の申告期限まで有し、かつ、引き続きその法人の事業のように供していること。
>医療法人制度の詳細はこちら
遺産分割と小規模宅地等の特例の関係
最後に遺産分割についてですが、小規模宅地等の特例は相続税を計算するうえでの特例です。この特例を適用した宅地等の評価額は、本来の時価とは著しく乖離します。
したがって、遺産分割時では小規模宅地等の特例による評価減は考慮しないで分割を決める場合が大半です。
また、遺留分減殺請求を受けた場合の当該宅地等も同様です。
今回は相続税の課税価格の計算上の特例である小規模宅地等の特例について記載してみました。制度の適用要件等はかなり複雑なため割愛をさせていただきました。
小規模宅地等の特例が適用できるか否かにより、大きく相続税の納付額が左右するのも現実です。
今回は注意点の一部を記載しましたが、事例1.2に記載した他にも類似したケースであっても適用が異なる場合がございます。かなり奥が深い規定ですので、ご興味がある場合はお気軽にご相談いただければ幸いです。
上記の場合、父親と息子が同居や生計を一(別居でも父親の生活費の大半を息子が仕送り等をしている場合)としていれば、【同一生計親族の事業用の宅地】のため、限度面積(400㎡まで80%評価減が可能です。しかし、別生計(別居で生計も別)の場合は、評価減が一切使えないこととなります。
事例2 父親が経営している医療法人(持ち分の定めのない医療法人)への貸し付けの場合
事例1のケースが、個人経営ではなく医療法人の場合ですが、その医療法人が【持ち分の定めのある医療法人】である場合は条件を満たせば【特定同族会社事業用宅地等】に該当し、限度面積(400㎡)まで80%評価減が可能となります。※しかし、その【医療法人が【持ち分の定めのない医療法人】の場合は、一定の条件を満たさないため評価減の適用を受けることができません。
一定の条件とは、
(1) 相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有していること。
(2) 相続税の申告期限において、その法人の役員である親族が相続等により当該宅地等を取得。
(3) その宅地等を相続税の申告期限まで有し、かつ、引き続きその法人の事業のように供していること。
>医療法人制度の詳細はこちら
遺産分割と小規模宅地等の特例の関係
最後に遺産分割についてですが、小規模宅地等の特例は相続税を計算するうえでの特例です。この特例を適用した宅地等の評価額は、本来の時価とは著しく乖離します。
したがって、遺産分割時では小規模宅地等の特例による評価減は考慮しないで分割を決める場合が大半です。
また、遺留分減殺請求を受けた場合の当該宅地等も同様です。
今回は相続税の課税価格の計算上の特例である小規模宅地等の特例について記載してみました。制度の適用要件等はかなり複雑なため割愛をさせていただきました。
小規模宅地等の特例が適用できるか否かにより、大きく相続税の納付額が左右するのも現実です。
今回は注意点の一部を記載しましたが、事例1.2に記載した他にも類似したケースであっても適用が異なる場合がございます。かなり奥が深い規定ですので、ご興味がある場合はお気軽にご相談いただければ幸いです。
 上記の場合、父親と息子が同居や生計を一(別居でも父親の生活費の大半を息子が仕送り等をしている場合)としていれば、【同一生計親族の事業用の宅地】のため、限度面積(400㎡まで80%評価減が可能です。しかし、別生計(別居で生計も別)の場合は、評価減が一切使えないこととなります。
事例2 父親が経営している医療法人(持ち分の定めのない医療法人)への貸し付けの場合
事例1のケースが、個人経営ではなく医療法人の場合ですが、その医療法人が【持ち分の定めのある医療法人】である場合は条件を満たせば【特定同族会社事業用宅地等】に該当し、限度面積(400㎡)まで80%評価減が可能となります。※しかし、その【医療法人が【持ち分の定めのない医療法人】の場合は、一定の条件を満たさないため評価減の適用を受けることができません。
一定の条件とは、
(1) 相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有していること。
(2) 相続税の申告期限において、その法人の役員である親族が相続等により当該宅地等を取得。
(3) その宅地等を相続税の申告期限まで有し、かつ、引き続きその法人の事業のように供していること。
>医療法人制度の詳細はこちら
遺産分割と小規模宅地等の特例の関係
最後に遺産分割についてですが、小規模宅地等の特例は相続税を計算するうえでの特例です。この特例を適用した宅地等の評価額は、本来の時価とは著しく乖離します。
したがって、遺産分割時では小規模宅地等の特例による評価減は考慮しないで分割を決める場合が大半です。
また、遺留分減殺請求を受けた場合の当該宅地等も同様です。
今回は相続税の課税価格の計算上の特例である小規模宅地等の特例について記載してみました。制度の適用要件等はかなり複雑なため割愛をさせていただきました。
小規模宅地等の特例が適用できるか否かにより、大きく相続税の納付額が左右するのも現実です。
今回は注意点の一部を記載しましたが、事例1.2に記載した他にも類似したケースであっても適用が異なる場合がございます。かなり奥が深い規定ですので、ご興味がある場合はお気軽にご相談いただければ幸いです。
上記の場合、父親と息子が同居や生計を一(別居でも父親の生活費の大半を息子が仕送り等をしている場合)としていれば、【同一生計親族の事業用の宅地】のため、限度面積(400㎡まで80%評価減が可能です。しかし、別生計(別居で生計も別)の場合は、評価減が一切使えないこととなります。
事例2 父親が経営している医療法人(持ち分の定めのない医療法人)への貸し付けの場合
事例1のケースが、個人経営ではなく医療法人の場合ですが、その医療法人が【持ち分の定めのある医療法人】である場合は条件を満たせば【特定同族会社事業用宅地等】に該当し、限度面積(400㎡)まで80%評価減が可能となります。※しかし、その【医療法人が【持ち分の定めのない医療法人】の場合は、一定の条件を満たさないため評価減の適用を受けることができません。
一定の条件とは、
(1) 相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有していること。
(2) 相続税の申告期限において、その法人の役員である親族が相続等により当該宅地等を取得。
(3) その宅地等を相続税の申告期限まで有し、かつ、引き続きその法人の事業のように供していること。
>医療法人制度の詳細はこちら
遺産分割と小規模宅地等の特例の関係
最後に遺産分割についてですが、小規模宅地等の特例は相続税を計算するうえでの特例です。この特例を適用した宅地等の評価額は、本来の時価とは著しく乖離します。
したがって、遺産分割時では小規模宅地等の特例による評価減は考慮しないで分割を決める場合が大半です。
また、遺留分減殺請求を受けた場合の当該宅地等も同様です。
今回は相続税の課税価格の計算上の特例である小規模宅地等の特例について記載してみました。制度の適用要件等はかなり複雑なため割愛をさせていただきました。
小規模宅地等の特例が適用できるか否かにより、大きく相続税の納付額が左右するのも現実です。
今回は注意点の一部を記載しましたが、事例1.2に記載した他にも類似したケースであっても適用が異なる場合がございます。かなり奥が深い規定ですので、ご興味がある場合はお気軽にご相談いただければ幸いです。 記事提供
© Dentwave.com



 LINE公式アカウントはじめました!
LINE公式アカウントはじめました!
 歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
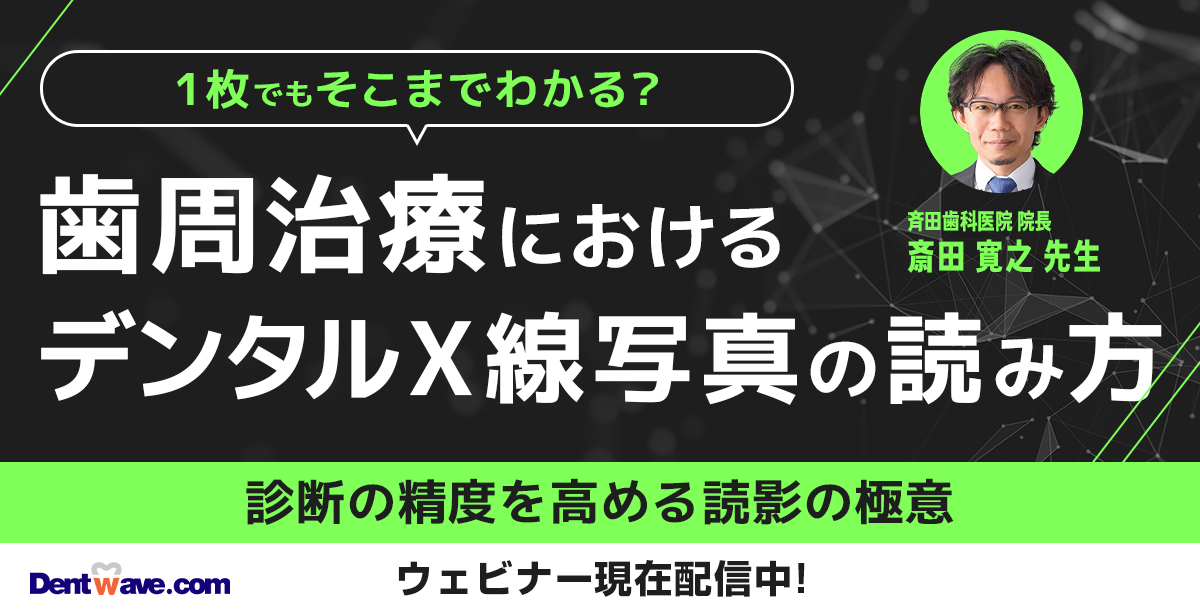 1枚でもそこまでわかる?歯周治療におけるデンタルX線写真の読み方 診断の精度を高める読影の極意
1枚でもそこまでわかる?歯周治療におけるデンタルX線写真の読み方 診断の精度を高める読影の極意
 ジルコニアクラウンの支台歯形成のコツとそのワケ 術前の診査から形成後までのポイント集
ジルコニアクラウンの支台歯形成のコツとそのワケ 術前の診査から形成後までのポイント集