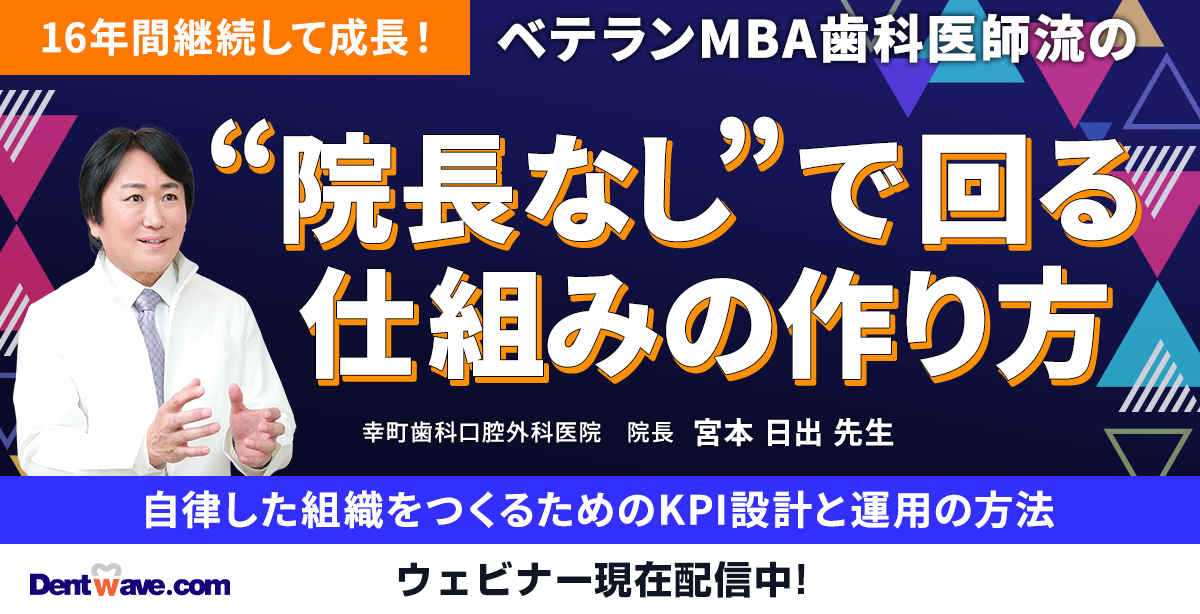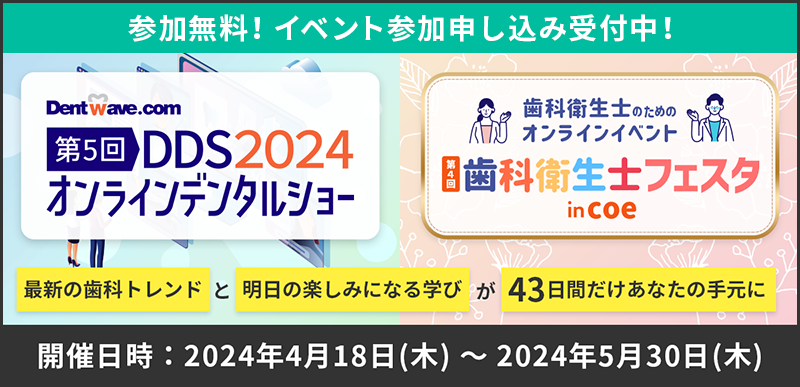フッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法の変更
この記事は
無料会員限定です。
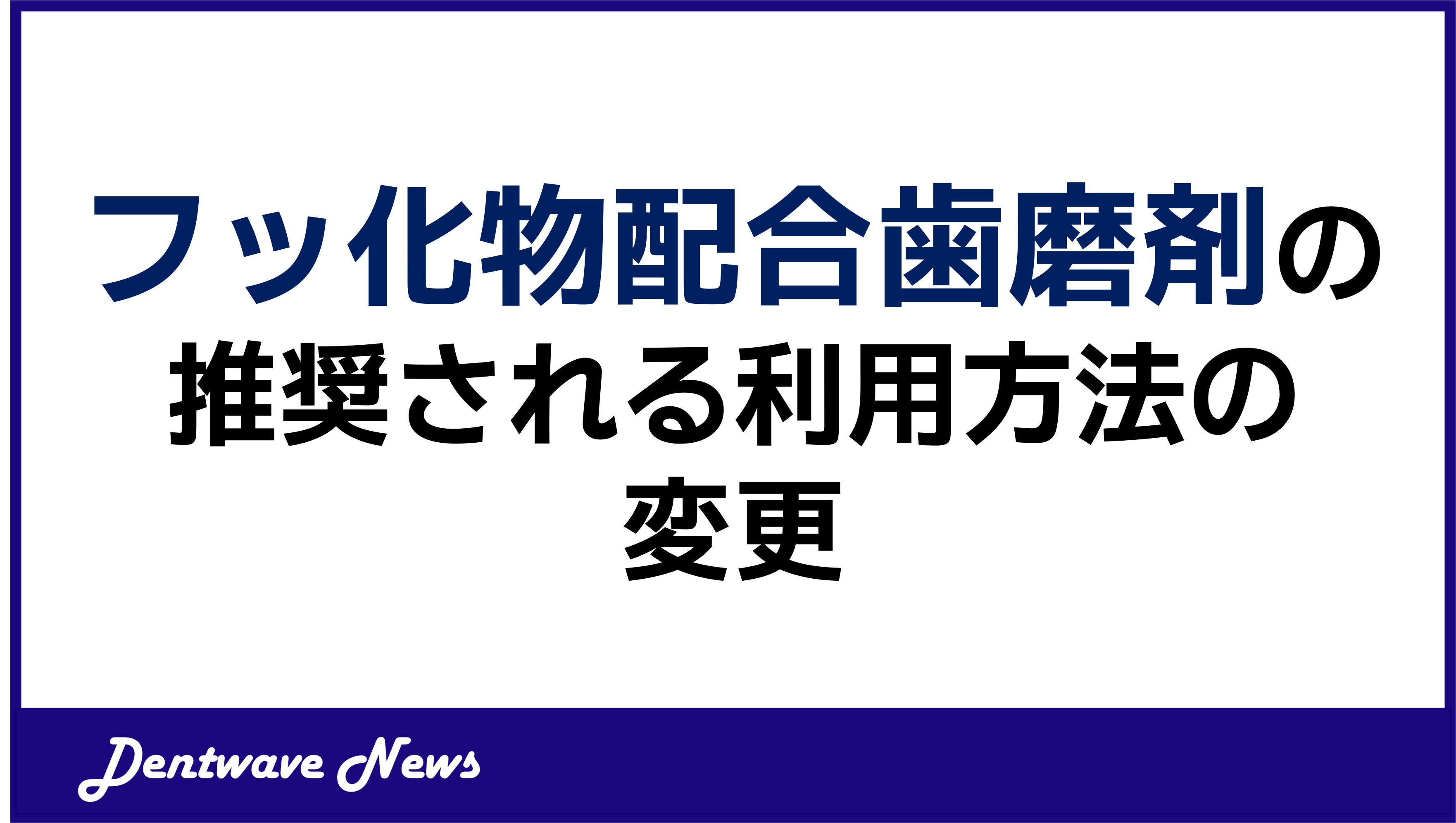
日本口腔衛生学会と日本小児歯科学会、日本保存学会、日本老年歯科学会は、2023年1月に「4学会合同のフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法」を発表しました。
日本では、う蝕予防のためのフッ化物応用が幅広く普及しており、中でもフッ化物配合の歯磨剤は、多く使用されています。
今回、4学会は合同で、フッ化物応用に関する研究のアップデートや、市販歯磨剤におけるフッ化物濃度の変更、国際的な推奨の更新を受け、日本のう蝕予防および治療を専門とする4学会が合同で、現在の日本において推奨されるフッ化物配合歯磨剤の利用方法をまとめたものが発表されました。
これまでは500ppm(泡タイプであれば1,000ppm)でしたが、今回変更され1,000ppmの濃度が推奨されています。
これまでは500ppm(泡タイプであれば1,000ppm)でしたが、変更後は1,000ppmの濃度が推奨されています。
これまでは、6~14歳は500〜1,000ppmで、15歳以上は1,000ppm~1,500ppmでしたが、変更後は6〜14歳の枠が廃止され、6歳以上であれば1,500ppmのフッ素濃度が推奨されています。
これまでは、切った爪程度の使用量が推奨されていましたが、変更後は米粒程度(1〜2mm程度)に変更となりました。
これまでは、5mm程度の使用量が推奨されていましたが、今回もグリンピース程度(5mm程度)となっています。
これまでは、6〜14歳は1cm程度で、15歳以上は2cmの使用量が推奨されていましたが、変更後は歯ブラシ全体(1.5〜2cm)となりました。
それぞれの使用方法や注意事項も以下の通りの記載がありました。
・就寝時を含めて1日2回のブラッシングを行う。
・1,000ppmの歯磨剤をごく少量使用し、ブラッシング後はティッシュ等で軽く拭き取りを行っても良い。
・歯磨剤はお子さんの手の届かない場所に保管する。
・歯科医院等で専門家のアドバイスを受ける
・就寝時を含めて1日2回のブラッシングを行う。
・ブラッシング後は、口の中の歯磨剤を軽く吐き出す。
・うがいを行う場合は、少量の水で1回のみ。
・お子さんが歯磨剤の適切量を出せない場合は、保護者が行う。
・就寝時を含めて1日2回のブラッシングを行う。
・ブラッシング後は、口の中の歯磨剤を軽く吐き出す。
・うがいを行う場合は、少量の水で1回のみ。
・チタン製の歯科治療(インプラント等)の既往歴があっても、歯がある場合はフッ化物配合の歯磨剤を使用する。
今回の発表では、フッ化物配合の歯磨剤と関連のある3つのテーマでも、それぞれ見解が記載されていました。
今回発表されたフッ化物配合歯磨剤の推奨に関しては、現在国際的に推奨されているフッ素配合歯磨剤の推奨を参考にし、日本の状況を加味して作成されました。
歯磨剤のフッ素濃度は、高ければ高いほどう蝕予防効果は高いと言われていますが、飲み込みによるリスクを考慮し、年齢別にわかりやすく推奨を行っています。
歯の形成期にあたる乳幼児や小児は、歯のフッ素症リスクとう蝕予防のメリットをそれぞれのバランスを考慮し、その際にメリットのほうが上回ると考えられる利用方法や量が、推奨されています。
また、乳幼児が歯磨剤を誤って大量に食べたり飲み込んだりしないように、使用方法や保管場所に対する注意事項も記載があります。
さらに、歯磨剤の国際規格(ISO 11609)では、容器にフッ化物の種類と濃度を表示することが義務づけられていますが、現在日本で市販されている多くの歯磨剤には、配合されているフッ化物濃度が記載されていない製品も多くあります。そのため、日本の製品も国際規格に合わせて、フッ化物濃度の明記が求められています。
日本では使用されていませんが、5,000ppmの高濃度フッ化物配合歯磨剤の有用性が知られており、う蝕等のハイリスク患者への利用が推奨されています。特に、初期の根面う蝕に関しては、進行が停止するエビデンスがあります。歯根面が露出している高齢で、根面う蝕のリスクが高い患者さんに対しては、5,000ppmの歯磨剤が推奨されています。先進国の多くでは、5,000ppmの歯磨剤の処方を歯科医師が行っています。処方箋なしでも購入できる国もあり、日本でも5,000ppmの歯磨剤の販売許可が求められている旨が述べていました。
高濃度で酸性のフッ化物歯面塗布はチタンインプラントを腐食させると言われていますが、低濃度で中性のフッ化物出はその可能性がないと記載がありました。また、クロルヘキシジンには、う蝕予防効果がないことが報告されており、使用上の注意点もあります。そのため、インプラント治療を行った患者さんにもフッ化物配合歯磨剤の使用が推奨されていることが記載されていました。
フッ素は、臨床や日常で幅広く使用されている虫歯予防方法です。今回の発表に伴い、患者さんに対し有益な情報をいち早く伝えられるように、多くの歯科従事者に、今回のこの学会の発表を知っていただきたいです。
引き続き、各学会の今後の動向に注目していきたいと思います。
出典:4学会合同のフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法-日本口腔衛生学会・日本小児歯科学会・日本歯科保存学会・日本老年歯科医学会

松本歯科大学衛生学院卒業後、一般歯科医院にて勤務。歯科衛生士としてキャリアを重ねる一方で、働き方の多様性を模索していた時にライターという仕事に出会う。
現在は、歯科医院に勤務しながら、ライター活動を行う。
「歯科の専門家の書く分かりやすい記事」をモットーに歯科医院のHP記事やブログ執筆活動を中心に執筆を行なっている。
記事提供
© Dentwave.com


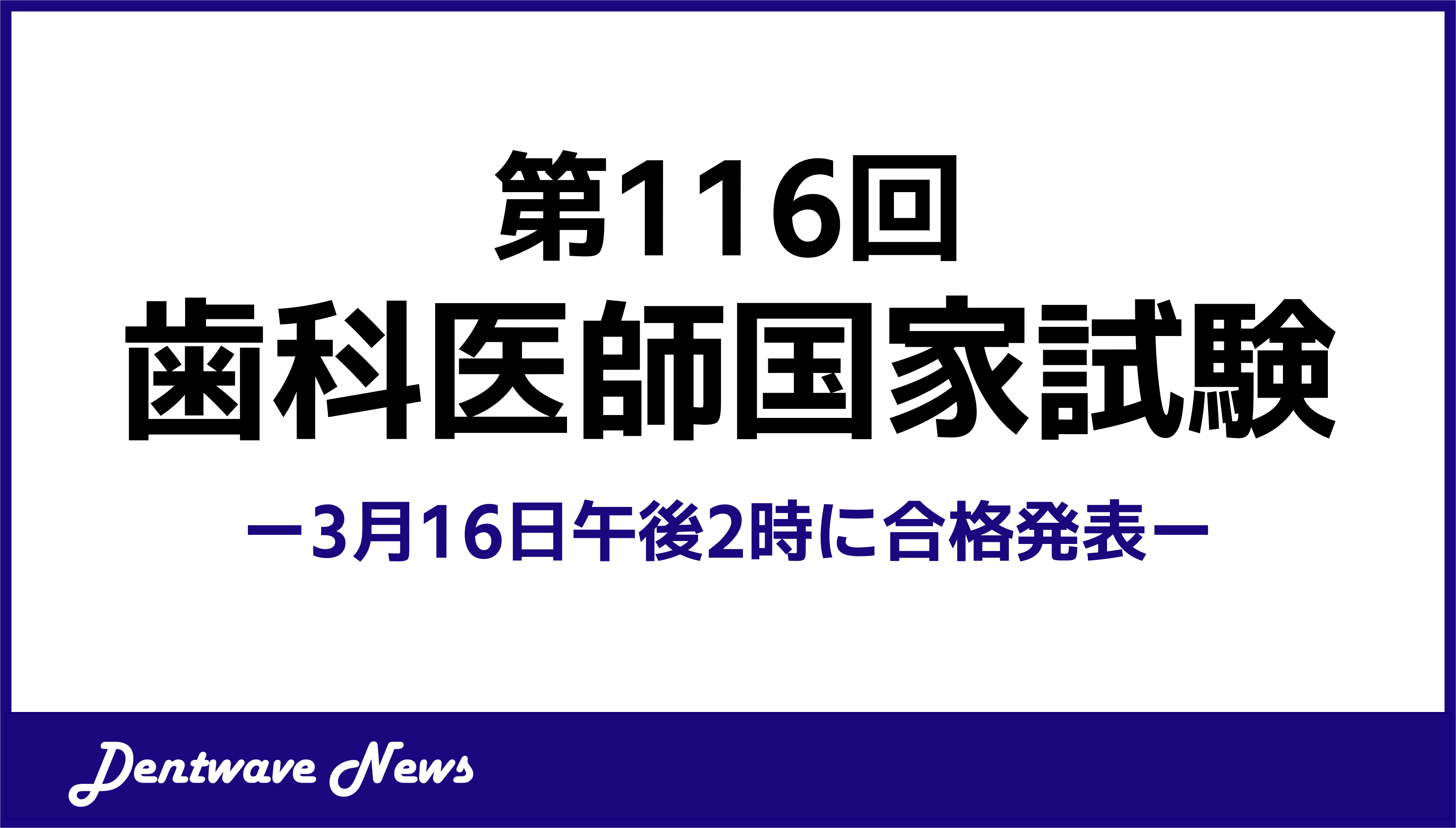
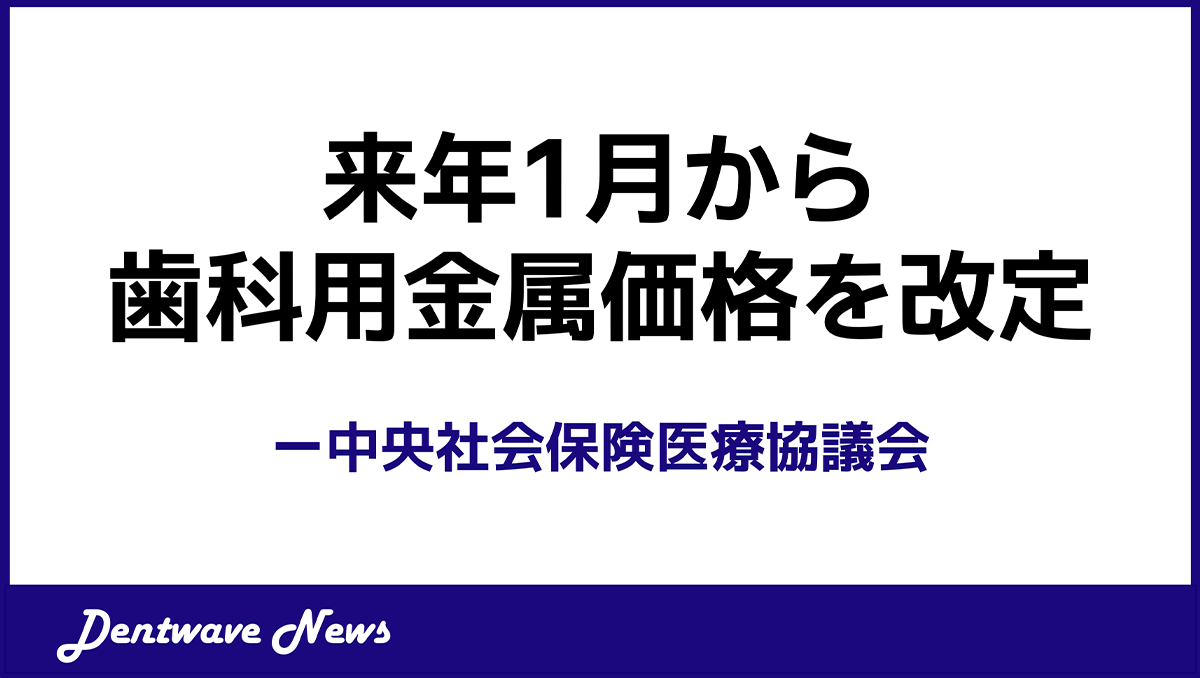

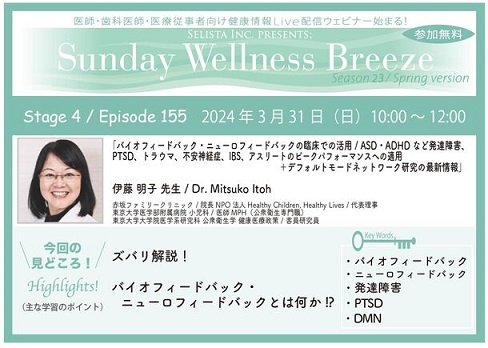






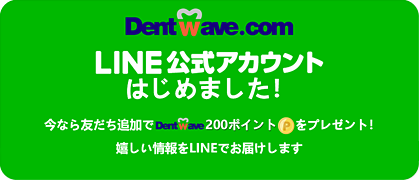 LINE公式アカウントはじめました!
LINE公式アカウントはじめました!
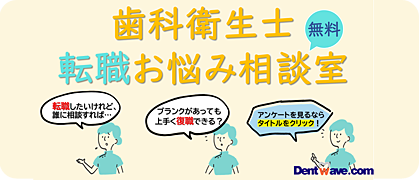 歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
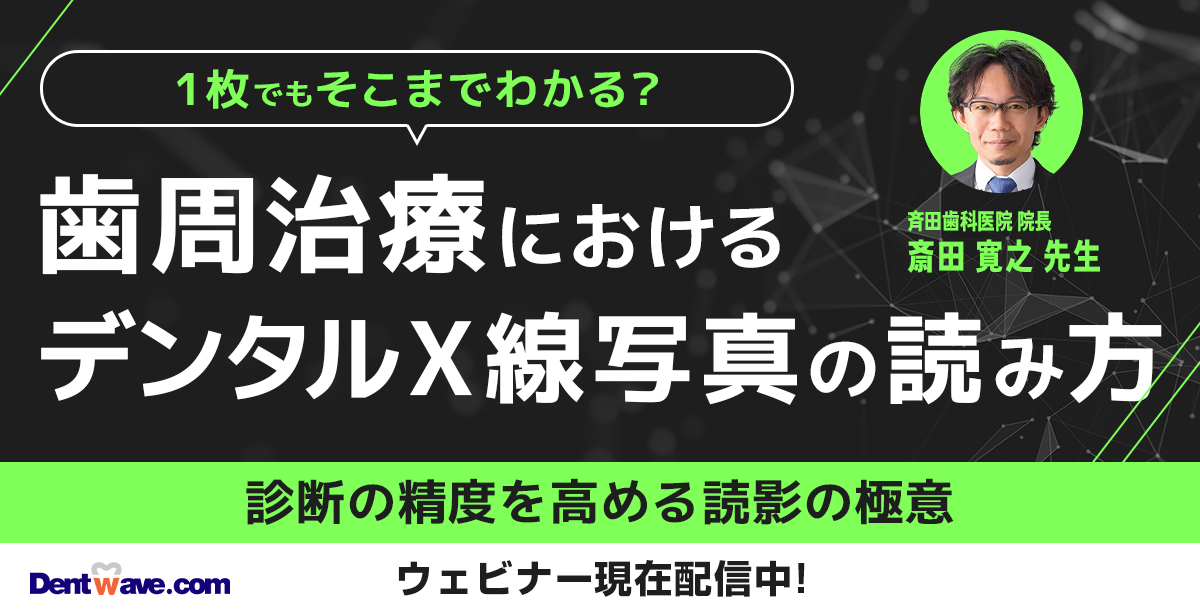 1枚でもそこまでわかる?歯周治療におけるデンタルX線写真の読み方 診断の精度を高める読影の極意
1枚でもそこまでわかる?歯周治療におけるデンタルX線写真の読み方 診断の精度を高める読影の極意
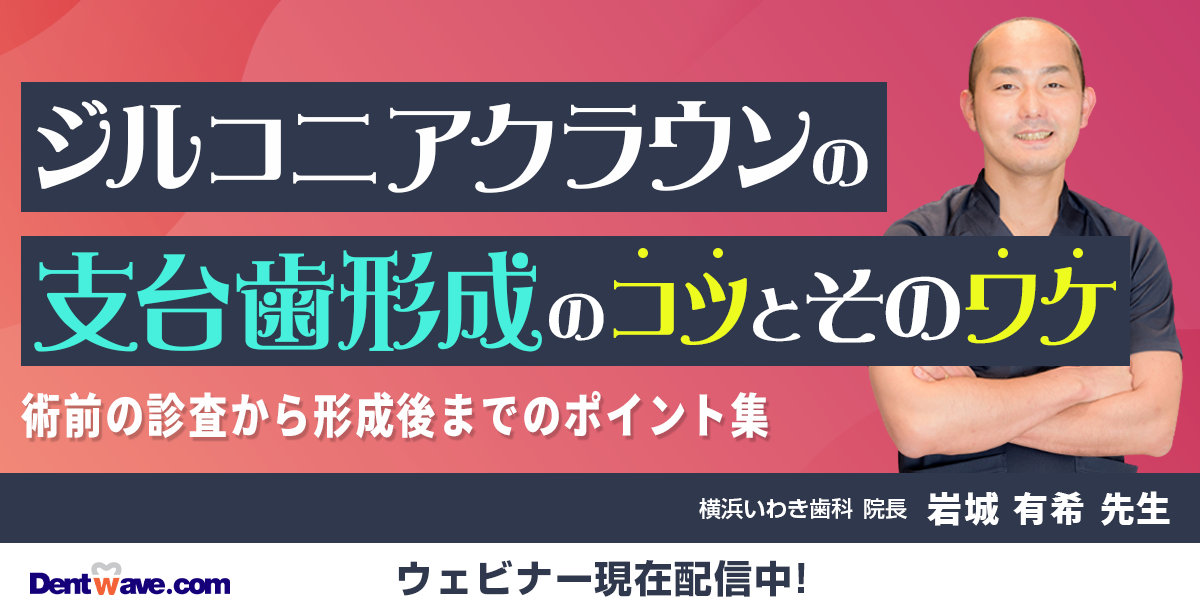 ジルコニアクラウンの支台歯形成のコツとそのワケ 術前の診査から形成後までのポイント集
ジルコニアクラウンの支台歯形成のコツとそのワケ 術前の診査から形成後までのポイント集