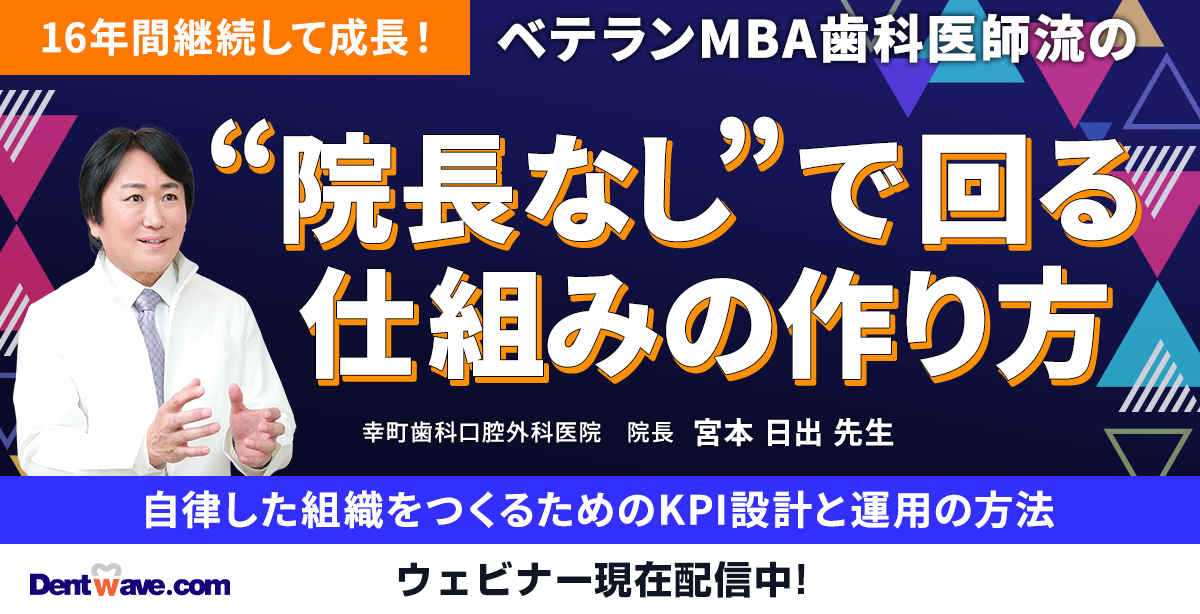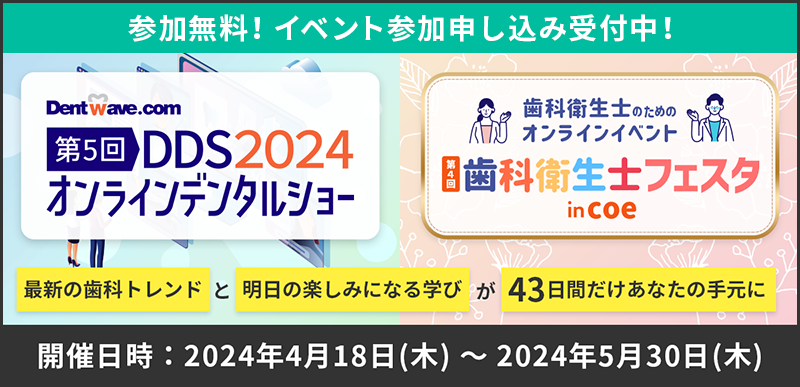この記事は
無料会員限定です。
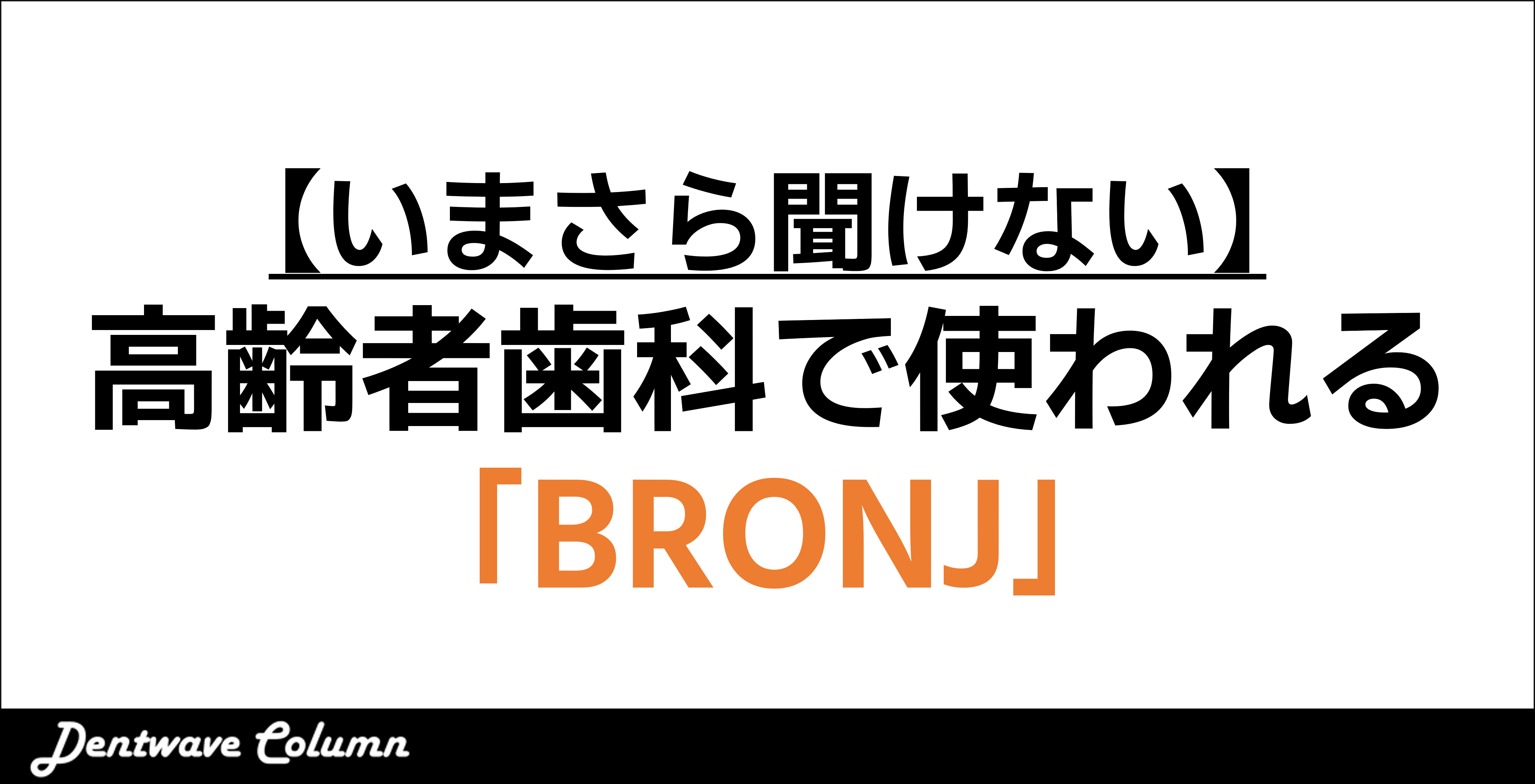
高齢者歯科・在宅歯科診療で使用される略語の中には、普段の歯科診療ではあまり使用されない言葉も多くあるためしっかり意味を確認しておきましょう。
今回は高齢者歯科・在宅診療で使用される略語「BRONJ」について解説します。
ビスフォスフォネート系薬剤関連顎骨壊死(Bisphosphonate Related Osteo Necrosis of the Jew)の略語です。ビスフォスフォネート(以下BP)薬剤を使用している患者が発症する合併症の一つで、抜歯などの外科処置、歯内治療、歯周治療などの後に創傷が正常に治癒しなかったり、歯槽骨の露出や疼痛、軟組織の腫脹などが見られたりする状態です。BRONJの詳しい発生機序は明確にされておらず、確定している予防法もありません。
BP薬剤は悪性腫瘍による高カルシウム血症や骨粗鬆症の治療などに使用される薬剤です。高齢患者(特に女性)においては、骨粗鬆症の治療としてこのBP薬剤を使用している患者が多くみられます。注射と経口の2つの投与方法があり、前者の方が抜歯に関連したBRONJ発症リスクが高いとされています。また米国口腔外科学会では、経口のBP薬剤であっても治療期間が3年を超えるとBRONJの発生リスクが高くなると提言しています。主に使用されているBP薬剤は以下のとおりです。
●注射用BP薬剤
○アレディア
○テイロック
○ビスフォナール
○ゾメタ
●経口BP薬剤
○ダイドロネル
○フォサマック
○ボナロン
○アクトネル
○ベネット
○ボノテオ
○リカルボン
BRONJを防ぐためにも、歯科治療の際は事前にBP薬剤を使用したことがないか問診で確認しておく必要があります。もし内服している場合はいつから内服しているのかを併せて確認しておきましょう。
次回は、同じく高齢者歯科・在宅診療で使用される摂食・嚥下に関する用語について確認していきましょう。
記事提供
© Dentwave.com




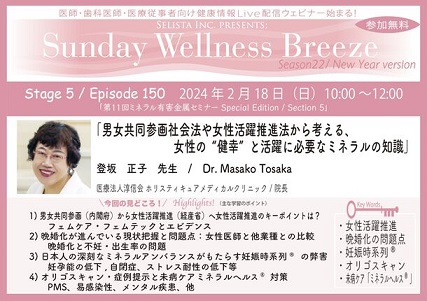





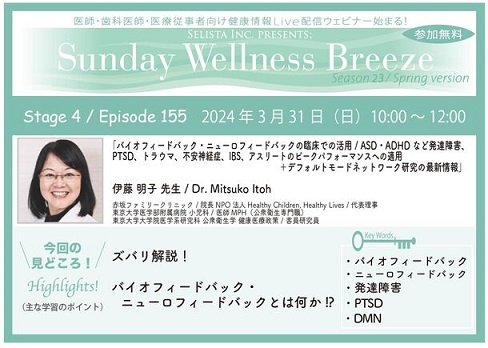

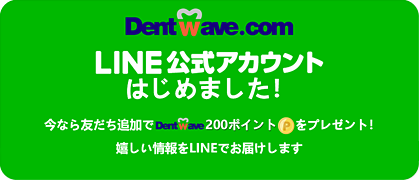 LINE公式アカウントはじめました!
LINE公式アカウントはじめました!
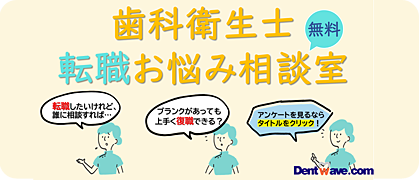 歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室
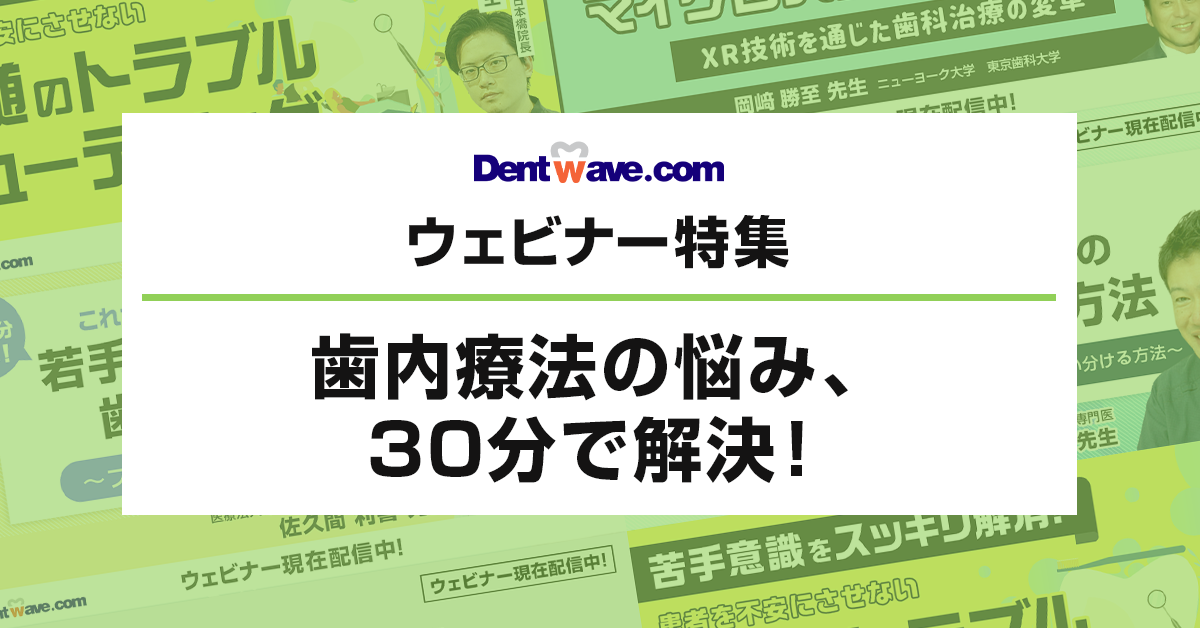 歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
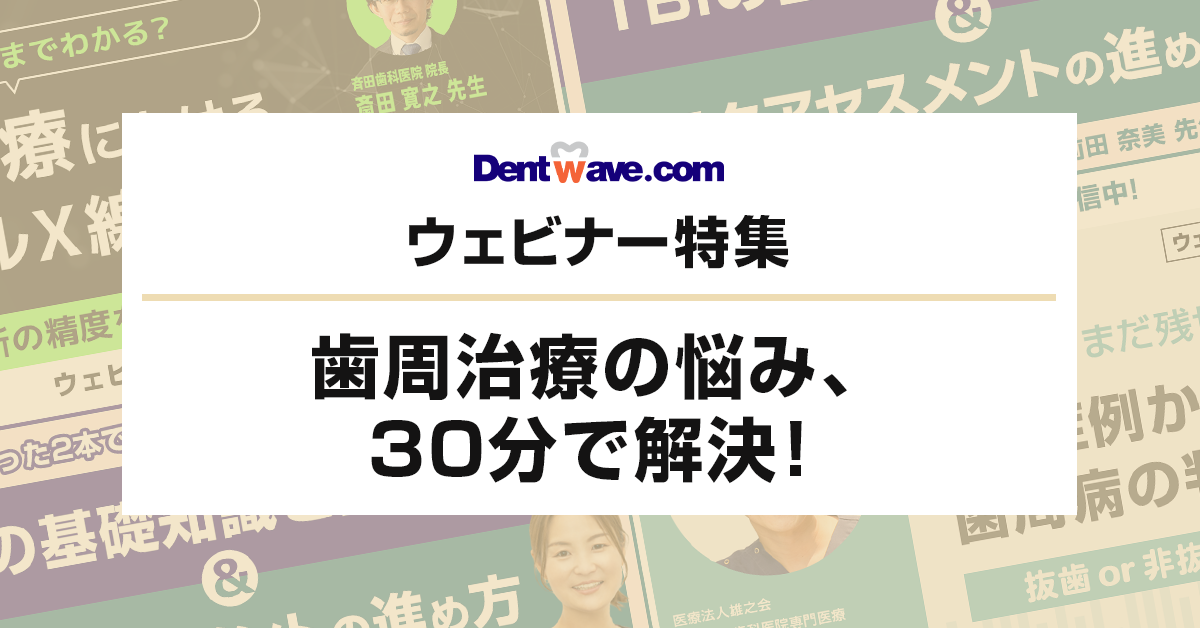 歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。
歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。